
シューマン 交響曲第2番
2011.03.14
交響曲作曲家としての真価
 シューマンの名前を聞いて多くの人がまず思い浮かべる作品は、おそらく「クライスレリアーナ」「謝肉祭」「子供の情景」などのピアノ曲か、「詩人の恋」「女の愛と生涯」「ミルテの花」といった歌曲だろう。この分野での評価には揺るぎないものがある。だが、他方、交響曲の作曲家としてはそこまで評価されることがない。「シューマンは管弦楽の扱いが稚拙だった」というのが定説のようになっている。それを鵜呑みにして、きちんと作品を聴いたことのない人までもが敬遠しだす始末である。こういうイメージは、一度ついてしまうとなかなか拭えないものらしい。
シューマンの名前を聞いて多くの人がまず思い浮かべる作品は、おそらく「クライスレリアーナ」「謝肉祭」「子供の情景」などのピアノ曲か、「詩人の恋」「女の愛と生涯」「ミルテの花」といった歌曲だろう。この分野での評価には揺るぎないものがある。だが、他方、交響曲の作曲家としてはそこまで評価されることがない。「シューマンは管弦楽の扱いが稚拙だった」というのが定説のようになっている。それを鵜呑みにして、きちんと作品を聴いたことのない人までもが敬遠しだす始末である。こういうイメージは、一度ついてしまうとなかなか拭えないものらしい。
とりわけ交響曲第2番に関しては、支離滅裂、中途半端、失敗作、とこれまでさんざんに言われてきた。ほぼ同じ頃に書かれたピアノ協奏曲は傑作として名高いのに、交響曲になるとこうも扱いが悪くなる。なぜか。しばしば言われるようにオーケストレーションのバランス感覚がおかしく、交響曲だとその粗が目立つから? シューマンの管弦楽書法が個性的であることは確かだが、それを悪いと決めつけるのはおかしい。別にモーツァルトやベートーヴェンのように交響曲を作る必要はないのだ。
第2番は、1845年から翌年にかけて、精神病を悪化させていたシューマンがそこからどうにかして立ち直ろうともがきながら書いた作品である。ここで彼はベートーヴェン、シューベルトの影響から一歩脱した、新しいタイプの交響曲を提示しようとしたが、聴衆と評論家の理解を得ることはできなかった。
メンデルスゾーン、チャイコフスキーなど、早い段階からこの作品の魅力に気付いていた人もいないわけではない。とくにチャイコフスキーは、この作品に込められた楽想の美しさと構成の大胆さに最上級の賛辞を寄せている。ただし、これは例外中の例外である。
これは聴き手に「宝さがし」をさせる作品である。うかうかしていると魅力に気付かず聴き流してしまう。私もこの作品を最初に聴いたときは、第3楽章のアダージョの美しさに惹かれはしたものの、全体的に凹凸が少なく、あっさりした作品、という印象を持った。これが気の遠くなるような細心の配慮をもって書かれた、極めて論理的な作品であることに気付いたのは、だいぶ後のことである。完璧な構成であることを巧妙に隠した作品、と言い換えてもよい。名指揮者ジョージ・セルの言葉を借りれば、「シューマンの総譜は、ワーグナーやチャイコフスキーやR・シュトラウスの総譜のように、明瞭でひとりでにわかる、というタイプのものではない」。だからこそ、発見する楽しみがある。第1楽章の49小節に及ぶ序奏部が作品全体に大きな関わりを持っていること、一種の循環形式がとられていること、第1楽章から第3楽章までの流れを論理的に統括する意味で、終楽章が設定されていること等々......が次々と見えてきたとき、おそらくシンフォニー作曲家としてのシューマンの評価は、あなたの中で大きく変わってくるはずだ。
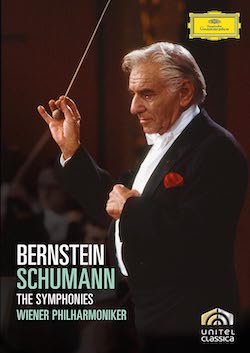 セルジウ・チェリビダッケが1994年にミュンヘン・フィルを振った際のライヴ録音は、説得力のあるテンポと絶妙なオーケストラ・コントロールによって、この作品の「宝さがし」をかなり容易にさせてくれる。聴いていると、曲全体の美しい輪郭が鮮やかに見えてくるはずだ。これほど緻密なアプローチをライヴでやってのけるのだから驚異というほかない。
セルジウ・チェリビダッケが1994年にミュンヘン・フィルを振った際のライヴ録音は、説得力のあるテンポと絶妙なオーケストラ・コントロールによって、この作品の「宝さがし」をかなり容易にさせてくれる。聴いていると、曲全体の美しい輪郭が鮮やかに見えてくるはずだ。これほど緻密なアプローチをライヴでやってのけるのだから驚異というほかない。

とりわけ交響曲第2番に関しては、支離滅裂、中途半端、失敗作、とこれまでさんざんに言われてきた。ほぼ同じ頃に書かれたピアノ協奏曲は傑作として名高いのに、交響曲になるとこうも扱いが悪くなる。なぜか。しばしば言われるようにオーケストレーションのバランス感覚がおかしく、交響曲だとその粗が目立つから? シューマンの管弦楽書法が個性的であることは確かだが、それを悪いと決めつけるのはおかしい。別にモーツァルトやベートーヴェンのように交響曲を作る必要はないのだ。
第2番は、1845年から翌年にかけて、精神病を悪化させていたシューマンがそこからどうにかして立ち直ろうともがきながら書いた作品である。ここで彼はベートーヴェン、シューベルトの影響から一歩脱した、新しいタイプの交響曲を提示しようとしたが、聴衆と評論家の理解を得ることはできなかった。
メンデルスゾーン、チャイコフスキーなど、早い段階からこの作品の魅力に気付いていた人もいないわけではない。とくにチャイコフスキーは、この作品に込められた楽想の美しさと構成の大胆さに最上級の賛辞を寄せている。ただし、これは例外中の例外である。
これは聴き手に「宝さがし」をさせる作品である。うかうかしていると魅力に気付かず聴き流してしまう。私もこの作品を最初に聴いたときは、第3楽章のアダージョの美しさに惹かれはしたものの、全体的に凹凸が少なく、あっさりした作品、という印象を持った。これが気の遠くなるような細心の配慮をもって書かれた、極めて論理的な作品であることに気付いたのは、だいぶ後のことである。完璧な構成であることを巧妙に隠した作品、と言い換えてもよい。名指揮者ジョージ・セルの言葉を借りれば、「シューマンの総譜は、ワーグナーやチャイコフスキーやR・シュトラウスの総譜のように、明瞭でひとりでにわかる、というタイプのものではない」。だからこそ、発見する楽しみがある。第1楽章の49小節に及ぶ序奏部が作品全体に大きな関わりを持っていること、一種の循環形式がとられていること、第1楽章から第3楽章までの流れを論理的に統括する意味で、終楽章が設定されていること等々......が次々と見えてきたとき、おそらくシンフォニー作曲家としてのシューマンの評価は、あなたの中で大きく変わってくるはずだ。
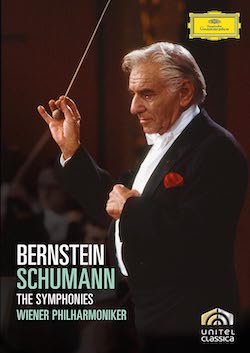
レナード・バーンスタインが1985年にウィーン・フィルを指揮した時の演奏(映像)は、万感の思いがこもっていて、音の響きの変化から様々な感情の綾が見えてくる。最後のリタルダントも素晴らしい。私の先輩は、この演奏を生で聴き、驚き、感動したと言っていたが、羨ましい限りだ。
マーラーが大幅に手を加えた(というか鬼のように添削した)編曲版もある。オリジナルと聴き比べてみると、音響的に逞しく豊かになり、スケール感が増しているのが分かる。こちらを好む人もいるかもしれない。が、ここに広がっているのはすでにシューマンの夢幻的な世界ではなく、あくまでもマーラーの世界である。(阿部十三)
ロベルト・シューマン
[1810.6.8-1856.7.29]
交響曲第2番ハ長調 作品61
【お薦めディスク】(掲載ジャケット)
ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
セルジウ・チェリビダッケ指揮
録音:1994年11月29日(ライヴ)
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
レナード・バーンスタイン指揮
録音:1985年(ライヴ)
[1810.6.8-1856.7.29]
交響曲第2番ハ長調 作品61
【お薦めディスク】(掲載ジャケット)
ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
セルジウ・チェリビダッケ指揮
録音:1994年11月29日(ライヴ)
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
レナード・バーンスタイン指揮
録音:1985年(ライヴ)
月別インデックス
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]