
ドヴォルザーク その人生と音楽
2011.04.11
涸れることを知らぬ旋律の泉
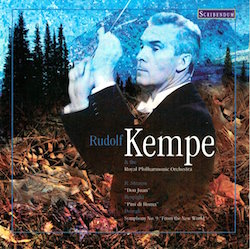 アントニン・ドヴォルザークは、1841年9月8日、豊かな自然に囲まれたモルダウ河ほとりのネラホゼヴェス村で生まれた。家は肉屋兼居酒屋。彼は幼い頃から楽器に親しみ、音楽家として生きることを望むが、父親に言われるまま肉屋職人としての資格を取得した。しかし最終的に父親が折れ、18歳のドヴォルザークはプラハの小さな楽団のヴィオラ奏者となり、しばらくして劇場オーケストラに移る。以後12年間、ほとんど誰にも知られずに作曲をしながら、劇場で日銭を稼ぐという生活が続いた。
アントニン・ドヴォルザークは、1841年9月8日、豊かな自然に囲まれたモルダウ河ほとりのネラホゼヴェス村で生まれた。家は肉屋兼居酒屋。彼は幼い頃から楽器に親しみ、音楽家として生きることを望むが、父親に言われるまま肉屋職人としての資格を取得した。しかし最終的に父親が折れ、18歳のドヴォルザークはプラハの小さな楽団のヴィオラ奏者となり、しばらくして劇場オーケストラに移る。以後12年間、ほとんど誰にも知られずに作曲をしながら、劇場で日銭を稼ぐという生活が続いた。
作曲家として初めて成功したのは32歳の時。賛歌「白山の後継者たち」が好評を以て迎えられたのである。同年に結婚。2年後にはオーストリア文化省に認められ、国家奨学金を受ける身分となる。その際、彼の才能を高く評価し、奨学金を受けられるよう計らったのはブラームスだった。
それからというもの、良妻の支えもあり(家庭生活では3人の子に先立たれたが、その後5人の子を授かった)、立て続けに傑作を発表。名声は国外に広まりドイツとイギリスでは熱狂的な人気を得る。1892年にはアメリカへ。ナショナル音楽院院長を務める。このアメリカ滞在中に書かれたのが交響曲第9番「新世界より」。チェロ協奏曲ロ短調、弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」もこの時期の収穫である。2年半後に帰国してからはオペラの作曲に専念し、『ルサルカ』を完成。しかしオペラ作曲家として大成したいという希望までは叶わず、1904年5月1日、脳卒中のため62歳で亡くなった。
ドヴォルザークの音楽の魅力は、なんといっても親しみやすく美しい旋律が次から次へと惜しげもなく飛び出してくるところにある。構成力よりも旋律発想力で惹きつけるタイプ。交響曲第8番、第9番「新世界より」、さらにチェロ協奏曲、スラヴ舞曲集、ピアノ五重奏曲イ長調第2番などは、まさにその好例。メロディー・メーカーの真骨頂を示す、涸れることを知らぬ泉のような作品だ。
ドヴォルザークの人生は恵まれていた。耳が聞こえなくなり精神病院で亡くなった同国人のスメタナに比べると大きな違いである。そんなことからドヴォルザークの音楽には重みや深みがないと言いだす人もある。しかし、それは言いがかりである。「お前は裕福だから駄目だ」と言って、その人の人生を否定するのと何も変わらない。
かくいう私はドヴォルザーク賛美者でも何でもない。どちらかと言えば苦手な作曲家の部類に属する。メロディーの一つ一つはたしかに魅力的で、親しみやすく、美しいのだが、彼はそれをこねくり回し、これ見よがしに繰り返す。「どうだ、いいメロディーだろ」と言わんばかりに。そのせいで、せっかくの親しみやすい旋律も、親しみを通り越して、厚かましく思えてくるのだ。コーダをむやみに引っ張ろうとするのも、音楽的必然というより過剰なサービス精神みたいで、「もう十分です」と言いたくなる。先に「涸れることを知らぬ泉」と書いたが、水浸しでは草木がだめになる。
言うまでもなく、繰り返しそのものが原因なわけではない。こういうことはベートーヴェンの「運命」を聴いても、シューベルトの「グレイト」を聴いても、ほとんど感じることはない。では、その違いは何なのか。メロディーそのものが有する個性やアクの性質によるものなのか。構成力の違いによるものなのか。作曲上のクセによるものなのか。あるいはもっと別の何かがあるのか。この問題はもっと時間をかけて考えてみる必要がありそうだ。
これはドヴォルザークに限らず全ての音楽にあてはまることだが、指揮者、演奏者の解釈次第で、聴き慣れていたはずの作品がずいぶん違った様相を示すことがある。フリッツ・ライナーの指揮でドヴォルザークを聴くのと、ほかの指揮者で聴くのとでは、まるで印象が異なる。作曲家について語る時は、自分自身がなじんでいるCDやレコードのことなども考慮に入れなければならない。
だから「ドヴォルザークは悪くない。演奏が悪いのだ」と言われたら、そうかもしれないとも思う。ただ、ドヴォルザークの交響曲や協奏曲は、CD、レコード、DVD、コンサートで相当数聴いてはいるが、作品の印象が覆るような画期的な解釈、新たな発見を提供する演奏はほとんどない。ハイドンやモーツァルトやベートーヴェン、あるいはブルックナーやマーラーよりも、聴き手を圧倒するような表現のディメンションが生まれにくい、ということは言えそうだ。
交響曲第7番と第8番の音楽はみずみずしく、旋律が有機的に絡み、つながり合って脈を打ち、自然に流れて起伏を描く。鼻につくわざとらしさを感じさせない。この2作は誰の指揮で聴いてもそれなりに楽しめる。しかしポピュラーな第9番「新世界」だとそうはいかず、指揮によって拒絶反応が起こる。私はフリッツ・ライナー、ジョージ・セルの解釈に衝撃を受け、イシュトヴァン・ケルテスとコンスタンティン・シルヴェストリの(第1楽章の)演奏にはまり、軍神マルスが乗り移ったようなアルトゥーロ・トスカニーニの指揮(ライヴ音源)に戦慄し、その後、ルドルフ・ケンペがロイヤル・フィルを振った演奏に感銘を受けた。ほかにも良い演奏はあるが、何度も聴きたいと思ったのはこの6人くらいだ。それぞれ個性は異なるが、くどさ、ぬるさ、甘ったるさがないところは共通している。
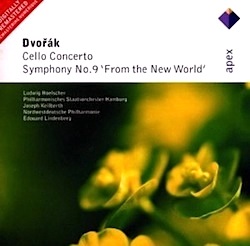 チェロ協奏曲は、ルートヴィヒ・ヘルシャーのチェロで聴きたい。指揮はヨーゼフ・カイルベルト。ジャクリーヌ・デュ・プレの響きが恋しくなった時は、私はセルジウ・チェリビダッケと協演したライヴを選ぶ。この作品は、ソリストが大事なのはもちろんだが、豊潤で美しいのに、ともすると押しつけがましくなるドヴォルザーク節を指揮者が巧みにコントロールできるかどうかが一番のポイントだ。その点で、カイルベルトもチェリビダッケも理想的なサポートをしている。
チェロ協奏曲は、ルートヴィヒ・ヘルシャーのチェロで聴きたい。指揮はヨーゼフ・カイルベルト。ジャクリーヌ・デュ・プレの響きが恋しくなった時は、私はセルジウ・チェリビダッケと協演したライヴを選ぶ。この作品は、ソリストが大事なのはもちろんだが、豊潤で美しいのに、ともすると押しつけがましくなるドヴォルザーク節を指揮者が巧みにコントロールできるかどうかが一番のポイントだ。その点で、カイルベルトもチェリビダッケも理想的なサポートをしている。
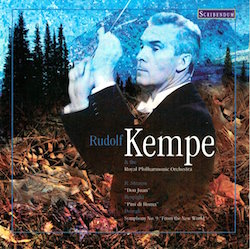
作曲家として初めて成功したのは32歳の時。賛歌「白山の後継者たち」が好評を以て迎えられたのである。同年に結婚。2年後にはオーストリア文化省に認められ、国家奨学金を受ける身分となる。その際、彼の才能を高く評価し、奨学金を受けられるよう計らったのはブラームスだった。
それからというもの、良妻の支えもあり(家庭生活では3人の子に先立たれたが、その後5人の子を授かった)、立て続けに傑作を発表。名声は国外に広まりドイツとイギリスでは熱狂的な人気を得る。1892年にはアメリカへ。ナショナル音楽院院長を務める。このアメリカ滞在中に書かれたのが交響曲第9番「新世界より」。チェロ協奏曲ロ短調、弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」もこの時期の収穫である。2年半後に帰国してからはオペラの作曲に専念し、『ルサルカ』を完成。しかしオペラ作曲家として大成したいという希望までは叶わず、1904年5月1日、脳卒中のため62歳で亡くなった。
ドヴォルザークの音楽の魅力は、なんといっても親しみやすく美しい旋律が次から次へと惜しげもなく飛び出してくるところにある。構成力よりも旋律発想力で惹きつけるタイプ。交響曲第8番、第9番「新世界より」、さらにチェロ協奏曲、スラヴ舞曲集、ピアノ五重奏曲イ長調第2番などは、まさにその好例。メロディー・メーカーの真骨頂を示す、涸れることを知らぬ泉のような作品だ。
ドヴォルザークの人生は恵まれていた。耳が聞こえなくなり精神病院で亡くなった同国人のスメタナに比べると大きな違いである。そんなことからドヴォルザークの音楽には重みや深みがないと言いだす人もある。しかし、それは言いがかりである。「お前は裕福だから駄目だ」と言って、その人の人生を否定するのと何も変わらない。
かくいう私はドヴォルザーク賛美者でも何でもない。どちらかと言えば苦手な作曲家の部類に属する。メロディーの一つ一つはたしかに魅力的で、親しみやすく、美しいのだが、彼はそれをこねくり回し、これ見よがしに繰り返す。「どうだ、いいメロディーだろ」と言わんばかりに。そのせいで、せっかくの親しみやすい旋律も、親しみを通り越して、厚かましく思えてくるのだ。コーダをむやみに引っ張ろうとするのも、音楽的必然というより過剰なサービス精神みたいで、「もう十分です」と言いたくなる。先に「涸れることを知らぬ泉」と書いたが、水浸しでは草木がだめになる。
言うまでもなく、繰り返しそのものが原因なわけではない。こういうことはベートーヴェンの「運命」を聴いても、シューベルトの「グレイト」を聴いても、ほとんど感じることはない。では、その違いは何なのか。メロディーそのものが有する個性やアクの性質によるものなのか。構成力の違いによるものなのか。作曲上のクセによるものなのか。あるいはもっと別の何かがあるのか。この問題はもっと時間をかけて考えてみる必要がありそうだ。
これはドヴォルザークに限らず全ての音楽にあてはまることだが、指揮者、演奏者の解釈次第で、聴き慣れていたはずの作品がずいぶん違った様相を示すことがある。フリッツ・ライナーの指揮でドヴォルザークを聴くのと、ほかの指揮者で聴くのとでは、まるで印象が異なる。作曲家について語る時は、自分自身がなじんでいるCDやレコードのことなども考慮に入れなければならない。
だから「ドヴォルザークは悪くない。演奏が悪いのだ」と言われたら、そうかもしれないとも思う。ただ、ドヴォルザークの交響曲や協奏曲は、CD、レコード、DVD、コンサートで相当数聴いてはいるが、作品の印象が覆るような画期的な解釈、新たな発見を提供する演奏はほとんどない。ハイドンやモーツァルトやベートーヴェン、あるいはブルックナーやマーラーよりも、聴き手を圧倒するような表現のディメンションが生まれにくい、ということは言えそうだ。
交響曲第7番と第8番の音楽はみずみずしく、旋律が有機的に絡み、つながり合って脈を打ち、自然に流れて起伏を描く。鼻につくわざとらしさを感じさせない。この2作は誰の指揮で聴いてもそれなりに楽しめる。しかしポピュラーな第9番「新世界」だとそうはいかず、指揮によって拒絶反応が起こる。私はフリッツ・ライナー、ジョージ・セルの解釈に衝撃を受け、イシュトヴァン・ケルテスとコンスタンティン・シルヴェストリの(第1楽章の)演奏にはまり、軍神マルスが乗り移ったようなアルトゥーロ・トスカニーニの指揮(ライヴ音源)に戦慄し、その後、ルドルフ・ケンペがロイヤル・フィルを振った演奏に感銘を受けた。ほかにも良い演奏はあるが、何度も聴きたいと思ったのはこの6人くらいだ。それぞれ個性は異なるが、くどさ、ぬるさ、甘ったるさがないところは共通している。
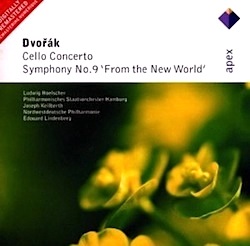
最後に、ドヴォルザークの作品中、別格の評価を与えられている「異色作」を紹介しておきたい。3人の子を失った悲しみを音楽に託した『スターバト・マーテル』である。これはチェコ音楽最初の宗教曲と言われるもの。ここにはサービス精神のかけらもない。大衆を意識せずに書かれたプライベートな作品であり、純然たる祈りの音楽で紡がれており、ほかの曲では見出せないような神韻縹渺たる世界へといとも簡単に聴き手を連れて行ってしまう。こういう作品に接すると、宗教音楽の領域ではまだまだ大作を遺せたのではないかという気もするのである。
(阿部十三)
アントニン・ドヴォルザーク
[1841.9.8-1904.5.1]
【ドヴォルザーク・お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
交響曲第9番ホ短調「新世界より」
ルドルフ・ケンペ指揮
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
チェロ協奏曲ロ短調
ルートヴィヒ・ヘルシャー(vc)
ハンブルク州立フィルハーモニー管弦楽団
ヨーゼフ・カイルベルト指揮
[1841.9.8-1904.5.1]
【ドヴォルザーク・お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
交響曲第9番ホ短調「新世界より」
ルドルフ・ケンペ指揮
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
チェロ協奏曲ロ短調
ルートヴィヒ・ヘルシャー(vc)
ハンブルク州立フィルハーモニー管弦楽団
ヨーゼフ・カイルベルト指揮
月別インデックス
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]