
モーツァルト 交響曲第40番 後篇
2011.04.23
ワルターからミンコフスキまで
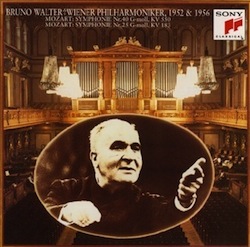 名盤と呼ばれている録音は少なくない。長年、最高の「40番」とされてきたブルーノ・ワルター/コロンビア響の組み合わせを筆頭に、オットー・クレンペラー/フィルハーモニア管、カール・ベーム/ウィーン・フィル、ヨーゼフ・カイルベルト/バイエルン放送交響楽団(ライヴ)などなど、どれも素晴らしい出来である。
名盤と呼ばれている録音は少なくない。長年、最高の「40番」とされてきたブルーノ・ワルター/コロンビア響の組み合わせを筆頭に、オットー・クレンペラー/フィルハーモニア管、カール・ベーム/ウィーン・フィル、ヨーゼフ・カイルベルト/バイエルン放送交響楽団(ライヴ)などなど、どれも素晴らしい出来である。
ワルターならコロンビア響よりウィーン・フィルを指揮したライヴ盤の方が上だと言う人も多い(ずっと1952年5月18日のライヴ音源とされてきたが、何年か前にオーストリア放送協会のデータにより1956年6月24日に訂正された)。この演奏は気迫がこもっていて、50年代のウィーン・フィルならではの甘美なポルタメントも味わえるし、低弦の音もインパクトがあり、一度聴いたら忘れられない感触を残す。ちなみにワルターとウィーン・フィルのライヴ音源はもう一種類あり(1952年5月17日)、こちらを推す人もいる。この辺は甲乙付けがたいし、あえて付ける意味もないだろう。
 「ワルターのモーツァルト」に拮抗するものとして挙げておきたいのは、亡くなる直前の1970年5月に来日したジョージ・セル/クリーヴランド管のライヴ。「セル=完璧主義=冷たい」と評する人もいるが、このライヴは熱い。完璧な演奏でありながら、そこをさらに突きぬけて高く駆け出そうとしている。第1楽章はとくに凄絶で、鳥肌が立つほど美しく、哀しい。
「ワルターのモーツァルト」に拮抗するものとして挙げておきたいのは、亡くなる直前の1970年5月に来日したジョージ・セル/クリーヴランド管のライヴ。「セル=完璧主義=冷たい」と評する人もいるが、このライヴは熱い。完璧な演奏でありながら、そこをさらに突きぬけて高く駆け出そうとしている。第1楽章はとくに凄絶で、鳥肌が立つほど美しく、哀しい。
1948年12月に録音されたヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーン・フィルの演奏は、〈モルト・アレグロ〉の指示に従っている点で傾聴に値する。まるで地煙りをたてながら疾駆しているような激越な第1楽章。それでいて品格を失うことがない。
残念ながら1990年代以降の録音にはめぼしい「40番」が見当たらない。期待して聴いても、充実感がなく、空疎な印象しか残らない。あるいはピリオド奏法で作為的にやりすぎ、聴くに堪えない壊れた玩具のような音楽にしてしまった人もいる。それらの演奏に接するたびに、現代においてモーツァルトをありのままに美しく演奏することがそこまで困難なことなのだろうか、と考えてしまう。
比較的新しいところでは、モーツァルティアンを唸らせたジャンルイジ・ジェルメッティ/シュトゥットガルト放送交響楽団の演奏が良い。とはいえ録音は1989年、もう20年以上前である。
現代のモーツァルト演奏で最も精彩を放ち、最も説得力があるのは、マルク・ミンコフスキ/ルーブル宮音楽隊の録音かもしれない。私の中でのミンコフスキのイメージは、末梢的な刺激を追いかけているパリの悪童。だが、この「40番」はスコアの読みの深さを感じさせる名演奏だ。外向的なようで内向的。軽快なように見せながら、裏には哀しみが隠されている。これみよがしの哀しみではない。その繊細な表現力には舌を巻く。難しいアゴーギクも悉く成功している。これは過去の名盤と比べても遜色はないと思う。
【関連サイト】
モーツァルト 交響曲第40番 前篇
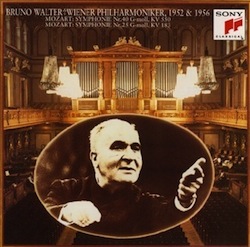
ワルターならコロンビア響よりウィーン・フィルを指揮したライヴ盤の方が上だと言う人も多い(ずっと1952年5月18日のライヴ音源とされてきたが、何年か前にオーストリア放送協会のデータにより1956年6月24日に訂正された)。この演奏は気迫がこもっていて、50年代のウィーン・フィルならではの甘美なポルタメントも味わえるし、低弦の音もインパクトがあり、一度聴いたら忘れられない感触を残す。ちなみにワルターとウィーン・フィルのライヴ音源はもう一種類あり(1952年5月17日)、こちらを推す人もいる。この辺は甲乙付けがたいし、あえて付ける意味もないだろう。

1948年12月に録音されたヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーン・フィルの演奏は、〈モルト・アレグロ〉の指示に従っている点で傾聴に値する。まるで地煙りをたてながら疾駆しているような激越な第1楽章。それでいて品格を失うことがない。
残念ながら1990年代以降の録音にはめぼしい「40番」が見当たらない。期待して聴いても、充実感がなく、空疎な印象しか残らない。あるいはピリオド奏法で作為的にやりすぎ、聴くに堪えない壊れた玩具のような音楽にしてしまった人もいる。それらの演奏に接するたびに、現代においてモーツァルトをありのままに美しく演奏することがそこまで困難なことなのだろうか、と考えてしまう。
比較的新しいところでは、モーツァルティアンを唸らせたジャンルイジ・ジェルメッティ/シュトゥットガルト放送交響楽団の演奏が良い。とはいえ録音は1989年、もう20年以上前である。
現代のモーツァルト演奏で最も精彩を放ち、最も説得力があるのは、マルク・ミンコフスキ/ルーブル宮音楽隊の録音かもしれない。私の中でのミンコフスキのイメージは、末梢的な刺激を追いかけているパリの悪童。だが、この「40番」はスコアの読みの深さを感じさせる名演奏だ。外向的なようで内向的。軽快なように見せながら、裏には哀しみが隠されている。これみよがしの哀しみではない。その繊細な表現力には舌を巻く。難しいアゴーギクも悉く成功している。これは過去の名盤と比べても遜色はないと思う。
(阿部十三)
【関連サイト】
モーツァルト 交響曲第40番 前篇
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
[1756.1.27-1791.12.5]
交響曲第40番ト短調 K.550
【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ブルーノ・ワルター指揮
録音:1956年6月24日(ライヴ)
クリーヴランド管弦楽団
ジョージ・セル指揮
録音:1970年5月22日(ライヴ)
[1756.1.27-1791.12.5]
交響曲第40番ト短調 K.550
【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ブルーノ・ワルター指揮
録音:1956年6月24日(ライヴ)
クリーヴランド管弦楽団
ジョージ・セル指揮
録音:1970年5月22日(ライヴ)
月別インデックス
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]