
ラヴェル 『ボレロ』
2011.05.28
音色の変奏曲
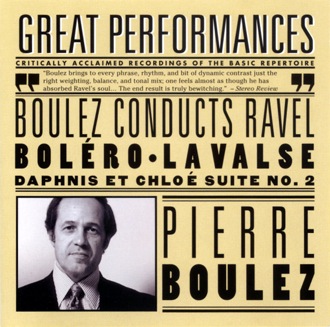 モーリス・ラヴェルの『ボレロ』は、極めてユニークな手法で書かれた傑作として音楽史上特異な地位を占めている。管弦楽曲の醍醐味をここまで大胆かつわかりやすく明示した作品はほかにない。
モーリス・ラヴェルの『ボレロ』は、極めてユニークな手法で書かれた傑作として音楽史上特異な地位を占めている。管弦楽曲の醍醐味をここまで大胆かつわかりやすく明示した作品はほかにない。
曲の構成はいたってシンプル。一定のリズムが刻まれる中、ひたすら2つのメロディーが繰り返される。ただそれだけ。展開も何もない。変化するのは「音色」のみ。様々な楽器が代わり番こにメロディーを奏でてゆく。途中からそれらの楽器が2つ、3つ......と組み合わさり、音量が少しずつ大きくなる。そして最後はオーケストラによる力強い全合奏でしめくくられる。要するに、作品全体がひとつの巨大なクレッシェンドになっているのだ。よくもまあこんなことを思いついたものである。しかし、それでもちゃんと「聴かせる」作品として成立しているのだから凄い。
作曲されたのは1928年。ロシア人の名舞踏家イダ・ルビンスタインから、スペイン風のバレエ作品を依頼されたのが始まり。当初はアルベニスの『イベリア』を編曲する予定だったが、権利上の問題でかなわず、ラヴェルがゼロから創作することになった。
その夏、サン=ジャン=ド=リューズで、ラヴェルは海水浴姿でピアノに向かい、1本指で「スペイン=アラビア風」の主題を友人に弾いてみせた。その時こう言ったという。「この主題には何か執拗に訴えてくるものがあると思わないか? 僕はこいつを全く展開させず、何度も繰り返しながら、管弦楽の規模を徐々に大きくしてゆこうと思うんだ」
初演は同年11月22日、パリのオペラ座で行われた。その際、観客の1人が「ラヴェルの頭はどうかしてしまったんだわ!」と叫び、ラヴェルが「あの客こそこの曲の真の理解者だ」と漏らしたというエピソードが残されている。たしかに何の予備知識もなければ、「頭がどうかしてしまった」人の作品と思うのが普通なのかもしれない。
バレエの舞台はスペインの薄暗い酒場。若い女性がボレロを踊り始め、徐々にまわりの人々が彼女の踊りにつり込まれてゆき、最後は全員で熱狂的に踊りだす、という内容である。翌年1月には演奏会形式で披露され、以来、オーケストラのレパートリーとして無くてはならないものになっている。ちなみに、ボレロというのは18世紀末に生まれたスペインの舞踏の一種。3拍子で、カスタネットを伴うが、ラヴェルの『ボレロ』ではカスタネットは削除されている。おそらくカスタネットが入ると、その音ばかりが目立ってしまうためと思われる。
オーケストレーションの魔術師と言われたラヴェルだけに、楽器の使い分け、配合の仕方がとにかくうまい。「タン・タタタ タン・タタタ タン・タン|タン・タタタ タン・タタタ タタタタタタ」という小太鼓のリズムが延々と繰り返される中(計169回)、少し飽きてきたところで楽器の組み合わせが変わり、空気がさっと新しくなる。メロディーとリズムは変わらないのに、それを奏でる楽器によってこうも印象が違ってくるものか、と驚かされる瞬間である。「音色の変奏曲」と呼ばれる所以だ。テナーサックスやトロンボーンを要所に入れ、ジャズ的な風味を加えているのもポイントだろう。なお、ラヴェルは演奏時間を「17分」と指定している。
 超有名曲なだけに録音の種類は数多くあるが、ブーレーズ&ニューヨーク・フィルによる1974年の演奏は、緻密なアンサンブルによって劇的なクライマックスを築き上げてゆくプロセスをじっくり堪能させてくれる。ただ、スリルと迫力を求める人にはシャルル・ミュンシュ&パリ管の録音が一番。しかも演奏時間は17分である。
超有名曲なだけに録音の種類は数多くあるが、ブーレーズ&ニューヨーク・フィルによる1974年の演奏は、緻密なアンサンブルによって劇的なクライマックスを築き上げてゆくプロセスをじっくり堪能させてくれる。ただ、スリルと迫力を求める人にはシャルル・ミュンシュ&パリ管の録音が一番。しかも演奏時間は17分である。
『ボレロ』からジョルジュ・ドンを連想する人も多いだろう。一世を風靡した彼のダンスは、クロード・ルルーシュ監督の映画『愛と哀しみのボレロ』で観ることができる。20世紀後半を代表する振付師、モーリス・ベジャールによる振付は今観ても全く色褪せていない。
【関連サイト】
モーリス・ラヴェル『ボレロ』(CD)
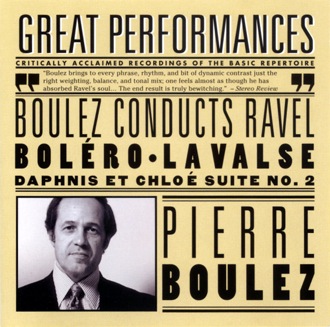
曲の構成はいたってシンプル。一定のリズムが刻まれる中、ひたすら2つのメロディーが繰り返される。ただそれだけ。展開も何もない。変化するのは「音色」のみ。様々な楽器が代わり番こにメロディーを奏でてゆく。途中からそれらの楽器が2つ、3つ......と組み合わさり、音量が少しずつ大きくなる。そして最後はオーケストラによる力強い全合奏でしめくくられる。要するに、作品全体がひとつの巨大なクレッシェンドになっているのだ。よくもまあこんなことを思いついたものである。しかし、それでもちゃんと「聴かせる」作品として成立しているのだから凄い。
作曲されたのは1928年。ロシア人の名舞踏家イダ・ルビンスタインから、スペイン風のバレエ作品を依頼されたのが始まり。当初はアルベニスの『イベリア』を編曲する予定だったが、権利上の問題でかなわず、ラヴェルがゼロから創作することになった。
その夏、サン=ジャン=ド=リューズで、ラヴェルは海水浴姿でピアノに向かい、1本指で「スペイン=アラビア風」の主題を友人に弾いてみせた。その時こう言ったという。「この主題には何か執拗に訴えてくるものがあると思わないか? 僕はこいつを全く展開させず、何度も繰り返しながら、管弦楽の規模を徐々に大きくしてゆこうと思うんだ」
初演は同年11月22日、パリのオペラ座で行われた。その際、観客の1人が「ラヴェルの頭はどうかしてしまったんだわ!」と叫び、ラヴェルが「あの客こそこの曲の真の理解者だ」と漏らしたというエピソードが残されている。たしかに何の予備知識もなければ、「頭がどうかしてしまった」人の作品と思うのが普通なのかもしれない。
バレエの舞台はスペインの薄暗い酒場。若い女性がボレロを踊り始め、徐々にまわりの人々が彼女の踊りにつり込まれてゆき、最後は全員で熱狂的に踊りだす、という内容である。翌年1月には演奏会形式で披露され、以来、オーケストラのレパートリーとして無くてはならないものになっている。ちなみに、ボレロというのは18世紀末に生まれたスペインの舞踏の一種。3拍子で、カスタネットを伴うが、ラヴェルの『ボレロ』ではカスタネットは削除されている。おそらくカスタネットが入ると、その音ばかりが目立ってしまうためと思われる。
オーケストレーションの魔術師と言われたラヴェルだけに、楽器の使い分け、配合の仕方がとにかくうまい。「タン・タタタ タン・タタタ タン・タン|タン・タタタ タン・タタタ タタタタタタ」という小太鼓のリズムが延々と繰り返される中(計169回)、少し飽きてきたところで楽器の組み合わせが変わり、空気がさっと新しくなる。メロディーとリズムは変わらないのに、それを奏でる楽器によってこうも印象が違ってくるものか、と驚かされる瞬間である。「音色の変奏曲」と呼ばれる所以だ。テナーサックスやトロンボーンを要所に入れ、ジャズ的な風味を加えているのもポイントだろう。なお、ラヴェルは演奏時間を「17分」と指定している。

『ボレロ』からジョルジュ・ドンを連想する人も多いだろう。一世を風靡した彼のダンスは、クロード・ルルーシュ監督の映画『愛と哀しみのボレロ』で観ることができる。20世紀後半を代表する振付師、モーリス・ベジャールによる振付は今観ても全く色褪せていない。
番外編として紹介しておきたいのが『パトリス・ルコントのボレロ』。冒頭からひたすら同じリズムを刻み続ける小太鼓奏者のやりきれない表情を撮り続けた短編映画である。ただそれだけの映画なのだが地味に笑える。
(阿部十三)
【関連サイト】
モーリス・ラヴェル『ボレロ』(CD)
モーリス・ラヴェル
[1875.3.7-1937.12.28]
『ボレロ』
【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
ニューヨーク・フィルハーモニック
ピエール・ブーレーズ指揮
録音:1974年
パリ管弦楽団
シャルル・ミュンシュ指揮
録音:1967年
[1875.3.7-1937.12.28]
『ボレロ』
【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
ニューヨーク・フィルハーモニック
ピエール・ブーレーズ指揮
録音:1974年
パリ管弦楽団
シャルル・ミュンシュ指揮
録音:1967年
月別インデックス
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]