
マーラー 交響曲第7番「夜の歌」
2013.02.12
「悲劇的」を超えて
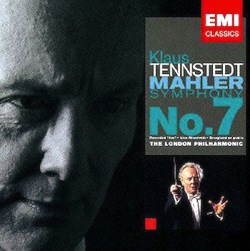 一番最初に聴いたマーラーの交響曲は第7番だった、という人はどれくらいいるのだろう。おそらくそこまで多くないのではないか。私の場合、誰にいわれたわけでもなく、何のガイドブックを読んだわけでもなく、結果的に第7番を最後に聴いた。そして、大袈裟にいえば、これまでほかの交響曲に親しんできたのは、第7番の世界に入るための準備であったかのような気持ちになったものである。それくらい第7番を聴く前と聴いた後、好きになる前と好きになった後では、マーラーに対する見方が変わる。いってみれば分水嶺的な作品なのだ。
一番最初に聴いたマーラーの交響曲は第7番だった、という人はどれくらいいるのだろう。おそらくそこまで多くないのではないか。私の場合、誰にいわれたわけでもなく、何のガイドブックを読んだわけでもなく、結果的に第7番を最後に聴いた。そして、大袈裟にいえば、これまでほかの交響曲に親しんできたのは、第7番の世界に入るための準備であったかのような気持ちになったものである。それくらい第7番を聴く前と聴いた後、好きになる前と好きになった後では、マーラーに対する見方が変わる。いってみれば分水嶺的な作品なのだ。
交響曲第7番ホ短調「夜の歌」は、1904年夏から1905年夏にかけて作曲された。当時マーラーは40代半ば。次女アンナ・ユスティーネが生まれて間もない頃である。
1904年夏といえば、第6番「悲劇的」を完成させたタイミングでもあるが、そのまま休むことなく、第7番の第2楽章と第4楽章が書かれた。そして、1905年に残りの3楽章が書かれたのである。
ちなみに、「夜の歌」は第2楽章と第4楽章に付けられたタイトルであり、交響曲全体にはマーラーは何の名称も与えていない。「夜の歌」という言葉のイメージでこの作品を掴もうとしても、掴みきれないだろう。
「ホ短調」とされている点についても、異論を唱える人は少なくない。第1楽章はロ短調で始まり、主要部でホ短調に中心を移し、最後はホ長調で終わる。第2楽章はハ長調ではじまり、第3楽章はニ短調ではじまる。第4楽章はヘ長調、第5楽章はハ長調。以上の調性を考えると、ホ短調ではなく、ロ短調もしくはハ長調とすべきである、というのだ。中には、「最も悲劇的なハ長調の交響曲」と呼ぶ人もいる。
構成は、スケルツォの第3楽章を中央に据えて、その両脇に「夜の歌」の第2楽章、第4楽章を配置。さらに両端にソナタ形式の第1楽章、ロンド形式風の第5楽章を置いている。つまりABCBAのアーチ型になっているのである。
終楽章の型破りな性格については、すでに多くのことが語られている。性格が突然変異したようなこの華やかなフィナーレは、なぜ書かれなければならなかったのか。テオドール・W・アドルノは、終楽章から「華麗な現象と中身の薄い内実との間の無力な不均衡」を感じる、と書いた上で、次のように表現している。
「この楽章は劇場的なものである。これほど青く見えるのは、あまりに手近なところに設けられたお祭り広場の書き割りの空だけである」
すでに第6番「悲劇的」で凄絶なフィナーレを書いていたマーラーは、ベートーヴェン以来の「苦難を乗り越えて栄光へ」という肯定性を素直に昇華することが出来ず、とってつけたハッピーエンドを加えることで、「伝統の形式」を騒々しいタブローにしてしまった。パロディ化した、といってもいい。ーー私が見る限り、こういう視点に立脚した論が多いようである。
私自身は、この終楽章を中身が薄いものとみなすことには共感出来ない。
第6番で容赦のないカタストロフを描いたマーラーは(同時期に「亡き子をしのぶ歌」の第2曲、第5曲も書いている)、それ以上「悲劇」に嵌るのを避けるようにして、次作を書きはじめた。その心理が、第7番をハッピーエンドにさせたのではないか。確かに「書き割り」のように無理矢理な明るさかもしれない(ワーグナーの『ニュルンベルクのマイスタージンガー』まで組み込まれている)。しかし、マーラーには「悲劇的」を押し黙らせるレベルの明るさがぜひとも必要だったのである。だから彼は、「これ(第7番)は私の最良の作品で、概して明朗な性格のものです」(エミール・グートマン宛の手紙)と書いた。彼自身、本気で「明朗な性格」と信じていたかどうかはともかく、そういう作品として世に出したかったのである。
大編成でありながら、各楽器を細かく、しかもたっぷり活躍させているのも特徴である。そして、精巧な響きのバランスの上で、一癖も二癖もある旋律が顔を出しては引っ込んでいく。なんとなく大勢の悪戯好きな音の精がうごめいているように聞こえる。テノールホルン、タムタム、マンドリン、ギターなどの楽器を採り入れている点もユニークである。「悲劇的」で使われていたカウベルも登場する。
私は先に「分水嶺的な作品」と書いたが、ここには胸にしみる旋律で編まれたアダージョや、誰もが感動的できるようなフィナーレがあるわけではない。「マーラーは好きだけど、第7番はとっつきにくい」と感じる人がいても不思議はないと思う。マーラーがこの作品について遺したメッセージも少ない。ただし、ポピュラリティやメッセージ性が作品の価値を決めるわけではない。
第7番は、マーラーの異常な才能やバランス感覚を純粋に楽しむには最高の作品である。楽譜を見ながら(眺めながらでもいい)聴けば、その楽しみは倍加するだろう。
数ある録音の中で、私が最も感銘を受けたのはクラウス・テンシュテットが指揮したものだ。1993年のライヴで、もう呆れるほどの大熱演である。生で聴いた人にとっては、一生忘れられない出来事になったに違いない。遠慮がちなところは一切ない。一つ一つの音符の切れ目を思いきり押し広げて、そこにあるニュアンスを全力で引っ張り上げようとしているような、異様なテンションが伝わってくる。
初めて聴く人には、エリアフ・インバルがフランクフルト放送響を指揮したものや、マイケル・ティルソン・トーマスがロンドン響を指揮したものを紹介するのが穏当かもしれない。ただ、テンシュテット盤を引っ込めて、インバルやティルソン・トーマスから聴いてくださいというのも、私にはちょっとケチな話に思えるので、まずはテンシュテットの凄絶な演奏を聴いて面食らい、それから色々な演奏を聴くことをお薦めしたい。
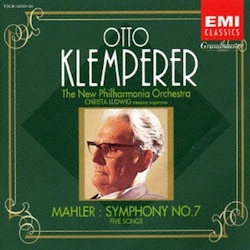 1968年に録音されたオットー・クレンペラー指揮による演奏は、いつ終わるのか、果てしなく思えるほどのテンポの遅さで有名。第7番の中にある音という音、そして構造上の秘密が白日の下にさらされている。私はこれを聴くと、音の精たちが動きを止められ、標本にされているのを見ているかのような気分にさせられる。歴史的怪演といわれているが、炯眼の賜物である。
1968年に録音されたオットー・クレンペラー指揮による演奏は、いつ終わるのか、果てしなく思えるほどのテンポの遅さで有名。第7番の中にある音という音、そして構造上の秘密が白日の下にさらされている。私はこれを聴くと、音の精たちが動きを止められ、標本にされているのを見ているかのような気分にさせられる。歴史的怪演といわれているが、炯眼の賜物である。
バルビローリ&ハレ管、バーンスタイン&ニューヨーク・フィル、ケーゲル&都響、ブーレーズ&クリーヴランド管の演奏を聴いても、第7番の魅力は伝わるだろう。バルビローリが指揮した第2楽章と第4楽章などは、作品の核をゆっくり射抜いていくような独特の美感があり、聴く度に唸らされる。個人的にはミヒャエル・ギーレン盤も好きで、よく聴いている。アーティキュレーションの精度の高さは、かつて「レントゲン写真のような」といわれたブーレーズ級である。冒頭の弦からして、ほかの人たちの演奏とはまるで違う。ただ、オーケストラの力量のせいか、ギーレンの意図が完全に表現されているとはいえない箇所も多い。オケ次第でもっと凄い演奏になったのではないかと思う。
【関連サイト】
マーラー:交響曲第7番ホ短調「夜の歌」
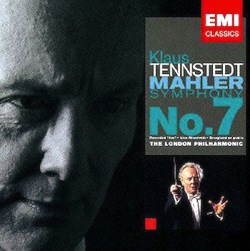
交響曲第7番ホ短調「夜の歌」は、1904年夏から1905年夏にかけて作曲された。当時マーラーは40代半ば。次女アンナ・ユスティーネが生まれて間もない頃である。
1904年夏といえば、第6番「悲劇的」を完成させたタイミングでもあるが、そのまま休むことなく、第7番の第2楽章と第4楽章が書かれた。そして、1905年に残りの3楽章が書かれたのである。
ちなみに、「夜の歌」は第2楽章と第4楽章に付けられたタイトルであり、交響曲全体にはマーラーは何の名称も与えていない。「夜の歌」という言葉のイメージでこの作品を掴もうとしても、掴みきれないだろう。
「ホ短調」とされている点についても、異論を唱える人は少なくない。第1楽章はロ短調で始まり、主要部でホ短調に中心を移し、最後はホ長調で終わる。第2楽章はハ長調ではじまり、第3楽章はニ短調ではじまる。第4楽章はヘ長調、第5楽章はハ長調。以上の調性を考えると、ホ短調ではなく、ロ短調もしくはハ長調とすべきである、というのだ。中には、「最も悲劇的なハ長調の交響曲」と呼ぶ人もいる。
構成は、スケルツォの第3楽章を中央に据えて、その両脇に「夜の歌」の第2楽章、第4楽章を配置。さらに両端にソナタ形式の第1楽章、ロンド形式風の第5楽章を置いている。つまりABCBAのアーチ型になっているのである。
終楽章の型破りな性格については、すでに多くのことが語られている。性格が突然変異したようなこの華やかなフィナーレは、なぜ書かれなければならなかったのか。テオドール・W・アドルノは、終楽章から「華麗な現象と中身の薄い内実との間の無力な不均衡」を感じる、と書いた上で、次のように表現している。
「この楽章は劇場的なものである。これほど青く見えるのは、あまりに手近なところに設けられたお祭り広場の書き割りの空だけである」
すでに第6番「悲劇的」で凄絶なフィナーレを書いていたマーラーは、ベートーヴェン以来の「苦難を乗り越えて栄光へ」という肯定性を素直に昇華することが出来ず、とってつけたハッピーエンドを加えることで、「伝統の形式」を騒々しいタブローにしてしまった。パロディ化した、といってもいい。ーー私が見る限り、こういう視点に立脚した論が多いようである。
私自身は、この終楽章を中身が薄いものとみなすことには共感出来ない。
第6番で容赦のないカタストロフを描いたマーラーは(同時期に「亡き子をしのぶ歌」の第2曲、第5曲も書いている)、それ以上「悲劇」に嵌るのを避けるようにして、次作を書きはじめた。その心理が、第7番をハッピーエンドにさせたのではないか。確かに「書き割り」のように無理矢理な明るさかもしれない(ワーグナーの『ニュルンベルクのマイスタージンガー』まで組み込まれている)。しかし、マーラーには「悲劇的」を押し黙らせるレベルの明るさがぜひとも必要だったのである。だから彼は、「これ(第7番)は私の最良の作品で、概して明朗な性格のものです」(エミール・グートマン宛の手紙)と書いた。彼自身、本気で「明朗な性格」と信じていたかどうかはともかく、そういう作品として世に出したかったのである。
大編成でありながら、各楽器を細かく、しかもたっぷり活躍させているのも特徴である。そして、精巧な響きのバランスの上で、一癖も二癖もある旋律が顔を出しては引っ込んでいく。なんとなく大勢の悪戯好きな音の精がうごめいているように聞こえる。テノールホルン、タムタム、マンドリン、ギターなどの楽器を採り入れている点もユニークである。「悲劇的」で使われていたカウベルも登場する。
私は先に「分水嶺的な作品」と書いたが、ここには胸にしみる旋律で編まれたアダージョや、誰もが感動的できるようなフィナーレがあるわけではない。「マーラーは好きだけど、第7番はとっつきにくい」と感じる人がいても不思議はないと思う。マーラーがこの作品について遺したメッセージも少ない。ただし、ポピュラリティやメッセージ性が作品の価値を決めるわけではない。
第7番は、マーラーの異常な才能やバランス感覚を純粋に楽しむには最高の作品である。楽譜を見ながら(眺めながらでもいい)聴けば、その楽しみは倍加するだろう。
数ある録音の中で、私が最も感銘を受けたのはクラウス・テンシュテットが指揮したものだ。1993年のライヴで、もう呆れるほどの大熱演である。生で聴いた人にとっては、一生忘れられない出来事になったに違いない。遠慮がちなところは一切ない。一つ一つの音符の切れ目を思いきり押し広げて、そこにあるニュアンスを全力で引っ張り上げようとしているような、異様なテンションが伝わってくる。
初めて聴く人には、エリアフ・インバルがフランクフルト放送響を指揮したものや、マイケル・ティルソン・トーマスがロンドン響を指揮したものを紹介するのが穏当かもしれない。ただ、テンシュテット盤を引っ込めて、インバルやティルソン・トーマスから聴いてくださいというのも、私にはちょっとケチな話に思えるので、まずはテンシュテットの凄絶な演奏を聴いて面食らい、それから色々な演奏を聴くことをお薦めしたい。
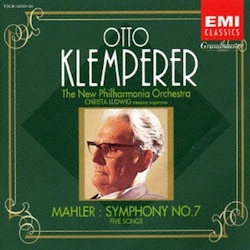
バルビローリ&ハレ管、バーンスタイン&ニューヨーク・フィル、ケーゲル&都響、ブーレーズ&クリーヴランド管の演奏を聴いても、第7番の魅力は伝わるだろう。バルビローリが指揮した第2楽章と第4楽章などは、作品の核をゆっくり射抜いていくような独特の美感があり、聴く度に唸らされる。個人的にはミヒャエル・ギーレン盤も好きで、よく聴いている。アーティキュレーションの精度の高さは、かつて「レントゲン写真のような」といわれたブーレーズ級である。冒頭の弦からして、ほかの人たちの演奏とはまるで違う。ただ、オーケストラの力量のせいか、ギーレンの意図が完全に表現されているとはいえない箇所も多い。オケ次第でもっと凄い演奏になったのではないかと思う。
(阿部十三)
【関連サイト】
マーラー:交響曲第7番ホ短調「夜の歌」
グスタフ・マーラー
[1860.7.7-1911.5.18]
交響曲第7番ホ短調「夜の歌」
【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
クラウス・テンシュテット指揮
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1993年(ライヴ)
オットー・クレンペラー指揮
ニュー・フィルハーモニア管弦楽団
録音:1968年
[1860.7.7-1911.5.18]
交響曲第7番ホ短調「夜の歌」
【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
クラウス・テンシュテット指揮
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1993年(ライヴ)
オットー・クレンペラー指揮
ニュー・フィルハーモニア管弦楽団
録音:1968年
月別インデックス
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]