
ベートーヴェン 『ディアベリの主題による33の変奏曲』
2013.05.01
シューベルトやムソルグスキーにもつながる宇宙
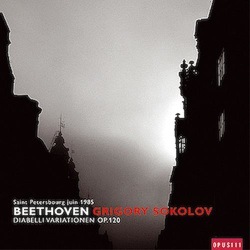 『ディアベリの主題による33の変奏曲』、略して『ディアベリ変奏曲』は、1823年に出版されたピアノ作品で、J.S.バッハの『ゴールドベルク変奏曲』と共に、変奏曲史上の最高傑作といわれている。原題は〈33 Veränderungen über einen Walzer von A.Diabelli〉。意図的に〈Veränderungen〉という言葉が遣われているのは、「変質」や「変容」のニュアンスを持たせたかったからだろう。ちなみに、この〈Veränderungen〉を用いているのは『ゴールドベルク変奏曲』も同じである。
『ディアベリの主題による33の変奏曲』、略して『ディアベリ変奏曲』は、1823年に出版されたピアノ作品で、J.S.バッハの『ゴールドベルク変奏曲』と共に、変奏曲史上の最高傑作といわれている。原題は〈33 Veränderungen über einen Walzer von A.Diabelli〉。意図的に〈Veränderungen〉という言葉が遣われているのは、「変質」や「変容」のニュアンスを持たせたかったからだろう。ちなみに、この〈Veränderungen〉を用いているのは『ゴールドベルク変奏曲』も同じである。
ディアベリとは、ウィーンの出版商アントン・ディアベリのこと。彼が自作のワルツ主題を50人の作曲家に与えて、競作させようとしたのが事の発端である。その作曲家の中にはシューベルトやリストの名前もあった。
最初、ベートーヴェンは与えられた主題を取るに足らないものとして申し出を断ったが、意を翻して作曲を開始。『ミサ・ソレムニス』の作曲と並行して、1822年から本格的に着手し、ディアベリが想像もしなかったような大規模なスケールの作品を書きあげて提出した。なお、献呈の相手はディアベリではなく、「不滅の恋人」の候補とされているアントーニエ・ブレンターノである。
ベートーヴェンの作品中、『ディアベリ変奏曲』は「途方もない難曲」という意味合いで評されることが多い。そのせいで、私は長年警戒心のようなものを抱いていた。軽い気持ちで聴いてはいけない、と。そして聴くたびに、得るものもなく、疲弊していた(正直なところ、ベートーヴェンの発想に感嘆させられたのは、モーツァルトのフレーズを借用した第22変奏くらいだ)。
変な枷がとれたのは、グリゴリー・ソコロフの演奏を聴いてからである。これは「途方もない難曲」ではない。ベートーヴェンの自由な創造力と33の音楽的多重人格の饗宴である。しかも、シューベルトにつながる世界があり、ムソルグスキーにつながる世界がある。放埒に見える変奏にも秩序があり、それぞれが有機的に呼応している。ーーソコロフ体験以後、私は『ディアベリ』に夢中になり、聴いて疲れるどころか、音楽的愉悦すら感じるようになった。殊更深刻さを強調する人は、「ベートーヴェンのピアノ作品の到達点が深刻でないわけがない」という先入観にとらわれすぎていると思う。
『ディアベリ』の世界は多彩なイメージに溢れている。そのイメージを独自の方法で言語化したのが、『時間割』や『心変わり』で知られるフランスの作家ミシェル・ビュトールの『ディアベリ変奏曲との対話』。この著作で、ビュトールはスコアを綿密に読み解きながら、一方で詩的なイメージを膨らませ、天文学との関わりにまで話を広げている。「湧き出る泡」(第5変奏)、「光の幻想曲」(第19変奏)、「亡霊のワルツ」(第29変奏)など、各変奏に名前を付けているのも面白い。『ゴールドベルク変奏曲』との共通項についても軽く言及している。アドニラムの話まで出てくる。シューベルト、シューマン、ショパン、ムソルグスキー、ドビュッシーまで包括しかねないこの宇宙のような作品を語るのに、あらゆる手段を講じた、という趣がある。
ベートーヴェンは若い頃、即興演奏を得意としていた。『ディアベリ』を作曲する30年ほど前、リヒノフスキー侯爵の紹介で、ピアニストとしてサロンに出入りするようになった野心家の青年は、そこで長大な即興演奏を聴かせ、時には即興競演に駆り出され、ライバルたちを負かしていたという。彼の即興演奏が具体的にどんなものであったかは分からないが、『ディアベリ変奏曲』を聴くと、この作品を書かせる感性の萌芽は当時からあったのではないか、と想像したくなる。
最初の主題から第1変奏への「変容」ぶりで、すでに度肝を抜かれる人は多いと思うが、その後も驚きのレベルが減退することはない。「こんな変奏、ありなのか。まあ、ありかもしれない」と受け入れていくうちに、どんどん深みに入っていく。白眉は第29変奏から第31変奏。第31変奏になると、もはやシューベルトでも聴いているような気分になる。これをビュトールは「悲愴幻想曲」と名付けたが、感情を「悲」に限定する必要はないだろう。もっと親密な感情の静かな広がりがここにはある。
ピアニストのアプローチ次第で、作品のイメージがあやふやになったり、素っ頓狂なものになったりしてしまう『ディアベリ変奏曲』。これを退屈な演奏で聴くと、無駄な時間を過ごすことになり、作品自体を敬遠したくなる。
私自身は、既述したようにソコロフのライヴ音源を通じて『ディアベリ』にのめり込んだ。彼のピアノはメリハリがきいていて、しかもヴィヴィッドになりすぎず、ゆるやかな変奏では上品な詩情が漂っている。つくづく、隅々まで神経の行き届いた名演奏だ。
ソコロフ盤の研ぎすまされた空気感に疲れると、もう少し演奏の自由度が高いジュリアス・カッチェンの録音を聴きたくなる。快刀のようなピアニズムで『ディアベリ変奏曲』の複雑さを感じさせないフリードリヒ・グルダの録音も素晴らしいが、ややまとまりが良すぎ、スマートすぎるようにも聞こえる。
 ルドルフ・ゼルキン、ピーター・ゼルキン、スヴャトスラフ・リヒテルの録音も有名。とくにリヒテル盤は大きな生命力がうごめいているような感触を伝える大演奏である。そして、この作品の演奏によって世界的名声を博した鬼才、アナトール・ウゴルスキ。造型感と自由度と夢幻が奇跡のように噛み合わさったピアニズムは、一度聴いただけでは消化しきれないかもしれないが、何度も聴いているうちに癖になるだろう。第8変奏、第14変奏、第18変奏、第31変奏などは、ベートーヴェンの規格外の感性に、これまた規格外の感性を重ねて生まれたエレガントなファンタジーである。比較的新しい世代では、ピョートル・アンデルジェフスキの録音が非常にユニーク(ブリュノ・モンサンジョン監督による映像もある)。彼の演奏は、『ディアベリ』がとらえどころのない難曲ではなく、一本の線を持ったドラマであることを噛んで含めるように説いている。この作品は、アプローチの可能性が無限にありそうなので、未来の天才たちの演奏にも期待したい。
ルドルフ・ゼルキン、ピーター・ゼルキン、スヴャトスラフ・リヒテルの録音も有名。とくにリヒテル盤は大きな生命力がうごめいているような感触を伝える大演奏である。そして、この作品の演奏によって世界的名声を博した鬼才、アナトール・ウゴルスキ。造型感と自由度と夢幻が奇跡のように噛み合わさったピアニズムは、一度聴いただけでは消化しきれないかもしれないが、何度も聴いているうちに癖になるだろう。第8変奏、第14変奏、第18変奏、第31変奏などは、ベートーヴェンの規格外の感性に、これまた規格外の感性を重ねて生まれたエレガントなファンタジーである。比較的新しい世代では、ピョートル・アンデルジェフスキの録音が非常にユニーク(ブリュノ・モンサンジョン監督による映像もある)。彼の演奏は、『ディアベリ』がとらえどころのない難曲ではなく、一本の線を持ったドラマであることを噛んで含めるように説いている。この作品は、アプローチの可能性が無限にありそうなので、未来の天才たちの演奏にも期待したい。
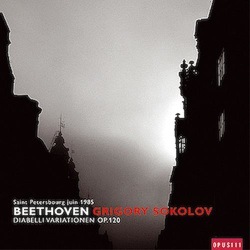
ディアベリとは、ウィーンの出版商アントン・ディアベリのこと。彼が自作のワルツ主題を50人の作曲家に与えて、競作させようとしたのが事の発端である。その作曲家の中にはシューベルトやリストの名前もあった。
最初、ベートーヴェンは与えられた主題を取るに足らないものとして申し出を断ったが、意を翻して作曲を開始。『ミサ・ソレムニス』の作曲と並行して、1822年から本格的に着手し、ディアベリが想像もしなかったような大規模なスケールの作品を書きあげて提出した。なお、献呈の相手はディアベリではなく、「不滅の恋人」の候補とされているアントーニエ・ブレンターノである。
ベートーヴェンの作品中、『ディアベリ変奏曲』は「途方もない難曲」という意味合いで評されることが多い。そのせいで、私は長年警戒心のようなものを抱いていた。軽い気持ちで聴いてはいけない、と。そして聴くたびに、得るものもなく、疲弊していた(正直なところ、ベートーヴェンの発想に感嘆させられたのは、モーツァルトのフレーズを借用した第22変奏くらいだ)。
変な枷がとれたのは、グリゴリー・ソコロフの演奏を聴いてからである。これは「途方もない難曲」ではない。ベートーヴェンの自由な創造力と33の音楽的多重人格の饗宴である。しかも、シューベルトにつながる世界があり、ムソルグスキーにつながる世界がある。放埒に見える変奏にも秩序があり、それぞれが有機的に呼応している。ーーソコロフ体験以後、私は『ディアベリ』に夢中になり、聴いて疲れるどころか、音楽的愉悦すら感じるようになった。殊更深刻さを強調する人は、「ベートーヴェンのピアノ作品の到達点が深刻でないわけがない」という先入観にとらわれすぎていると思う。
『ディアベリ』の世界は多彩なイメージに溢れている。そのイメージを独自の方法で言語化したのが、『時間割』や『心変わり』で知られるフランスの作家ミシェル・ビュトールの『ディアベリ変奏曲との対話』。この著作で、ビュトールはスコアを綿密に読み解きながら、一方で詩的なイメージを膨らませ、天文学との関わりにまで話を広げている。「湧き出る泡」(第5変奏)、「光の幻想曲」(第19変奏)、「亡霊のワルツ」(第29変奏)など、各変奏に名前を付けているのも面白い。『ゴールドベルク変奏曲』との共通項についても軽く言及している。アドニラムの話まで出てくる。シューベルト、シューマン、ショパン、ムソルグスキー、ドビュッシーまで包括しかねないこの宇宙のような作品を語るのに、あらゆる手段を講じた、という趣がある。
ベートーヴェンは若い頃、即興演奏を得意としていた。『ディアベリ』を作曲する30年ほど前、リヒノフスキー侯爵の紹介で、ピアニストとしてサロンに出入りするようになった野心家の青年は、そこで長大な即興演奏を聴かせ、時には即興競演に駆り出され、ライバルたちを負かしていたという。彼の即興演奏が具体的にどんなものであったかは分からないが、『ディアベリ変奏曲』を聴くと、この作品を書かせる感性の萌芽は当時からあったのではないか、と想像したくなる。
最初の主題から第1変奏への「変容」ぶりで、すでに度肝を抜かれる人は多いと思うが、その後も驚きのレベルが減退することはない。「こんな変奏、ありなのか。まあ、ありかもしれない」と受け入れていくうちに、どんどん深みに入っていく。白眉は第29変奏から第31変奏。第31変奏になると、もはやシューベルトでも聴いているような気分になる。これをビュトールは「悲愴幻想曲」と名付けたが、感情を「悲」に限定する必要はないだろう。もっと親密な感情の静かな広がりがここにはある。
ピアニストのアプローチ次第で、作品のイメージがあやふやになったり、素っ頓狂なものになったりしてしまう『ディアベリ変奏曲』。これを退屈な演奏で聴くと、無駄な時間を過ごすことになり、作品自体を敬遠したくなる。
私自身は、既述したようにソコロフのライヴ音源を通じて『ディアベリ』にのめり込んだ。彼のピアノはメリハリがきいていて、しかもヴィヴィッドになりすぎず、ゆるやかな変奏では上品な詩情が漂っている。つくづく、隅々まで神経の行き届いた名演奏だ。
ソコロフ盤の研ぎすまされた空気感に疲れると、もう少し演奏の自由度が高いジュリアス・カッチェンの録音を聴きたくなる。快刀のようなピアニズムで『ディアベリ変奏曲』の複雑さを感じさせないフリードリヒ・グルダの録音も素晴らしいが、ややまとまりが良すぎ、スマートすぎるようにも聞こえる。

(阿部十三)
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
[1770.12.17-1827.3.26]
ディアベリの主題による33の変奏曲
【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
グリゴリー・ソコロフ(p)
録音:1985年6月
アナトール・ウゴルスキ(p)
録音:1991年5月
[1770.12.17-1827.3.26]
ディアベリの主題による33の変奏曲
【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
グリゴリー・ソコロフ(p)
録音:1985年6月
アナトール・ウゴルスキ(p)
録音:1991年5月
月別インデックス
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]