
ラヴェル 弦楽四重奏曲
2014.08.25
古の旋法が描く20世紀のメランコリー
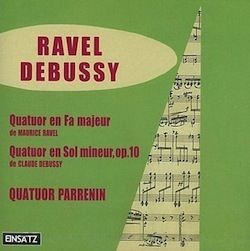 モーリス・ラヴェルの弦楽四重奏曲は、1902年から翌年にかけて作曲された。初演が行われたのは1904年3月5日。反響は上々で、多くの人がまだ20代の若きラヴェルの才能を称えた。何しろあの辛辣なドビュッシーが「音楽の神と私の名において、君の四重奏曲の一音符たりとも変更してはなりません」と忠告したというから驚くほかない。しかし、ラヴェル自身は仕上がりに満足しておらず、後年改訂を施した。作品は「わが親愛なる師、ガブリエル・フォーレ」に献呈されている。
モーリス・ラヴェルの弦楽四重奏曲は、1902年から翌年にかけて作曲された。初演が行われたのは1904年3月5日。反響は上々で、多くの人がまだ20代の若きラヴェルの才能を称えた。何しろあの辛辣なドビュッシーが「音楽の神と私の名において、君の四重奏曲の一音符たりとも変更してはなりません」と忠告したというから驚くほかない。しかし、ラヴェル自身は仕上がりに満足しておらず、後年改訂を施した。作品は「わが親愛なる師、ガブリエル・フォーレ」に献呈されている。
作曲にあたり、ラヴェルはフランクの循環形式をとりいれているが、その扱いはより巧妙であり、複雑でもある。第1楽章の第1主題がフリギア旋法に近く、第2主題がヒポフリギア旋法に基づいていることからもうかがえるように、機能和声の概念からはみ出し、異なる教会旋法の対話により、エレガンスとメランコリーをたたえたモダンな世界を醸成させる。おそらくこれはドビュッシーの弦楽四重奏曲を意識したものだろう。ちなみに、ラヴェル自身は「音楽の構成意志にこたえるために書いた」と述べている。
この作品は一貫して繊細に演奏されなければならない。強弱緩急を過剰にやりたがる現代演奏家が弾くと、その潔癖なヴィジョンが仇となり、彫りが深くなるどころか、表現のコントラストを楽しむだけの薄っぺらいものになる。そうではないカルテットも存在するが、それにしても底の浅い演奏が多い。奏者にとって最も危険なのは第3楽章と第4楽章で、「トレ・ラン(非常にゆるやかに)」と指示された第3楽章の48小節、フォルテで入るチェロを仰々しく響かせたり、激しく躍動する第4楽章をやたらスポーティーに弾き切ったりしてしまうと、それだけであざとさが前面に出てきて、エレガントな味わいがなくなり、奏者の取るに足らない解釈自慢、腕自慢を鑑賞しているような気分にさせられる。
 古くから名演奏とされているのはカペー弦楽四重奏団による1928年の録音で、冒頭からポルタメントを多用し、ひとつひとつの旋律が朧にとけていくような美しさを感じさせる。録音年代のわりに音質もそこまで悪くないので、今なおこれを支持する人がいても不思議はない。ただ、私にはこのポルタメントがやや鬱陶しく感じられることがあり、もう少し弦楽器が自然に息づいているような演奏を聴きたくなる。そんな欲求を満たすのが、ジャック・パレナン率いるパレナン四重奏団である。彼らが1950年代に録音した素朴で高貴な演奏は、まだこの作品の全容を見通せずにいた私に、みずみずしい風景を見せてくれた。
古くから名演奏とされているのはカペー弦楽四重奏団による1928年の録音で、冒頭からポルタメントを多用し、ひとつひとつの旋律が朧にとけていくような美しさを感じさせる。録音年代のわりに音質もそこまで悪くないので、今なおこれを支持する人がいても不思議はない。ただ、私にはこのポルタメントがやや鬱陶しく感じられることがあり、もう少し弦楽器が自然に息づいているような演奏を聴きたくなる。そんな欲求を満たすのが、ジャック・パレナン率いるパレナン四重奏団である。彼らが1950年代に録音した素朴で高貴な演奏は、まだこの作品の全容を見通せずにいた私に、みずみずしい風景を見せてくれた。
カルヴェ弦楽四重奏団による1937年の録音にも、レーヴェングート弦楽四重奏団による1953年の録音にも、繊細さと抒情味があり、良い意味で個性的だが、パレナンを超えるものとはいえない。1960年代以降のものでは、下手な作為性のないカルミナ四重奏団とオルランド四重奏団の演奏に好感を抱いたくらいで、大半の録音からは余計な肩の力ないし表現の過剰さを感じた。まだまだ良い演奏はあると思うので、根気よく探し続けたいものである。
【関連サイト】
MAURICE RAVEL(CD)
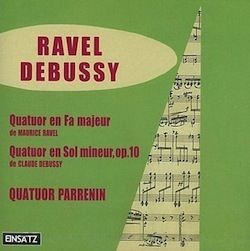
作曲にあたり、ラヴェルはフランクの循環形式をとりいれているが、その扱いはより巧妙であり、複雑でもある。第1楽章の第1主題がフリギア旋法に近く、第2主題がヒポフリギア旋法に基づいていることからもうかがえるように、機能和声の概念からはみ出し、異なる教会旋法の対話により、エレガンスとメランコリーをたたえたモダンな世界を醸成させる。おそらくこれはドビュッシーの弦楽四重奏曲を意識したものだろう。ちなみに、ラヴェル自身は「音楽の構成意志にこたえるために書いた」と述べている。
この作品は一貫して繊細に演奏されなければならない。強弱緩急を過剰にやりたがる現代演奏家が弾くと、その潔癖なヴィジョンが仇となり、彫りが深くなるどころか、表現のコントラストを楽しむだけの薄っぺらいものになる。そうではないカルテットも存在するが、それにしても底の浅い演奏が多い。奏者にとって最も危険なのは第3楽章と第4楽章で、「トレ・ラン(非常にゆるやかに)」と指示された第3楽章の48小節、フォルテで入るチェロを仰々しく響かせたり、激しく躍動する第4楽章をやたらスポーティーに弾き切ったりしてしまうと、それだけであざとさが前面に出てきて、エレガントな味わいがなくなり、奏者の取るに足らない解釈自慢、腕自慢を鑑賞しているような気分にさせられる。

カルヴェ弦楽四重奏団による1937年の録音にも、レーヴェングート弦楽四重奏団による1953年の録音にも、繊細さと抒情味があり、良い意味で個性的だが、パレナンを超えるものとはいえない。1960年代以降のものでは、下手な作為性のないカルミナ四重奏団とオルランド四重奏団の演奏に好感を抱いたくらいで、大半の録音からは余計な肩の力ないし表現の過剰さを感じた。まだまだ良い演奏はあると思うので、根気よく探し続けたいものである。
(阿部十三)
【関連サイト】
MAURICE RAVEL(CD)
モーリス・ラヴェル
[1875.3.7-1937.12.28]
弦楽四重奏曲
【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
パレナン弦楽四重奏団
録音:1950年代
カルミナ弦楽四重奏団
収録:1992年2月
[1875.3.7-1937.12.28]
弦楽四重奏曲
【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
パレナン弦楽四重奏団
録音:1950年代
カルミナ弦楽四重奏団
収録:1992年2月
月別インデックス
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]