
マーラー 交響曲第9番
2016.11.27
「9番」にふさわしいもの
 「作曲家は交響曲第9番を書いた後、生き延びることができない」という迷信を恐れるあまり、マーラーはもともと「第9番」として作曲していた『大地の歌』に番号を与えなかった。そして本来ならば10番目にあたる次の交響曲を「第9番」とすることで、生命の危険を回避することができると考えた。いわゆる「第九のジンクス」である。
「作曲家は交響曲第9番を書いた後、生き延びることができない」という迷信を恐れるあまり、マーラーはもともと「第9番」として作曲していた『大地の歌』に番号を与えなかった。そして本来ならば10番目にあたる次の交響曲を「第9番」とすることで、生命の危険を回避することができると考えた。いわゆる「第九のジンクス」である。
この逸話に私はずっと疑問を抱いていた。そこまで迷信を信じていたわりには、「第9番」の番号を与えた作品の内容が、多くの人に生死を想起させる重さと深さを持っているからだ。もし本気でジンクスへの対策を練っていたのであれば、「第9番」を小規模の軽い内容にして、すぐにでも第10番を書いていたのではないか。あるいは、新たな交響曲を完成させた後に、『大地の歌』を「第9番」にしてしまい、新作に「第10番」の名称を与えてもよかったのではないか。
そのようにしなかったのは、おそらく「交響曲第9番」は偉大な音楽であるべきだという考えを持っていたからだろう。それゆえ適当にやりすごすことができず、1909年夏頃から1910年春にかけて大急ぎで書きながらも、深い内容を持たせることになったのではないかと推測する。つまるところ、彼はこの作品を「交響曲第9番」と呼ぶにふさわしい内容を持つものとして世に出したかったのである。
第1楽章はアンダンテ・コモド。ハープ、ホルン、低弦などに導かれて夢うつつの世界が静かにあらわれる。溜息のようなリズムは、巨大な呼吸器がふくらんだりへこんだりする様子を模しているようにも感じられる。交響曲第3番や『大地の歌』にみられる音型も登場し、回想と告別、憧憬、葛藤が入り混じった印象がある。私がここから連想するのは、「彼が愛したすべてのものへの、そして世界への告別」(ウィレム・メンゲルベルク)ではなく、かつてマーラーが交響曲第2番「復活」の第1楽章に葬送行進曲を配置したときの心境である。この第9番で言えば、過去の自分の葬送といったところか。
第2楽章は一種のスケルツォ。マーラーらしい機知とパロディ精神をうかがわせるが、次第に緊張感を帯びてめまぐるしくなり、最後は静かに終わる。第3楽章はロンド・ブルレスケ。諧謔味を含みながらも、その要素が鬼気迫る響きの中で燃え尽きてゆく感がある。ただ勢い一辺倒ではなく、交響曲第3番の第1楽章を一部引用したり、次の終楽章を予告する雰囲気になったりと、構成は一筋縄ではいかない。
終楽章はアダージョ。冒頭から弦楽器の美しい旋律が波打ち、憧憬と叫びと緊張の音楽が続く。そして122小節でクライマックスに達した後、徐々に静かになり、やがて「亡き子をしのぶ歌」の第4曲が引用されて全曲を閉じる。先にもふれたようにこの作品には交響曲第3番の旋律が引用されており、また、その第6楽章(元の標題は「愛が私に語ること」)と同じように「アダージョ」が最後に置かれていることから、第9番を「死が私に語ること」と標題的にとらえる向きもある。
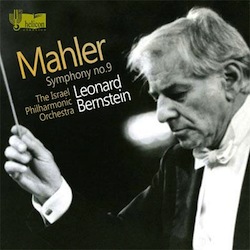 1909年夏頃のマーラーは穏やかな状態にあったようで、「この上ない幸福な状態」と手紙にも書いている。だからといって死をテーマにするわけがないとは言えないが、その死は自分自身の人生の終焉ではなく、ニューヨーク・フィルの首席指揮者になることも決まり、新たな音楽人生を歩み始めた自分が過去に向けて告げた惜別と決別を示すのではないか。もっと言えば、葛藤を経て過去を葬った人間(その葬送が第1楽章で行われる)が復活するための、祈りと浄化の音楽ではないか。浄化されるものの中には、1907年に失った娘アンナ・マリアの面影もあっただろう。その意識が「亡き子をしのぶ歌」の引用につながっている。
1909年夏頃のマーラーは穏やかな状態にあったようで、「この上ない幸福な状態」と手紙にも書いている。だからといって死をテーマにするわけがないとは言えないが、その死は自分自身の人生の終焉ではなく、ニューヨーク・フィルの首席指揮者になることも決まり、新たな音楽人生を歩み始めた自分が過去に向けて告げた惜別と決別を示すのではないか。もっと言えば、葛藤を経て過去を葬った人間(その葬送が第1楽章で行われる)が復活するための、祈りと浄化の音楽ではないか。浄化されるものの中には、1907年に失った娘アンナ・マリアの面影もあっただろう。その意識が「亡き子をしのぶ歌」の引用につながっている。
ちょうど同じように静かに終わるチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」のように、人生最後の完成作となったために、第9番は死のイメージに覆われてしまったが、もしこれを以て死を迎える覚悟であったのなら、交響曲第10番の第1楽章が書かれることはなかったはずだ。
マーラーの死後、1912年6月26日に行われた初演で指揮を務めたのは弟子のブルーノ・ワルター。彼とウィーン・フィルの組み合わせによる演奏(1938年1月ライヴ録音)は今もよく聴かれているようだ。実際、音質は悪くないし、演奏自体も手探りのものではない。戦前の時点でマーラーの作品がここまで正しく演奏されていたのか、というのが正直な感想である。
ジョン・バルビローリ指揮、ベルリン・フィルの演奏(1964年1月録音)も高い評価を得た名盤。客演で指揮したバルビローリに共鳴した楽団員が熱望し、実現した録音である。結構あっさりしたところもあるが、終楽章は素晴らしい。ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮、ロンドン響の演奏(1966年4月ライヴ録音)は作品への没入の度合いが尋常ではない。ミスは少なくないが、手に汗握る緊張感が漂い、スケールも壮大だ。変に甘口にならず、ヒステリックに喚き散らさないところも良い。
オットー・クレンペラー指揮、ニュー・フィルハーモニア管の演奏(1967年録音)は巨大建造物の構造をつまびらかにするようなアプローチで、取り乱したところがない。カルロ・マリア・ジュリーニ指揮、シカゴ響の演奏(1976年録音)は第1楽章冒頭から低弦の響かせ方が素晴らしくて鳥肌モノだが、録音状態が良くない。レナード・バーンスタインが指揮した第9番はどれも耳を圧する迫力があり、濃厚で凄絶な世界だが、祈りの音楽のように響くイスラエル・フィルとの組み合わせ(1985年8月ライヴ録音)が、私には合っている。
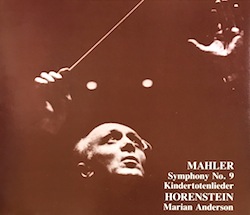 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルの演奏(1982年9月ライヴ録音)は熱量に満ちた美演で、至芸の記録としてファンに尊ばれている。ガリー・ベルティーニ指揮、ケルン放送響の演奏(1991年2月ライヴ録音)はさらにその上を行くような究極の美演で、アンサンブル、テンポ、デュナーミク全ての点で最高のバランスを感じさせる。それも優等生的な演奏という意味ではない。「一念岩をも通す」ではないが、美に殉じて深みに達する、その徹底ぶりに打たれる。サイモン・ラトル指揮、ベルリン・フィルの演奏(2007年10月ライヴ録音)は総譜の細部まで熟知した匠の技で魅了する。見通しの良さで唸らせるだけでなく、演奏の精密さと自在な表現力により聴き手を感動させるものを持っている。
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルの演奏(1982年9月ライヴ録音)は熱量に満ちた美演で、至芸の記録としてファンに尊ばれている。ガリー・ベルティーニ指揮、ケルン放送響の演奏(1991年2月ライヴ録音)はさらにその上を行くような究極の美演で、アンサンブル、テンポ、デュナーミク全ての点で最高のバランスを感じさせる。それも優等生的な演奏という意味ではない。「一念岩をも通す」ではないが、美に殉じて深みに達する、その徹底ぶりに打たれる。サイモン・ラトル指揮、ベルリン・フィルの演奏(2007年10月ライヴ録音)は総譜の細部まで熟知した匠の技で魅了する。見通しの良さで唸らせるだけでなく、演奏の精密さと自在な表現力により聴き手を感動させるものを持っている。
【関連サイト】
Gustav Mahler

この逸話に私はずっと疑問を抱いていた。そこまで迷信を信じていたわりには、「第9番」の番号を与えた作品の内容が、多くの人に生死を想起させる重さと深さを持っているからだ。もし本気でジンクスへの対策を練っていたのであれば、「第9番」を小規模の軽い内容にして、すぐにでも第10番を書いていたのではないか。あるいは、新たな交響曲を完成させた後に、『大地の歌』を「第9番」にしてしまい、新作に「第10番」の名称を与えてもよかったのではないか。
そのようにしなかったのは、おそらく「交響曲第9番」は偉大な音楽であるべきだという考えを持っていたからだろう。それゆえ適当にやりすごすことができず、1909年夏頃から1910年春にかけて大急ぎで書きながらも、深い内容を持たせることになったのではないかと推測する。つまるところ、彼はこの作品を「交響曲第9番」と呼ぶにふさわしい内容を持つものとして世に出したかったのである。
第1楽章はアンダンテ・コモド。ハープ、ホルン、低弦などに導かれて夢うつつの世界が静かにあらわれる。溜息のようなリズムは、巨大な呼吸器がふくらんだりへこんだりする様子を模しているようにも感じられる。交響曲第3番や『大地の歌』にみられる音型も登場し、回想と告別、憧憬、葛藤が入り混じった印象がある。私がここから連想するのは、「彼が愛したすべてのものへの、そして世界への告別」(ウィレム・メンゲルベルク)ではなく、かつてマーラーが交響曲第2番「復活」の第1楽章に葬送行進曲を配置したときの心境である。この第9番で言えば、過去の自分の葬送といったところか。
第2楽章は一種のスケルツォ。マーラーらしい機知とパロディ精神をうかがわせるが、次第に緊張感を帯びてめまぐるしくなり、最後は静かに終わる。第3楽章はロンド・ブルレスケ。諧謔味を含みながらも、その要素が鬼気迫る響きの中で燃え尽きてゆく感がある。ただ勢い一辺倒ではなく、交響曲第3番の第1楽章を一部引用したり、次の終楽章を予告する雰囲気になったりと、構成は一筋縄ではいかない。
終楽章はアダージョ。冒頭から弦楽器の美しい旋律が波打ち、憧憬と叫びと緊張の音楽が続く。そして122小節でクライマックスに達した後、徐々に静かになり、やがて「亡き子をしのぶ歌」の第4曲が引用されて全曲を閉じる。先にもふれたようにこの作品には交響曲第3番の旋律が引用されており、また、その第6楽章(元の標題は「愛が私に語ること」)と同じように「アダージョ」が最後に置かれていることから、第9番を「死が私に語ること」と標題的にとらえる向きもある。
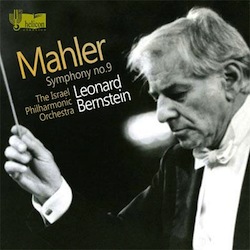
ちょうど同じように静かに終わるチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」のように、人生最後の完成作となったために、第9番は死のイメージに覆われてしまったが、もしこれを以て死を迎える覚悟であったのなら、交響曲第10番の第1楽章が書かれることはなかったはずだ。
マーラーの死後、1912年6月26日に行われた初演で指揮を務めたのは弟子のブルーノ・ワルター。彼とウィーン・フィルの組み合わせによる演奏(1938年1月ライヴ録音)は今もよく聴かれているようだ。実際、音質は悪くないし、演奏自体も手探りのものではない。戦前の時点でマーラーの作品がここまで正しく演奏されていたのか、というのが正直な感想である。
ジョン・バルビローリ指揮、ベルリン・フィルの演奏(1964年1月録音)も高い評価を得た名盤。客演で指揮したバルビローリに共鳴した楽団員が熱望し、実現した録音である。結構あっさりしたところもあるが、終楽章は素晴らしい。ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮、ロンドン響の演奏(1966年4月ライヴ録音)は作品への没入の度合いが尋常ではない。ミスは少なくないが、手に汗握る緊張感が漂い、スケールも壮大だ。変に甘口にならず、ヒステリックに喚き散らさないところも良い。
オットー・クレンペラー指揮、ニュー・フィルハーモニア管の演奏(1967年録音)は巨大建造物の構造をつまびらかにするようなアプローチで、取り乱したところがない。カルロ・マリア・ジュリーニ指揮、シカゴ響の演奏(1976年録音)は第1楽章冒頭から低弦の響かせ方が素晴らしくて鳥肌モノだが、録音状態が良くない。レナード・バーンスタインが指揮した第9番はどれも耳を圧する迫力があり、濃厚で凄絶な世界だが、祈りの音楽のように響くイスラエル・フィルとの組み合わせ(1985年8月ライヴ録音)が、私には合っている。
(阿部十三)
【関連サイト】
Gustav Mahler
グスタフ・マーラー
[1860.7.7-1911.5.18]
交響曲第9番 ニ長調
【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
ガリー・ベルティーニ指揮
ケルン放送交響楽団
録音:1991年2月(ライヴ)
レナード・バーンスタイン指揮
イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1985年8月25日(ライヴ)
ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮
ロンドン交響楽団
録音:1966年4月(ライヴ)
[1860.7.7-1911.5.18]
交響曲第9番 ニ長調
【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
ガリー・ベルティーニ指揮
ケルン放送交響楽団
録音:1991年2月(ライヴ)
レナード・バーンスタイン指揮
イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1985年8月25日(ライヴ)
ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮
ロンドン交響楽団
録音:1966年4月(ライヴ)
月別インデックス
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]