
ラヴェル ピアノ協奏曲
2021.09.03
協奏曲は軽快に、華麗に
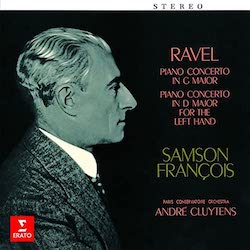 モーリス・ラヴェルのピアノ協奏曲は1929年から1931年にかけて作曲され、1932年1月14日、マルグリット・ロンの独奏により初演された。奇しくもラヴェルは1929年に「左手のためのピアノ協奏曲」を書くように依頼され、そちらの作曲も行っていた(完成したのは「左手」の方が早い)。これまでピアノ協奏曲を完成させたことのない作曲家が、晩年になって、同時期に2作を手掛けていたのである。
モーリス・ラヴェルのピアノ協奏曲は1929年から1931年にかけて作曲され、1932年1月14日、マルグリット・ロンの独奏により初演された。奇しくもラヴェルは1929年に「左手のためのピアノ協奏曲」を書くように依頼され、そちらの作曲も行っていた(完成したのは「左手」の方が早い)。これまでピアノ協奏曲を完成させたことのない作曲家が、晩年になって、同時期に2作を手掛けていたのである。
ラヴェルは自身のピアノ協奏曲について、「モーツァルトとサン=サーンスの協奏曲の精神に則って作曲した」と語っている。さらに、「協奏曲の音楽というものは、軽快かつ華麗であるべきで、深刻さを志向したりドラマティックな効果を狙ったりすべきではない」として、大げさな表現を排除した。
この作品は、当時としては珍しくジャズの要素を取り入れていることでも注目された。フランス音楽らしい色彩の豊かさ、古典主義の清潔感と品の良さ、ジャズのユーモアや物憂さという取り合わせは、どこからどう見てもアンバランスだが、ラヴェルはそれらを巧みに配合し、調和させることに成功している。
作曲にはかなり苦労したらしい。よく聴いてみると、音の重ね方が驚くほど精巧で、楽器の響きの細かいところまで計算されている。ただでさえ手のかかる曲なのに、当時(1931年)、56歳だったラヴェルは徐々に悪化する失語症や記憶障害に悩まされていた。作曲に費やされたエネルギーは大変な量だったろう。
第1楽章はアレグラメンテ。ソナタ形式。鞭の打音から始まり、ピアノによる分散和音の上で、ピッコロが跳ねるようにして第1主題を奏でる。ピアノで弾かれる第2主題はジャズの風味で、トロンボーンのグリッサンドなどがその味わいを深める。再現部で、ハープとホルンの独奏が幻想的な雰囲気を強め、ピアノのカデンツァ(トリルと分散和音)を経て、少しずつ高揚していく構成が素晴らしい。
第2楽章はアダージョ・アッサイ。3部形式。まずピアノが過去を回想するような優しい旋律(主題)を奏でる。楽章全体は108小節あるが、そのうち33小節をピアノのみで進めた後、ようやく管弦楽が柔和な表情で登場。やがて調性は不安定になり、内省的な美しさが浮き上がってくる。聴き所はコーラングレとピアノとの掛け合いで、ここは極めて繊細な弱音が求められるだけに演奏が難しそうだ。
第3楽章はプレスト。アクセントのきいた冒頭の楽節はユーモラスでパレードの雰囲気を思わせる。ピアノはトッカータ風で、5度音程の分散和音を奏で、平行和音による主題を提示する。その後、楽想とリズムを微妙に変化させながら駆け回り、最後はラヴェル好みのクレッシェンドで盛り上がり、冒頭の楽節を奏でてすっきりと終わる。
最初に聴いたときは、奇妙な音楽を耳に投げ込まれたような気分に陥った。鞭、ピアノ、ピッコロで始まる冒頭からすでに珍奇である。ハープ、高音域のホルン、コーラングレを目立たせるところも独特だ。しかし、そこは管弦楽の魔術師と呼ばれたラヴェルのこと、不思議な味わいだけでは終わらせず、巧みに音を重ねることにより、精巧で美しい音楽へと昇華させている。とりわけ第1楽章再現部、第2楽章がもたらす束の間の静謐と幻想は、聴き手を陶酔させずにはおかない。
これ以降、ラヴェルが完成させることが出来たのは『ドゥルシネア姫に心を寄せるドン・キホーテ』のみである。しかし後年、病が悪化して楽譜が書けない状態になっても、「生命とは本当に美しいものだ。だから、こんな風になっても生きている方がいいのだ」と語っていたという。
代表的な録音とされているのは、アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリが独奏を務めたもの(1957年録音)。テンポの取り方が難しい箇所でもピアノの音の粒が綺麗に整っていて、溜息が出るほど美しい。しかもキレが良い。ただ、オーケストラには雑なところがあり、もっと丁寧に演奏できなかったのかという不満が残る。
サンソン・フランソワ独奏、アンドレ・クリュイタンス指揮、パリ音楽院管による演奏(1959年録音)は、感興に満ちていて、型にはまらない自由闊達なフレージングが楽しめる。即興風の表現が効果的で、何度聴いても新鮮なメロディーとリズムに接しているような気分にさせられる。ミケランジェリ盤を楷書とするなら、こちらは草書といったところ。
マルタ・アルゲリッチ独奏、クラウディオ・アバド指揮、ロンドン響による録音(1984年録音)は、ピアノもオケも技術的に完璧だし、スケール感もある。両端楽章が放つ熱気ときらめきは、同じくアルゲリッチとアバドが組んだ1967年の録音に比べると幾分落ち着いている。しかし、第2楽章のコーラングレとピアノの対話は、詩の世界にいるかのように叙情的で、この楽章だけでも聴く価値がある。
 ピエール=ロラン・エマール独奏、ピエール・ブーレーズ指揮、クリーヴランド管の演奏(2010年録音)は、ブーレーズらしく音楽の構造の深部にまで目を光らせ、アンサンブルに埋もれがちな楽器の音をうねらせている。聴き慣れたはずの作品の魅力を再発見させる刺激的な演奏だ。ブーレーズにはクリスティアン・ツィメルマンと組んだ録音もあるが(オーケストラも同じ)、オケが生き生きしているのはエマール盤の方ではないかと思う。フセイン・セルメ独奏、エマニュエル・クリヴィヌ指揮、フランス国立リヨン管の録音(1999年録音)は、弱音での緩急の付け方が印象的で、揺らめく幻想性とまろやかな色彩感を醸している。
ピエール=ロラン・エマール独奏、ピエール・ブーレーズ指揮、クリーヴランド管の演奏(2010年録音)は、ブーレーズらしく音楽の構造の深部にまで目を光らせ、アンサンブルに埋もれがちな楽器の音をうねらせている。聴き慣れたはずの作品の魅力を再発見させる刺激的な演奏だ。ブーレーズにはクリスティアン・ツィメルマンと組んだ録音もあるが(オーケストラも同じ)、オケが生き生きしているのはエマール盤の方ではないかと思う。フセイン・セルメ独奏、エマニュエル・クリヴィヌ指揮、フランス国立リヨン管の録音(1999年録音)は、弱音での緩急の付け方が印象的で、揺らめく幻想性とまろやかな色彩感を醸している。
ミケランジェリ盤のように、オーケストラは今ひとつだけどピアノは素晴らしいという録音は少なくない。アンヌ・ケフェレック独奏、アラン・ロンバール指揮、ストラスブール・フィルの演奏(1976年録音)もその一つで、軽やかで香り高いフレージングは絶品だ。音色も、基本的にはクリアーだが、強弱をつける際に陰翳が濃くなり、深いところから響くような重みが出てくる。第2楽章では、オーケストラも(途中まで)美しいアンサンブルを聴かせている。
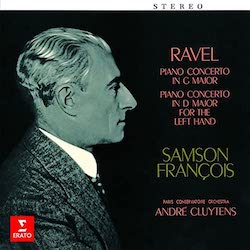
ラヴェルは自身のピアノ協奏曲について、「モーツァルトとサン=サーンスの協奏曲の精神に則って作曲した」と語っている。さらに、「協奏曲の音楽というものは、軽快かつ華麗であるべきで、深刻さを志向したりドラマティックな効果を狙ったりすべきではない」として、大げさな表現を排除した。
この作品は、当時としては珍しくジャズの要素を取り入れていることでも注目された。フランス音楽らしい色彩の豊かさ、古典主義の清潔感と品の良さ、ジャズのユーモアや物憂さという取り合わせは、どこからどう見てもアンバランスだが、ラヴェルはそれらを巧みに配合し、調和させることに成功している。
作曲にはかなり苦労したらしい。よく聴いてみると、音の重ね方が驚くほど精巧で、楽器の響きの細かいところまで計算されている。ただでさえ手のかかる曲なのに、当時(1931年)、56歳だったラヴェルは徐々に悪化する失語症や記憶障害に悩まされていた。作曲に費やされたエネルギーは大変な量だったろう。
第1楽章はアレグラメンテ。ソナタ形式。鞭の打音から始まり、ピアノによる分散和音の上で、ピッコロが跳ねるようにして第1主題を奏でる。ピアノで弾かれる第2主題はジャズの風味で、トロンボーンのグリッサンドなどがその味わいを深める。再現部で、ハープとホルンの独奏が幻想的な雰囲気を強め、ピアノのカデンツァ(トリルと分散和音)を経て、少しずつ高揚していく構成が素晴らしい。
第2楽章はアダージョ・アッサイ。3部形式。まずピアノが過去を回想するような優しい旋律(主題)を奏でる。楽章全体は108小節あるが、そのうち33小節をピアノのみで進めた後、ようやく管弦楽が柔和な表情で登場。やがて調性は不安定になり、内省的な美しさが浮き上がってくる。聴き所はコーラングレとピアノとの掛け合いで、ここは極めて繊細な弱音が求められるだけに演奏が難しそうだ。
第3楽章はプレスト。アクセントのきいた冒頭の楽節はユーモラスでパレードの雰囲気を思わせる。ピアノはトッカータ風で、5度音程の分散和音を奏で、平行和音による主題を提示する。その後、楽想とリズムを微妙に変化させながら駆け回り、最後はラヴェル好みのクレッシェンドで盛り上がり、冒頭の楽節を奏でてすっきりと終わる。
最初に聴いたときは、奇妙な音楽を耳に投げ込まれたような気分に陥った。鞭、ピアノ、ピッコロで始まる冒頭からすでに珍奇である。ハープ、高音域のホルン、コーラングレを目立たせるところも独特だ。しかし、そこは管弦楽の魔術師と呼ばれたラヴェルのこと、不思議な味わいだけでは終わらせず、巧みに音を重ねることにより、精巧で美しい音楽へと昇華させている。とりわけ第1楽章再現部、第2楽章がもたらす束の間の静謐と幻想は、聴き手を陶酔させずにはおかない。
これ以降、ラヴェルが完成させることが出来たのは『ドゥルシネア姫に心を寄せるドン・キホーテ』のみである。しかし後年、病が悪化して楽譜が書けない状態になっても、「生命とは本当に美しいものだ。だから、こんな風になっても生きている方がいいのだ」と語っていたという。
代表的な録音とされているのは、アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリが独奏を務めたもの(1957年録音)。テンポの取り方が難しい箇所でもピアノの音の粒が綺麗に整っていて、溜息が出るほど美しい。しかもキレが良い。ただ、オーケストラには雑なところがあり、もっと丁寧に演奏できなかったのかという不満が残る。
サンソン・フランソワ独奏、アンドレ・クリュイタンス指揮、パリ音楽院管による演奏(1959年録音)は、感興に満ちていて、型にはまらない自由闊達なフレージングが楽しめる。即興風の表現が効果的で、何度聴いても新鮮なメロディーとリズムに接しているような気分にさせられる。ミケランジェリ盤を楷書とするなら、こちらは草書といったところ。
マルタ・アルゲリッチ独奏、クラウディオ・アバド指揮、ロンドン響による録音(1984年録音)は、ピアノもオケも技術的に完璧だし、スケール感もある。両端楽章が放つ熱気ときらめきは、同じくアルゲリッチとアバドが組んだ1967年の録音に比べると幾分落ち着いている。しかし、第2楽章のコーラングレとピアノの対話は、詩の世界にいるかのように叙情的で、この楽章だけでも聴く価値がある。

ミケランジェリ盤のように、オーケストラは今ひとつだけどピアノは素晴らしいという録音は少なくない。アンヌ・ケフェレック独奏、アラン・ロンバール指揮、ストラスブール・フィルの演奏(1976年録音)もその一つで、軽やかで香り高いフレージングは絶品だ。音色も、基本的にはクリアーだが、強弱をつける際に陰翳が濃くなり、深いところから響くような重みが出てくる。第2楽章では、オーケストラも(途中まで)美しいアンサンブルを聴かせている。
(阿部十三)
【関連サイト】
モーリス・ラヴェル
[1875.3.7-1937.12.28]
ピアノ協奏曲 ト長調
【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)
サンソン・フランソワ (p)
アンドレ・クリュイタンス指揮
パリ音楽院管弦楽団
録音:1959年
ピエール=ロラン・エマール(p)
ピエール・ブーレーズ指揮
クリーヴランド管弦楽団
録音:2010年
[1875.3.7-1937.12.28]
ピアノ協奏曲 ト長調
【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)
サンソン・フランソワ (p)
アンドレ・クリュイタンス指揮
パリ音楽院管弦楽団
録音:1959年
ピエール=ロラン・エマール(p)
ピエール・ブーレーズ指揮
クリーヴランド管弦楽団
録音:2010年
月別インデックス
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]