
エルガー 『エニグマ変奏曲』
2022.09.04
音楽で描かれた14人

『エニグマ変奏曲』は1898年から1899年にかけて作曲され、同年6月19日、ハンス・リヒターの指揮によって初演された。正式なタイトルは「管弦楽のための独創主題による変奏曲」。楽譜の冒頭に「エニグマ(謎)」と記されていたことから、それが通称となった(作曲家もその通称を受け入れたという)。日本ではしばしば「〈謎〉変奏曲」と訳される。ちなみにリヒターによる初演の後、エルガーは改訂を行い、最終稿は1899年9月13日に作曲者自身の指揮によって披露された。当時42歳だったエルガーは作曲家としての地位を確立した。
この作品は、主題と14の変奏で構成され、各変奏には家族、友人の名前の頭文字や言い換えなどが標題的に付いている。この風変わりな着想が浮かんだのは、1898年10月、エルガーが食後にピアノを弾いているときのこと。妻のキャロラインがピアノのフレーズを気に入り、もう一度聴かせてくれるように言い、エルガーが自分の友人たちのイメージやキャラクターに合わせて、様々にアレンジして弾いてみせたのである。夫婦の楽しげなやりとりが目に浮かぶエピソードだ。
エルガー自身は、「必ずしも音楽家ばかりではない14人の友達を面白がらせ、また自分が楽しむ目的で、彼らの特徴を各変奏の中に描写したことは事実である」と証言し、個人名を伏せたまま、曲を14人に捧げた。この謎については、まもなく研究者たちによって解明され、個人名も明らかにされた。エルガーによると、「全曲を通じて演奏されない別の大きな主題がある」らしいが、それが何なのかは今もって判然としない。ミステリー作家にでも取り上げてほしい題材だ。
「自分の周囲の人をイメージした音楽」と言われると、何かこじんまりした私小説のような作品を思い浮かべたくなるが、実際のところは全く逆だ。スケールは壮大、しかも一つ一つの変奏が魅力的に書かれている。作曲家としてやっていけるかどうか不安があった時に、個人的な体験を見つめ直し、自分にしか書けない自分らしい音楽を改めて追求したことが良かったのだろう。この作品は、しばしば先行する変奏曲作品と比較されるが、それよりはムソルグスキーの『展覧会の絵』の方に近いと思う。
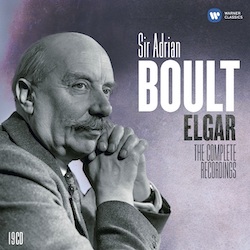
第4変奏〈W.M.B.〉は学者のウィリアム・ミーズ・ベイカー。精力的な人物だったらしく、活発で豪快な性格の曲となっている。第5変奏〈R.P.A.〉は有名な詩人の息子、リチャード・ペンローズ・アーノルド。「彼との真面目な会話は、気まぐれな冗談によって頻繁に中断される」(エルガーの言葉)様子が描写され、荘重さと軽快さが混在した不思議な世界が広がっている。第6変奏〈Ysobel〉はヴィオラ奏者のイザベル・フィットン。ヴィオラが活躍する明るく優美な曲である。第7変奏〈Troyte〉は建築家のアーサー・トロイト・グリフィス。ティンパニの猛打で荒々しく盛り上がるが、エルガーによると、これは一種の冗談で、トロイトは荒々しい人ではなかったようだ。
第8変奏〈W.N.〉はウィニフレッド・ノーブリー。古い建物に住む女性で、その優雅な雰囲気が木管のフレーズで表現され、特徴的な笑い声も再現されている。第9変奏〈Nimrod〉は親友のアウグスト・ヨハネス・イェーガー。「ニムロッド」は旧約聖書に出てくる狩の名手のことで、「イェーガー」もドイツ語で「狩人」を意味する。ベートーヴェンの緩徐楽章の素晴らしさについて語る親友への共感と敬意が込められた音楽で、ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」の第2楽章が暗示されている。第10変奏〈Dorabella〉はドーラ・ペニー。愛称の由来はモーツァルトのオペラ『コジ・ファン・トゥッテ』の登場人物である。愛らしく幻想的で軽やかな間奏曲だ。
第11変奏〈G.R.S.〉はオルガニストのジョージ・ロバートソン・シンクレア。シンクレアが飼っていたブルドッグが疾走して川に飛び込む様子が描かれている。第12変奏〈B.G.N.〉はチェロ奏者のベイジル・G・ネヴィンソン。メランコリックなチェロの旋律が沁みる曲だ。第13変奏〈* * *〉の人物は謎。モデラートのロマンツァで、最初は明るいが、雰囲気が一変し、得体の知れない驚異の前兆と官能のざわめきのようなものでゾクゾクさせる。メンデルスゾーンの『静かな海と楽しい航海』の主題が引用されていることから、ここで描かれているのは船で旅立った女性(女友達のレディ・メアリー・ライゴンか、元婚約者のヘレン・ウィーヴァー)と推理されている。第14変奏〈E.D.U.〉はエドゥー、自分自身のこと。勇ましく始まり、自分の人生に欠かせない第1変奏と第9変奏が回想され、やがて力強さを増し、オルガンを伴った壮大なクライマックスを築く。
録音が多いので何を聴けば良いのか迷うが、この作品を得意とした4人のイギリスの指揮者(トーマス・ビーチャム、エイドリアン・ボールト、マルコム・サージェント、ジョン・バルビローリ)が指揮したものなら、どれを聴いても満足感を得られると思う。私が好きなボールトとバルビローリの録音は少なくとも5種類以上ある。ボールト盤の中では、1961年にロンドン・フィルを指揮したものが理想的だ。表現意欲が旺盛で、叙情性も迫力もある。ただ、包み込むような優しさがあるのは、1970年にロンドン響を指揮したもので、人生が美しく総括されていくような感覚を抱かせる。「ニムロッド」も感動的だ。バルビローリ盤では、1956年にハレ管を指揮したものが情感豊かで、歌心に満ちている。表現は成熟しているが予定調和の演奏ではなく、クレッシェンド毎にオーケストラの音が情熱的にうねっている。

「これは」と思う演奏には、だいたい英国の指揮者、もしくは英国のオーケストラが関わっている。エルガー自身が1926年に指揮した貴重な音源もある。ポルタメントが多用されているので、好みは分かれるだろう。第1変奏が丁寧に、熱い思いを込めて演奏されているのが印象的で、キャロラインへの思いを感じさせた。21世紀以降では、オリジナル版を取り上げたマーク・エルダー盤(2002年録音)が品の良い情緒に溢れていて良い。主題のフレージングには、エルガー自身の録音からの影響がうかがえる。
【関連サイト】
エドワード・エルガー
[1857.6.2-1934.2.23]
『エニグマ変奏曲』(管弦楽のための独創主題による変奏曲)
【お薦めの演奏】(掲載ジャケット:上から)
ジョン・バルビローリ指揮
ハレ管弦楽団
録音:1956年
エイドリアン・ボールト指揮
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1961年
ピエール・モントゥー指揮
ロンドン交響楽団
録音:1962年(ライヴ録音)
[1857.6.2-1934.2.23]
『エニグマ変奏曲』(管弦楽のための独創主題による変奏曲)
【お薦めの演奏】(掲載ジャケット:上から)
ジョン・バルビローリ指揮
ハレ管弦楽団
録音:1956年
エイドリアン・ボールト指揮
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1961年
ピエール・モントゥー指揮
ロンドン交響楽団
録音:1962年(ライヴ録音)
月別インデックス
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]