
ブラームス 交響曲第3番
2024.10.05
型にとらわれず、自由に
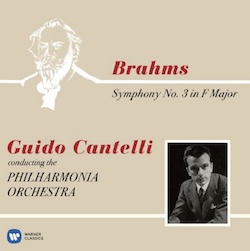
ハンス・リヒター指揮、ウィーン・フィルによる初演は成功裡に終わり、ブラームスは何度もカーテンコールに応えたという。評判は上々で、例えばエドゥアルト・ハンスリックは「健康的で、生気溢れるベートーヴェンの第2期を思わせ、ところどころにシューマンやメンデルスゾーンのあのロマン派的な光もほのかに見える」と評している。楽譜は1884年にジムロックから出版された。
第1楽章はアレグロ・コン・ブリオ。ヘ長調。ソナタ形式。管弦楽が基本動機を示し、第1主題が明るく躍動する。経過句は美しく、第2主題はのどかで優しい。第49小節以降、基本動機を発展させる手腕が鮮やかで、限られた要素で音楽の表情を大きく変化させている。展開部では第2主題を情熱的に繰り返し、徐々に穏やかになって、ホルンがゆったりと基本動機を奏で、第1主題の出現を暗示する。その暗示を繰り返し、ようやく第1主題がはっきりと姿を現し、再現部へ。再現部はほぼ型通りだが、コーダでは基本動機を大胆に変形させて第1主題を導き、第1主題と基本動機を絡ませて興奮状態に陥る。しかし、まもなく鎮まり、最後は第1主題を穏やかに奏でて終わる。
第2楽章はアンダンテ。ハ長調。3部形式。クラリネットとファゴットが穏やかな主題(冒頭主題)を奏で、弦楽器が低音でそれに応える。主題は木管によって変奏され、ヴァイオリンが加わることで明るさが増すが、すぐに暗く静かになる。中間部ではまず第40小節で木管が寂寥感のある旋律(中間部主題)を奏で、経過句に入る。ここで(第62小節で)冒頭主題をさらに変奏させた旋律があらわれ、情熱的に歌われる。その後、冒頭主題の原型が再現され、平穏な雰囲気が戻り、やがて静寂に向かう。最後に中間部主題の一部が回帰し、安穏のうちに曲を閉じる。
第3楽章はポーコ・アレグレット。ハ短調。3部形式。チェロが感傷的な主題を奏で、ヴァイオリンが引き継ぎ、さらにフルート、オーボエ、ホルンが引き継ぐ。中間部は変イ長調で、木管とチェロがのどかな旋律を奏でるが、どこか寂しげでもある。そこにヴァイオリンの優美な旋律が広がり、微妙な陰影が生まれる。その後、冒頭の主題がホルンによって再現され、オーボエがそれを引き継ぐ。最後はヴァイオリンが最後に高らかに歌い上げ、切ない余韻を残して静かに終わる。この主題は映画に使われたり、ポップスにアレンジされたりして有名になった。
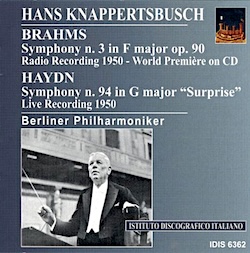
4つの楽章は全て静かに終わる。変わった趣向だが、何を意図したのだろう。第1楽章の展開部やコーダに工夫を凝らしたり、第4楽章で展開部を省いたりしているところもユニークと言えばユニークである。ブラームスなりに、ありきたりな交響曲のフォーマットから抜け出そうとしていたのだろうか。一説によると、第1楽章の基本動機は、ブラームスがモットーとしていた「Frei aber froh(自由に、しかし楽しく)」の頭文字をとり、「F-A♭-F」(ドイツ語だとF-As-F)の3音にしたらしい。先人が作った型にとらわれず、自由に交響曲を書きたいというのが本音だったのかもしれない。
第3番に関する同時代評は、先人ベートーヴェンを引き合いに出したものが目立つ。先に紹介したハンスリックもそうだが、ハンス・リヒターもベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」を念頭に置いた上で、「(第3番は)ブラームスの『英雄』である」と評した。ついでに言うと、ブラームスのことを敵視していたワーグナー派の作曲家フーゴ・ヴォルフも、ベートーヴェンの交響曲第2番と比べて「出来損ない」「独創性がない」と酷評している。
ワーグナー派に限らず、この作品を好まない人はいただろう。私自身も昔はブラームスの4つの交響曲の中で、第3番が最も苦手だった。両端楽章はいびつな大言壮語、第3楽章は通俗的に思えて仕方なかった。全体を通して聴いても、何を表現しようとしているのかよくわからなかった。それが今では何の抵抗もなく、むしろ好んで聴くようになっている。我ながら変われば変わるものだ。きっかけとなったのは、第2楽章の第62小節から始まる冒頭主題を変形させた旋律である。その歌心あふれるフレーズに魅了され、苦手意識が雲散霧消した。
また、これはHMVにいた頃お世話になった金井清隆さんの受け売りだが、第3番は指揮者にとって難易度が高く、バトンテクニックを測る上で非常に参考になる。いわば試金石みたいなものだ。注意して聴いてみると、名指揮者と言われている人でも(主に第1楽章で)苦労していることがわかる。そうした聴き方をしているうちに、だんだんこの音楽の表現の難しさ、面白さがわかってきて、親しみがわいてきた。ちなみに、金井さんはこのことをウィーンでクルト・ヴェスに教わったらしい。ヴェスは最も上手い指揮者としてハンス・クナッパーツブッシュの名を挙げていたという。
クナッパーツブッシュはこの作品を得意としていたようで、ライヴ音源が10種類ほどある。名演の誉れ高い1950年の演奏(オケはベルリン・フィル)は、第1楽章の冒頭から天変地異でも起こったかと思うくらい壮大な音が鳴り響く。テンポは遅く、アクセントの付け方は独特。フレーズを歌わせるときに低音を強調したり、彫りの深いアクセントをつけたりして、濃厚な陰影を出している。ただでさえ高度なバトンテクニックを要するこの作品で、ここまで自分の思うままに指揮している人もいないだろう。何が起こるかわからないスリリングな演奏である。ただし音質は良くない。
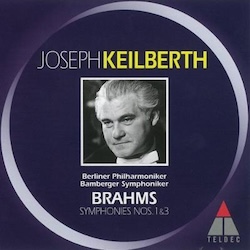
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮、ベルリン・フィル(1954年録音)、フリッツ・ライナー指揮、シカゴ交響楽団(1957年録音)、エイドリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィル(1970年録音)、マリス・ヤンソンス指揮、バイエルン放送響(2005年ライブ録音)の演奏も素晴らしい。私が最も惹かれた第2楽章の第62小節で旋律に関しては、ブルーノ・ワルター指揮、コロンビア響の演奏(1960年録音)とオイゲン・ヨッフム指揮、ロンドン・フィルの演奏(1977年録音)が双璧で、あふれんばかりの情感が伝わってくる。何度聴いても感動的だ。
(阿部十三)
【関連サイト】
Brahms:Symphony No.3(CD)
ヨハネス・ブラームス
[1833.5.7-1897.4.3]
交響曲第3番 ヘ長調 作品90
【お薦めの演奏】(掲載ジャケット:上から)
グイド・カンテルリ指揮
フィルハーモニア管弦楽団
録音:1955年
ハンス・クナッパーツブッシュ指揮
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1950年(ライヴ)
ヨーゼフ・カイルベルト指揮
バンベルク交響楽団
録音:1963年
[1833.5.7-1897.4.3]
交響曲第3番 ヘ長調 作品90
【お薦めの演奏】(掲載ジャケット:上から)
グイド・カンテルリ指揮
フィルハーモニア管弦楽団
録音:1955年
ハンス・クナッパーツブッシュ指揮
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1950年(ライヴ)
ヨーゼフ・カイルベルト指揮
バンベルク交響楽団
録音:1963年
月別インデックス
- November 2025 [1]
- September 2025 [1]
- July 2025 [1]
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]