
カール・シューリヒト 〜本物の至芸〜 [続き]
2013.07.19
比類なき至芸の結晶
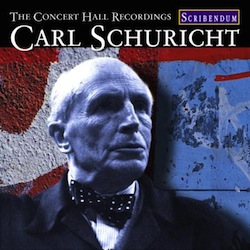 作品の美質を引き出す術は、オーケストラの美質を引き出す術と無関係ではあり得ない。シューリヒトはそのことを心得ていた。彼は固定スタイルを団員たちに押しつけるタイプの指揮者ではなかった。オーケストラが変われば演奏も変わる。ただ、いかなる方向からでも作品の核へと迫ろうとする、その姿勢は変わらない。
作品の美質を引き出す術は、オーケストラの美質を引き出す術と無関係ではあり得ない。シューリヒトはそのことを心得ていた。彼は固定スタイルを団員たちに押しつけるタイプの指揮者ではなかった。オーケストラが変われば演奏も変わる。ただ、いかなる方向からでも作品の核へと迫ろうとする、その姿勢は変わらない。
ウィーン・フィルとの組み合わせでは、1960年のザルツブルク音楽祭で演奏されたモーツァルトの「プラハ」、1961年に録音されたブルックナーの交響曲第9番が双璧。1953年に録音されたブラームスの交響曲第2番、その10年後に録音されたブルックナーの第8番も長い間ファンに愛されている名演奏だ。
オケはウィーン・フィルではなくパリ音楽院管だが、ベートーヴェンの「田園」も、絶品としかいいようのないテヌートで魅了する珠玉の演奏。同オケとのシューマンの「ライン」も素晴らしい。弾けんばかりの生々しい色彩感、胸のすくようなみずみずしさ、過剰になりがちな響きを中和させるノーブルな歌い回しで最後まで聴き手を飽きさせない。バイエルン放送響とのブラームスの交響曲第4番も誉れ高い名盤だが、お得意の曲だけにライヴ音源が少なくない。その中だと、フランス国立放送管との濃厚な演奏(1959年3月24日)、融通無碍の境地を示すウィーン・フィルとの演奏(1965年4月24日)が余韻嫋々である。ロシアものでは、シュトゥットガルト放送響とのチャイコフスキーの交響曲第4番のライヴが迫力満点。「淡々としていないシューリヒト」の代表盤である。
一流とはいいがたいオーケストラを振る時も、シューリヒトは自分の持てる力の全てを出し、オーケストラに持てる力の全てを出させる。ハーグ・フィルとのブルックナーの交響曲第7番や、パリ・オペラ座管とのモーツァルトの「リンツ」、「プラハ」を聴いても分かるように、彼は団員たちを無理やり自分色に染めることはない。オーケストラ自体が有している音色の素朴な持ち味を十全に活かし、巧みにテンポを揺らしながら表情付けを行い、ほかの指揮者が同じオケを振っても到底なしえないような名演奏へと導いている。彼の手にかかると、「なぜこのオーケストラがこのような演奏をすることが出来たのだろう」ということが起こるのである。
協奏曲、ミサ曲、オペラなど
戦前の音源では、ベルリン・フィルとのブルックナーの交響曲第7番が有名。その端正な表現と引き締まった造型は、今聴いても古さを感じさせない。シューリヒトの「ブル7」には既述したハーグ・フィル盤のほかに、コロンヌ管、デンマーク放送響、シュトゥットガルト放送響、フランス国立放送管などとのライヴ録音もあるので、あえてベルリン・フィル盤を選んで聴く必要はないかもしれないが、「ブル7」好きの人には一聴の価値がある。
1935年に録音されたビゼーの「アルルの女」第1組曲は、掛け値なしの名演。端正さの中にもどこか寒々しい寂寥感が漂っていて、時折その弱音のニュアンスにゾッとさせられる。ただし、音質は古い。
シューリヒトは伴奏指揮者としても一流だった。名人芸の極みともいえるのが、ヴィルヘルム・バックハウスとのブラームスのピアノ協奏曲第2番、タチアナ・ニコラーエワとのモーツァルトのピアノ協奏曲第22番。ソリストを引き立てつつ、要所では管楽器の細かいアクセントにこだわり、全体の響きに深みを与えている。
そして十八番の『ミサ・ソレムニス』。合唱の扱いに長けていたシューリヒトの至芸をここで確認することが出来る。かなりテンポを動かしているが、冗長さや不必要な過剰さを全く感じさせない。一つ一つの音符に対して「こう演奏されるべき」という強い信念を持ち、オーケストラとソリストの集中力を極限まで高め、この荘厳な作品を一気に聴かせる。私が所有しているのは1957年9月15日のライヴ音源。廃盤と再発を繰り返しているようだが、こういう遺産は多くの人に聴かれるべきである。
「歌」が絡む作品では、ベートーヴェンの第九、ブラームスの「ドイツ・レクイエム」、マーラーの「復活」、「大地の歌」も聴いておきたい。シューリヒトならではの間の取り方や管楽器の歌わせ方が、効果的に「歌」を引き立てる方向に作用し、忘れがたい感銘を残すに違いない。最も分かりやすい例としては、第九の〈Über Sternen muß er wohnen.〉の箇所などを挙げることが出来るだろう。ちなみに、「大地の歌」は1939年10月5日のライヴ音源で、ヒステリックな女性客による野次が収録されていることもあり、時代背景をうかがわせるが、演奏そのものはエネルギーに満ちていて、時に絶美である。
オペラの全曲録音は、今のところ、師フンパーディンクの『ヘンゼルとグレーテル』くらいしかないようである。その音源(1962年12月、放送用セッション)を聴く限り、一部の歌手にやや難を感じるものの、演奏自体は非常に美しく、フィナーレも感動的だ。ないものねだりは承知の上で、シューリヒトが指揮したオペラをもっと聴きたいものである。
【関連サイト】
カール・シューリヒト 〜本物の至芸〜
カール・シューリヒト(CD)
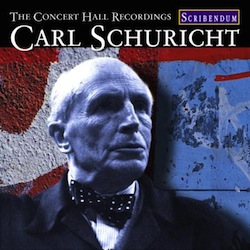
ウィーン・フィルとの組み合わせでは、1960年のザルツブルク音楽祭で演奏されたモーツァルトの「プラハ」、1961年に録音されたブルックナーの交響曲第9番が双璧。1953年に録音されたブラームスの交響曲第2番、その10年後に録音されたブルックナーの第8番も長い間ファンに愛されている名演奏だ。
オケはウィーン・フィルではなくパリ音楽院管だが、ベートーヴェンの「田園」も、絶品としかいいようのないテヌートで魅了する珠玉の演奏。同オケとのシューマンの「ライン」も素晴らしい。弾けんばかりの生々しい色彩感、胸のすくようなみずみずしさ、過剰になりがちな響きを中和させるノーブルな歌い回しで最後まで聴き手を飽きさせない。バイエルン放送響とのブラームスの交響曲第4番も誉れ高い名盤だが、お得意の曲だけにライヴ音源が少なくない。その中だと、フランス国立放送管との濃厚な演奏(1959年3月24日)、融通無碍の境地を示すウィーン・フィルとの演奏(1965年4月24日)が余韻嫋々である。ロシアものでは、シュトゥットガルト放送響とのチャイコフスキーの交響曲第4番のライヴが迫力満点。「淡々としていないシューリヒト」の代表盤である。
一流とはいいがたいオーケストラを振る時も、シューリヒトは自分の持てる力の全てを出し、オーケストラに持てる力の全てを出させる。ハーグ・フィルとのブルックナーの交響曲第7番や、パリ・オペラ座管とのモーツァルトの「リンツ」、「プラハ」を聴いても分かるように、彼は団員たちを無理やり自分色に染めることはない。オーケストラ自体が有している音色の素朴な持ち味を十全に活かし、巧みにテンポを揺らしながら表情付けを行い、ほかの指揮者が同じオケを振っても到底なしえないような名演奏へと導いている。彼の手にかかると、「なぜこのオーケストラがこのような演奏をすることが出来たのだろう」ということが起こるのである。
協奏曲、ミサ曲、オペラなど
戦前の音源では、ベルリン・フィルとのブルックナーの交響曲第7番が有名。その端正な表現と引き締まった造型は、今聴いても古さを感じさせない。シューリヒトの「ブル7」には既述したハーグ・フィル盤のほかに、コロンヌ管、デンマーク放送響、シュトゥットガルト放送響、フランス国立放送管などとのライヴ録音もあるので、あえてベルリン・フィル盤を選んで聴く必要はないかもしれないが、「ブル7」好きの人には一聴の価値がある。
1935年に録音されたビゼーの「アルルの女」第1組曲は、掛け値なしの名演。端正さの中にもどこか寒々しい寂寥感が漂っていて、時折その弱音のニュアンスにゾッとさせられる。ただし、音質は古い。
シューリヒトは伴奏指揮者としても一流だった。名人芸の極みともいえるのが、ヴィルヘルム・バックハウスとのブラームスのピアノ協奏曲第2番、タチアナ・ニコラーエワとのモーツァルトのピアノ協奏曲第22番。ソリストを引き立てつつ、要所では管楽器の細かいアクセントにこだわり、全体の響きに深みを与えている。
そして十八番の『ミサ・ソレムニス』。合唱の扱いに長けていたシューリヒトの至芸をここで確認することが出来る。かなりテンポを動かしているが、冗長さや不必要な過剰さを全く感じさせない。一つ一つの音符に対して「こう演奏されるべき」という強い信念を持ち、オーケストラとソリストの集中力を極限まで高め、この荘厳な作品を一気に聴かせる。私が所有しているのは1957年9月15日のライヴ音源。廃盤と再発を繰り返しているようだが、こういう遺産は多くの人に聴かれるべきである。
「歌」が絡む作品では、ベートーヴェンの第九、ブラームスの「ドイツ・レクイエム」、マーラーの「復活」、「大地の歌」も聴いておきたい。シューリヒトならではの間の取り方や管楽器の歌わせ方が、効果的に「歌」を引き立てる方向に作用し、忘れがたい感銘を残すに違いない。最も分かりやすい例としては、第九の〈Über Sternen muß er wohnen.〉の箇所などを挙げることが出来るだろう。ちなみに、「大地の歌」は1939年10月5日のライヴ音源で、ヒステリックな女性客による野次が収録されていることもあり、時代背景をうかがわせるが、演奏そのものはエネルギーに満ちていて、時に絶美である。
オペラの全曲録音は、今のところ、師フンパーディンクの『ヘンゼルとグレーテル』くらいしかないようである。その音源(1962年12月、放送用セッション)を聴く限り、一部の歌手にやや難を感じるものの、演奏自体は非常に美しく、フィナーレも感動的だ。ないものねだりは承知の上で、シューリヒトが指揮したオペラをもっと聴きたいものである。
(阿部十三)
【関連サイト】
カール・シューリヒト 〜本物の至芸〜
カール・シューリヒト(CD)
月別インデックス
- June 2024 [1]
- February 2024 [1]
- April 2023 [2]
- February 2023 [1]
- November 2022 [1]
- June 2022 [1]
- April 2022 [1]
- January 2022 [1]
- August 2021 [1]
- April 2021 [1]
- January 2021 [1]
- September 2020 [1]
- August 2020 [1]
- March 2020 [1]
- November 2019 [1]
- July 2019 [1]
- May 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [1]
- August 2018 [1]
- May 2018 [1]
- January 2018 [1]
- July 2017 [1]
- March 2017 [2]
- December 2016 [1]
- October 2016 [1]
- May 2016 [1]
- March 2016 [2]
- October 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- March 2015 [2]
- December 2014 [1]
- October 2014 [2]
- July 2014 [1]
- April 2014 [2]
- March 2014 [1]
- January 2014 [1]
- December 2013 [1]
- October 2013 [1]
- July 2013 [2]
- May 2013 [1]
- April 2013 [1]
- February 2013 [2]
- January 2013 [1]
- November 2012 [1]
- October 2012 [1]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- May 2012 [1]
- April 2012 [1]
- March 2012 [1]
- January 2012 [1]
- December 2011 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [2]
- June 2011 [3]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]