
オットー・クレンペラー 〜大器の音楽〜
2016.03.19
マーラーの影響
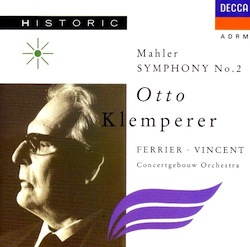 若い頃、オットー・クレンペラーはマーラーの交響曲第2番「復活」をピアノ用に編曲して暗譜で演奏し、作曲者に認められた。そして、そのとき書いてもらった推薦状のおかげで、プラハの歌劇場の指揮者になることができた。1907年のことである。
若い頃、オットー・クレンペラーはマーラーの交響曲第2番「復活」をピアノ用に編曲して暗譜で演奏し、作曲者に認められた。そして、そのとき書いてもらった推薦状のおかげで、プラハの歌劇場の指揮者になることができた。1907年のことである。
「すぐれた音楽家クレンペラー氏をご推薦申し上げます。氏はまだ若年にもかかわらず、すでに経験豊かであり、指揮者の職につくべく定められた人物です」
後年クレンペラーは、プロデューサーのウォルター・レッグに「なぜブルックナーよりマーラーの作品を多く指揮するのか」と訊かれた際、「マーラーはユダヤ人だし、初めて私に仕事をくれた人だから」と冗談まじりに答えていたらしい。厳密に言えば、クレンペラーはそれ以前にもマックス・ラインハルト演出の『天国と地獄』で指揮を務めているのだが、キャリアの土台を作ってくれたのはマーラーなのである。
しかし、マーラーは単に「初めて仕事をくれた人」であるだけでなく、指揮者として模範とすべき人でもあった。ピーター・ヘイワースによるインタビュー集『クレンペラーとの対話』には、マーラー指揮によるベートーヴェンの交響曲第7番の第2楽章冒頭を聴いたとき、クレンペラーがどう感じたのか記されている。
「それはまったく違うひびきがしたのです。しかしわたしはそれに対して、たしかに『同感だ』と言うことができました。マーラーが指揮したときには、これ以上でも、これ以外でもありえないと感じるのです。ほかの指揮者の場合にはこのようなことはありません。ほかの指揮者はそれぞれに問題点があり、完全に満足するということはない。しかしマーラーにはまったく問題がないのです」
1955年に録音されたクレンペラー指揮、フィルハーモニア管による第7交響曲の第2楽章も、ほかの指揮者とは明らかに違う響きがする。弦楽セクションのバランスを調整し、普通はそこまで強調されない旋律を浮き上がらせているのだ。しかし違和感は全くない。そこから感じとれるのは、いわば畏怖の念を起こさせる美しさである。たしかに「これ以上でも、これ以外でもありえない」と心底思える響きだ。おそらくクレンペラーの特異とも言えるアンサンブルのバランス感覚は、マーラーから受け継ぎ、発展させたものなのだろう。
グルックのオペラ『アウリスのイフィゲニア』も、若い頃にマーラーを通じて接した作品であり、クレンペラーはこの序曲(ワーグナー編曲)を1960年に録音している。これは彼が指揮するとどんなに凄いことが起こるのかを如実に示す大演奏だ。その格調の高さ、一切の感傷を排した厳格さ、揺るぎない堅牢性、抑えの利かない圧倒的な悲劇性は、人間の作り出したものとは思えない。
さまざまな困難
ユダヤ人だったクレンペラーは、ナチス台頭の際、亡命を余儀なくされた。しかし、そんな話さえ霞んでしまうほど、彼の88年にわたる人生はさまざまな災難にあふれている。そして、その都度不死鳥のごとくよみがえっている。脳腫瘍を患ったり、煙草の火で大やけどして一命をとりとめたり、転倒して大ケガを負い手術を受けたり......そんな出来事を挙げていくとキリがない。スキャンダルとも無縁ではなく、若き日に名歌手エリザベート・シューマンと不倫関係に陥り、観客からブーイングを受けたこともある。気に入ったオーケストラの女性奏者に執着していたこともよく知られている。躁鬱病を抱えていたこと、奇行が目立ったこと、ユダヤ人らしいジョークを連発していたことから、とにかくエピソードが多い人である。
1910年代後半からオペラ指揮者として高い評価を得ていたが、クロール・オペラの監督に就任(1927年)してからは同時代の音楽を積極的に取り上げ、先鋭的な音楽家として知られた。しかし、ナチスの介入やハインツ・ティーティエンとの確執などでうまくいかなくなり、スイス経由でアメリカに亡命。各地で指揮し、とくにロサンゼルス・フィル、ピッツバーグ響と深く関わった。その後、闘病を経てヨーロッパの楽壇に復帰。1946年にストックホルムで指揮し、1947年からブダペスト・オペラで采配を振るったが、地位も収入もなかなか安定しなかった。風向きが良くなったのは1952年にEMIと契約した頃からで、1959年にフィルハーモニア管弦楽団の首席指揮者に就任した。このとき、すでに74歳になっていた。
こうした事実を知っていても、クレンペラーが遺した録音を聴いて、世に言う「苦労人」の姿を思い浮かべる人はいないだろう。「大鷲」とも形容された(大柄な人だった)腕の動きから生まれる音楽は、スケールがとてつもなく大きく、非感傷的で無駄な装飾がなく、音が流れていくというより上に積み重なっていくような構築感と立体感がある。音の塊でできた巨大建造物とでも言おうか。だからといって、音楽は冷徹でもなく、硬直してもいない。クレンペラーの手にかかると、ひとつひとつの音符が楽器の生々しい音色と共にぐっと浮き上がってくるのである。とりわけ対位法を用いた作品だと、その意匠は感動的なものになる。
【関連サイト】
オットー・クレンペラー 〜大器の音楽〜 [続き]
『クレンペラーとの対話』(白水社)
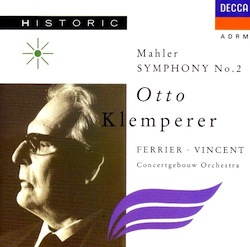
「すぐれた音楽家クレンペラー氏をご推薦申し上げます。氏はまだ若年にもかかわらず、すでに経験豊かであり、指揮者の職につくべく定められた人物です」
後年クレンペラーは、プロデューサーのウォルター・レッグに「なぜブルックナーよりマーラーの作品を多く指揮するのか」と訊かれた際、「マーラーはユダヤ人だし、初めて私に仕事をくれた人だから」と冗談まじりに答えていたらしい。厳密に言えば、クレンペラーはそれ以前にもマックス・ラインハルト演出の『天国と地獄』で指揮を務めているのだが、キャリアの土台を作ってくれたのはマーラーなのである。
しかし、マーラーは単に「初めて仕事をくれた人」であるだけでなく、指揮者として模範とすべき人でもあった。ピーター・ヘイワースによるインタビュー集『クレンペラーとの対話』には、マーラー指揮によるベートーヴェンの交響曲第7番の第2楽章冒頭を聴いたとき、クレンペラーがどう感じたのか記されている。
「それはまったく違うひびきがしたのです。しかしわたしはそれに対して、たしかに『同感だ』と言うことができました。マーラーが指揮したときには、これ以上でも、これ以外でもありえないと感じるのです。ほかの指揮者の場合にはこのようなことはありません。ほかの指揮者はそれぞれに問題点があり、完全に満足するということはない。しかしマーラーにはまったく問題がないのです」
1955年に録音されたクレンペラー指揮、フィルハーモニア管による第7交響曲の第2楽章も、ほかの指揮者とは明らかに違う響きがする。弦楽セクションのバランスを調整し、普通はそこまで強調されない旋律を浮き上がらせているのだ。しかし違和感は全くない。そこから感じとれるのは、いわば畏怖の念を起こさせる美しさである。たしかに「これ以上でも、これ以外でもありえない」と心底思える響きだ。おそらくクレンペラーの特異とも言えるアンサンブルのバランス感覚は、マーラーから受け継ぎ、発展させたものなのだろう。
グルックのオペラ『アウリスのイフィゲニア』も、若い頃にマーラーを通じて接した作品であり、クレンペラーはこの序曲(ワーグナー編曲)を1960年に録音している。これは彼が指揮するとどんなに凄いことが起こるのかを如実に示す大演奏だ。その格調の高さ、一切の感傷を排した厳格さ、揺るぎない堅牢性、抑えの利かない圧倒的な悲劇性は、人間の作り出したものとは思えない。
さまざまな困難
ユダヤ人だったクレンペラーは、ナチス台頭の際、亡命を余儀なくされた。しかし、そんな話さえ霞んでしまうほど、彼の88年にわたる人生はさまざまな災難にあふれている。そして、その都度不死鳥のごとくよみがえっている。脳腫瘍を患ったり、煙草の火で大やけどして一命をとりとめたり、転倒して大ケガを負い手術を受けたり......そんな出来事を挙げていくとキリがない。スキャンダルとも無縁ではなく、若き日に名歌手エリザベート・シューマンと不倫関係に陥り、観客からブーイングを受けたこともある。気に入ったオーケストラの女性奏者に執着していたこともよく知られている。躁鬱病を抱えていたこと、奇行が目立ったこと、ユダヤ人らしいジョークを連発していたことから、とにかくエピソードが多い人である。
1910年代後半からオペラ指揮者として高い評価を得ていたが、クロール・オペラの監督に就任(1927年)してからは同時代の音楽を積極的に取り上げ、先鋭的な音楽家として知られた。しかし、ナチスの介入やハインツ・ティーティエンとの確執などでうまくいかなくなり、スイス経由でアメリカに亡命。各地で指揮し、とくにロサンゼルス・フィル、ピッツバーグ響と深く関わった。その後、闘病を経てヨーロッパの楽壇に復帰。1946年にストックホルムで指揮し、1947年からブダペスト・オペラで采配を振るったが、地位も収入もなかなか安定しなかった。風向きが良くなったのは1952年にEMIと契約した頃からで、1959年にフィルハーモニア管弦楽団の首席指揮者に就任した。このとき、すでに74歳になっていた。
こうした事実を知っていても、クレンペラーが遺した録音を聴いて、世に言う「苦労人」の姿を思い浮かべる人はいないだろう。「大鷲」とも形容された(大柄な人だった)腕の動きから生まれる音楽は、スケールがとてつもなく大きく、非感傷的で無駄な装飾がなく、音が流れていくというより上に積み重なっていくような構築感と立体感がある。音の塊でできた巨大建造物とでも言おうか。だからといって、音楽は冷徹でもなく、硬直してもいない。クレンペラーの手にかかると、ひとつひとつの音符が楽器の生々しい音色と共にぐっと浮き上がってくるのである。とりわけ対位法を用いた作品だと、その意匠は感動的なものになる。
【関連サイト】
オットー・クレンペラー 〜大器の音楽〜 [続き]
『クレンペラーとの対話』(白水社)
月別インデックス
- June 2024 [1]
- February 2024 [1]
- April 2023 [2]
- February 2023 [1]
- November 2022 [1]
- June 2022 [1]
- April 2022 [1]
- January 2022 [1]
- August 2021 [1]
- April 2021 [1]
- January 2021 [1]
- September 2020 [1]
- August 2020 [1]
- March 2020 [1]
- November 2019 [1]
- July 2019 [1]
- May 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [1]
- August 2018 [1]
- May 2018 [1]
- January 2018 [1]
- July 2017 [1]
- March 2017 [2]
- December 2016 [1]
- October 2016 [1]
- May 2016 [1]
- March 2016 [2]
- October 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- March 2015 [2]
- December 2014 [1]
- October 2014 [2]
- July 2014 [1]
- April 2014 [2]
- March 2014 [1]
- January 2014 [1]
- December 2013 [1]
- October 2013 [1]
- July 2013 [2]
- May 2013 [1]
- April 2013 [1]
- February 2013 [2]
- January 2013 [1]
- November 2012 [1]
- October 2012 [1]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- May 2012 [1]
- April 2012 [1]
- March 2012 [1]
- January 2012 [1]
- December 2011 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [2]
- June 2011 [3]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]