
ヴィルヘルム・バックハウス 〜霊感と確信に満ちた演奏〜
2017.03.10
何もかもが音楽的
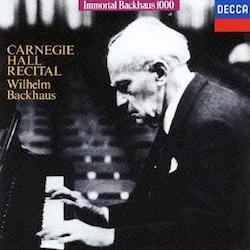 ヴィルヘルム・バックハウスは「鍵盤の獅子王」と呼ばれたドイツのピアニストで、ベートーヴェンやブラームスを得意としていた。質実剛健、謹厳実直と言われることが多いが、その音楽性は決して堅苦しいものではなく、聴き手に息詰まるような緊張を強いるものでもない。むしろ、すぐれた音楽作品に封じ込められた神秘をあっさりと解き放ち、難解さやいかめしさとは異なる次元で聴かせるピアニストである。
ヴィルヘルム・バックハウスは「鍵盤の獅子王」と呼ばれたドイツのピアニストで、ベートーヴェンやブラームスを得意としていた。質実剛健、謹厳実直と言われることが多いが、その音楽性は決して堅苦しいものではなく、聴き手に息詰まるような緊張を強いるものでもない。むしろ、すぐれた音楽作品に封じ込められた神秘をあっさりと解き放ち、難解さやいかめしさとは異なる次元で聴かせるピアニストである。
アーティキュレーションには不自然さがなく、余分なメッセージ性を入り込ませることもない。小手先でころころ表情を変えるピアニズムとは隔絶している。主情的ではないが、かといって理知的とも言い難い。あたかも霊感と確信に支えられながら、音符の一つ一つを息づかせているようなところがある。その何もかもが音楽的なのだ。
85年の生涯
生まれたのは1884年3月26日。生地ライプツィヒで教育を受けた後、弟子をとらないことで知られるオイゲン・ダルベールに見込まれてその指導を受けた。16歳の時に初めてコンサート・ツアーを行い、ロンドンで大成功を収め、1905年にはアントン・ルービンシュタイン国際コンクールのピアノ部門で優勝。その時2位になったベラ・バルトークがピアニストの道を断念したことは有名な話だ。
若い頃から絶大な人気を誇り、ヨーロッパのみならずアメリカでも成功し、カーティス音楽院で教鞭を執ったこともあるが、バックハウスの大ファンだったアドルフ・ヒトラーが彼のことをナチス・ドイツの宣伝に利用したため、戦後はなかなか渡米できなかった(なおバックハウスは1930年代はじめにスイスに移住し、1946年に帰化している)。ようやくカーネギー・ホールでのリサイタルが実現したのは70歳になった1954年3月のこと。4月には来日してリサイタルを開き、1ヶ月半ほど滞在していた。
日本での出来事はバックハウス自身によって記録されている。そこには東京、大阪、京都、福岡で演奏したことのほかに、歌舞伎を観たこと、奈良で名所見物をして春日山で災難に遭ったこと、皇后陛下の前で演奏したこと、ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮によるN響のコンサートを聴きに行ったことなどが書かれている。若い日本人ピアニストの演奏を聴いて感心しつつも、もう少し詩的であってほしいと思ったという一文も興味深い。
1960年代に入っても精力的にコンサート活動を続けていたが、1969年7月5日、85歳で死去。6月26日、28日にオーストリアのケルンテン州のオシアッハ修道院教会でリサイタルを行い、2日目にベートーヴェンのピアノ・ソナタを演奏している途中、心臓発作を起こしたのだ。それでも周囲の反対を押し切り、シューマン、シューベルトを演奏。その一週間後に亡くなった。
ロマン派の感性
バックハウスはコンサート・ピアニストとして生きた。20世紀の偉大な演奏家の大半がそうであるように、彼もまたライヴの人である。音楽院で教えていたのは若い頃の話で、教育者として弟子をとることはなく、作曲や指揮に手を出すこともなかった。本を書いていたという話も聞かない。これだけ偉大なピアニストなのに決定版と呼ぶべき伝記がないのも意外である。いくつかの資料には、酒も煙草も嗜まなかったと明記されているが、私が持っているブラームスのピアノ協奏曲第2番のCDジャケットには、煙草を持つ姿が写っている。本人の証言や記録がまとまった形で存在しないために、ストイックなイメージが先行し、こういうことが起こるのだろう。
ダルベールの師はリスト、リストの師はベートーヴェンの弟子ツェルニーなので、バックハウスはベートーヴェン直系の弟子筋にあたる。愛奏していたピアノは、リストも弾いていたベーゼンドルファー。バックハウスはその深みのある豊かな響きを自在にコントロールし、骨太で重みのあるフォルテ、やわらかな暖色のピアニッシモ、珠のように美しい音色を聴き手に堪能させる。
若い頃の録音では、卓越したテクニックを披露しているが、ショパンの練習曲(1928年録音)の「別れの曲」のような作品だと、不要な感傷を避けつつ、過剰にならない程度に詩情を重んじ、遅めのテンポでじっくりと演奏している。堅苦しさや技術だけの冷たさとは別物である。ショパンのピアノ協奏曲第1番をバックハウスがピアノ独奏用にアレンジした「ロマンス」(1925年録音)は、ロマン派の感性から生まれた結晶。音質が古くても、その幻想的な音の流れに接すれば、バックハウスのロマンティックな一面を味わえる。ショパン弾きとして人気があったというのも納得だ。
【関連サイト】
Wilhelm Backhaus(CD)
ヴィルヘルム・バックハウス 〜霊感と確信に満ちた演奏〜 [続き]
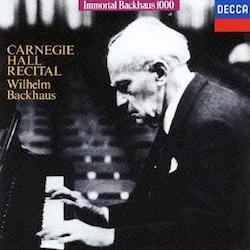
アーティキュレーションには不自然さがなく、余分なメッセージ性を入り込ませることもない。小手先でころころ表情を変えるピアニズムとは隔絶している。主情的ではないが、かといって理知的とも言い難い。あたかも霊感と確信に支えられながら、音符の一つ一つを息づかせているようなところがある。その何もかもが音楽的なのだ。
85年の生涯
生まれたのは1884年3月26日。生地ライプツィヒで教育を受けた後、弟子をとらないことで知られるオイゲン・ダルベールに見込まれてその指導を受けた。16歳の時に初めてコンサート・ツアーを行い、ロンドンで大成功を収め、1905年にはアントン・ルービンシュタイン国際コンクールのピアノ部門で優勝。その時2位になったベラ・バルトークがピアニストの道を断念したことは有名な話だ。
若い頃から絶大な人気を誇り、ヨーロッパのみならずアメリカでも成功し、カーティス音楽院で教鞭を執ったこともあるが、バックハウスの大ファンだったアドルフ・ヒトラーが彼のことをナチス・ドイツの宣伝に利用したため、戦後はなかなか渡米できなかった(なおバックハウスは1930年代はじめにスイスに移住し、1946年に帰化している)。ようやくカーネギー・ホールでのリサイタルが実現したのは70歳になった1954年3月のこと。4月には来日してリサイタルを開き、1ヶ月半ほど滞在していた。
日本での出来事はバックハウス自身によって記録されている。そこには東京、大阪、京都、福岡で演奏したことのほかに、歌舞伎を観たこと、奈良で名所見物をして春日山で災難に遭ったこと、皇后陛下の前で演奏したこと、ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮によるN響のコンサートを聴きに行ったことなどが書かれている。若い日本人ピアニストの演奏を聴いて感心しつつも、もう少し詩的であってほしいと思ったという一文も興味深い。
1960年代に入っても精力的にコンサート活動を続けていたが、1969年7月5日、85歳で死去。6月26日、28日にオーストリアのケルンテン州のオシアッハ修道院教会でリサイタルを行い、2日目にベートーヴェンのピアノ・ソナタを演奏している途中、心臓発作を起こしたのだ。それでも周囲の反対を押し切り、シューマン、シューベルトを演奏。その一週間後に亡くなった。
ロマン派の感性
バックハウスはコンサート・ピアニストとして生きた。20世紀の偉大な演奏家の大半がそうであるように、彼もまたライヴの人である。音楽院で教えていたのは若い頃の話で、教育者として弟子をとることはなく、作曲や指揮に手を出すこともなかった。本を書いていたという話も聞かない。これだけ偉大なピアニストなのに決定版と呼ぶべき伝記がないのも意外である。いくつかの資料には、酒も煙草も嗜まなかったと明記されているが、私が持っているブラームスのピアノ協奏曲第2番のCDジャケットには、煙草を持つ姿が写っている。本人の証言や記録がまとまった形で存在しないために、ストイックなイメージが先行し、こういうことが起こるのだろう。
ダルベールの師はリスト、リストの師はベートーヴェンの弟子ツェルニーなので、バックハウスはベートーヴェン直系の弟子筋にあたる。愛奏していたピアノは、リストも弾いていたベーゼンドルファー。バックハウスはその深みのある豊かな響きを自在にコントロールし、骨太で重みのあるフォルテ、やわらかな暖色のピアニッシモ、珠のように美しい音色を聴き手に堪能させる。
若い頃の録音では、卓越したテクニックを披露しているが、ショパンの練習曲(1928年録音)の「別れの曲」のような作品だと、不要な感傷を避けつつ、過剰にならない程度に詩情を重んじ、遅めのテンポでじっくりと演奏している。堅苦しさや技術だけの冷たさとは別物である。ショパンのピアノ協奏曲第1番をバックハウスがピアノ独奏用にアレンジした「ロマンス」(1925年録音)は、ロマン派の感性から生まれた結晶。音質が古くても、その幻想的な音の流れに接すれば、バックハウスのロマンティックな一面を味わえる。ショパン弾きとして人気があったというのも納得だ。
【関連サイト】
Wilhelm Backhaus(CD)
ヴィルヘルム・バックハウス 〜霊感と確信に満ちた演奏〜 [続き]
月別インデックス
- June 2024 [1]
- February 2024 [1]
- April 2023 [2]
- February 2023 [1]
- November 2022 [1]
- June 2022 [1]
- April 2022 [1]
- January 2022 [1]
- August 2021 [1]
- April 2021 [1]
- January 2021 [1]
- September 2020 [1]
- August 2020 [1]
- March 2020 [1]
- November 2019 [1]
- July 2019 [1]
- May 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [1]
- August 2018 [1]
- May 2018 [1]
- January 2018 [1]
- July 2017 [1]
- March 2017 [2]
- December 2016 [1]
- October 2016 [1]
- May 2016 [1]
- March 2016 [2]
- October 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- March 2015 [2]
- December 2014 [1]
- October 2014 [2]
- July 2014 [1]
- April 2014 [2]
- March 2014 [1]
- January 2014 [1]
- December 2013 [1]
- October 2013 [1]
- July 2013 [2]
- May 2013 [1]
- April 2013 [1]
- February 2013 [2]
- January 2013 [1]
- November 2012 [1]
- October 2012 [1]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- May 2012 [1]
- April 2012 [1]
- March 2012 [1]
- January 2012 [1]
- December 2011 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [2]
- June 2011 [3]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]