
エルネスト・アンセルメ伝 [続き]
2023.04.14
作品の解釈
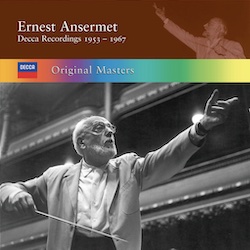 アンセルメは原典主義者ではなく、必要に応じて総譜を修正・変更していた。作曲家は幅広い解釈の余地を解釈者に委ねるものだ、というのが彼の持論だった。指揮者は作曲家の奴隷ではない。適切な解釈を行い、指揮者自身の意見を伝えなければならないとも主張していた。これは若い頃、ドビュッシー、ラヴェル、ストラヴィンスキーといった人たちと意見交換を行い、自分の提案を受け入れてもらった経験に基づいているのだろう。
アンセルメは原典主義者ではなく、必要に応じて総譜を修正・変更していた。作曲家は幅広い解釈の余地を解釈者に委ねるものだ、というのが彼の持論だった。指揮者は作曲家の奴隷ではない。適切な解釈を行い、指揮者自身の意見を伝えなければならないとも主張していた。これは若い頃、ドビュッシー、ラヴェル、ストラヴィンスキーといった人たちと意見交換を行い、自分の提案を受け入れてもらった経験に基づいているのだろう。
アンセルメの音楽観
「人間の情緒的主観性こそが、音楽の源である」ーー思想家でもあったアンセルメは、フッサールの現象主義を応用し、音楽というものを客観的な音響現象としてではなく、人間の意識の現象として捉えていた。その立場から、転調という現象も、「転調するのは人間の主観性であり、音ではない」とする。
アンセルメにとって大事なのは、美しい響きを出すことでも、単に譜面通りに演奏することでもなく、作品を正しく解釈し、聴き手に対して、情緒的な意味作用を及ぼすことだった。少々難解な話を私なりに噛み砕いて説明すると、その情緒的な意味をもたらす素となるのが、カダンス(アンセルメの造語)である。カダンスとは、楽曲を解釈することによって把握される根源的な感情・情緒の流れであり、人間の自然な認識作用と調和するものである。これがフレーズ、リズムを形成する土台となる。解釈以前の音楽テキストは、「音構造の抽象的な図式」にすぎない。演奏家は楽譜を研究をすることで、抽象的図式の奥にある感情・情緒(作曲家が音楽を書いた時の感情、作曲家に音楽を書かせたもの)を見出し、それと同化しなければならないのだ。
しかしながら、情緒的な意味作用が明らかに生じるのは、その作品が調性の法則によって支配されている(もしくは調性から完全には離れていない)場合のみである。調性から離れたセリー音楽は、「音楽の道からそれて思弁的体験に入り込み、音楽を難解な、あるいは理解不能な言語」にしたにすぎない。それはいちおう情緒に訴えかけはするものの、曖昧で、混乱していて、不確かで、「情緒的な意味作用」はない。そんな風に考えるアンセルメにとって、バッハやベートーヴェンの音楽は「人間の基本的な情緒的・倫理的諸様相を直接表現する」ものであり、情熱と信頼の対象だった。
不滅の名演奏
録音量は多いが、特に名盤とされているのは、チャイコフスキーの『くるみ割り人形』(1959年録音)、リムスキー=コルサコフの『シェヘラザード』(1960年録音)、ドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』(1957年録音)、『夜想曲』(1957年録音)、ラヴェルの『道化師の朝の歌』(1960年録音)、『スペイン狂詩曲』(1957年録音)、ファリャの『三角帽子』(1961年録音)、交響的印象『スペインの夜の庭』(1960年ライヴ録音)、ストラヴィンスキーの『ペトルーシュカ』(1946年録音、1957年録音)、『プルチネルラ』(1955年録音)である。これらは永遠に聴き継がれるであろう不滅の名演奏だ。
アンセルメは神秘的な表現に秀でていた。『牧神の午後への前奏曲』ではテンポを細かく揺らし、楽器の音を(緻密に計算しながら)大胆に重ねることで、水彩的な色合いと匂やかな官能性を醸している。『三角帽子』、『ペトルーシュカ』、『シェヘラザード』などに顕著なのは、目立たせたい音をとにかく目立たせる傾向だ。木管が寂寥の極みのような音を出したかと思えば、金管が鋭く耳をつんざくような強音を炸裂させ、打楽器が大変な勢いで躍動する。楽器の音量の加減、緩急強弱の付け方が独特なのである。それは強靭な生命力がうねっている『三角帽子』を少し聴くだけでも体感できるだろう。
アンセルメと古典派
アンセルメの録音を聴いていて、時折気になるのは、歯切れの良いテンポと推進力が求められている時に楽器の動きがもたつき、タテの線が微妙に揃わないことである。そういう状態で古典派音楽を演奏すれば、普通は悲惨なことになる。しかし、ハイドンの交響曲第22番「哲学者」(1965年録音)や交響曲第90番(1965年録音)を聴くと、その問題が解消されている。アンサンブルは機械的でない程度に揃っており、上品で、格調高く、諧謔味もあり、極上の演奏としか言いようがない。
この事実を踏まえて考えると、タテの線が揃わない録音があるのは意図的なことなのかもしれない。先述したように、アンセルメが重んじたのは情緒的な意味作用であり、譜面通りの正確さを常に優先していたわけではなかった。作品によっては、無理にタテの線を揃える必要はないと判断していたのだろう。
ベートーヴェンの「英雄」(1960年録音)や「田園」(1959年録音)も名演だ。「田園」の第1楽章の150小節からのクレッシェンドの高揚感は、エフゲニー・ムラヴィンスキー盤に匹敵する。第2楽章でしなやかな弦の動きから影のように浮かび上がるファゴットの音色も、どこか素朴で鄙びていて、耳の奥にしみる。こういった演奏を聴くと、「アンセルメはロシアもの、フランスものだけではない」と言いたくなる。とはいえ、ベートーヴェンに対する思いが強すぎるのか、例えば「運命」(1958年録音)などの演奏は、緩急強弱の変化が多すぎ、まとまりが感じられない。もっとも、そこが面白いと言う人もいるだろうが。
その他の録音
第二次世界大戦後の作品では、ブリテンの『戦争レクイエム』(1967年ライヴ録音)が怒りと悲しみを生々しく伝えるような演奏で、心打たれる。ひたむきで衒いのない合唱が「リベラ・メ」で不気味な迫力を帯びるところは特に忘れがたい。ディティユーの交響曲第1番(1956年ライヴ録音)も名演で、弦楽器の深みのある音が神秘的な印象を残す。マルタンの「7つの管楽器、ティンパニ、打楽器と弦楽のための協奏曲」(1961年録音)は各楽器の音色が醸す明るい色彩感が魅力。金管とティンパニがアンセルメらしく強調されている。
戦後の作品ではないが、フォーレのレクイエム(1955年録音)はアマチュア合唱団を起用した録音で、その拙さがしばしば批判されている。たしかに地声が聞こえるぶっきらぼうな合唱で、良く言えば「素朴」、率直に言えば下手である(ジェラール・スゼーのソロは美しい)。アンセルメの立場なら一流の合唱団も使えたはずだが、プロの洗練された技術ではなく、アマチュアにしか出せない率直さのようなものを求めたのだろう。それは映画の世界でロベール・ブレッソンが素人俳優を好んだ心境と似ているのかもしれない。粗野で生々しい合唱と、神聖なソロが混在する不思議な魅力に満ちたレクイエムである。
【関連サイト】
クロード・ピゲ 『アンセルメとの対話』
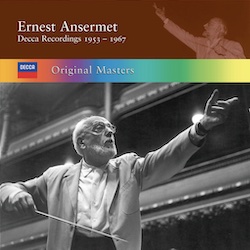
その演奏に耳を傾けていると、独特な響きやテンポに驚かされることはあるが、ほとんどの場合、彼が言うところの「不必要な感情の強調」は避けられ、節度が保たれている。解釈には苦悩の痕跡がない。旋律は当たり前のように彩度や透明度を上げ、迷いなく颯爽と進む。それは、言うまでもなく、万人に可能なわけではない。アンセルメ自身が「優れた感覚よりも正確さの方が大切だとは思えない」と述べているように、優れた感覚がなければ成立しないことである。彼には確かにそれがあった。
アンセルメの音楽観
「人間の情緒的主観性こそが、音楽の源である」ーー思想家でもあったアンセルメは、フッサールの現象主義を応用し、音楽というものを客観的な音響現象としてではなく、人間の意識の現象として捉えていた。その立場から、転調という現象も、「転調するのは人間の主観性であり、音ではない」とする。
アンセルメにとって大事なのは、美しい響きを出すことでも、単に譜面通りに演奏することでもなく、作品を正しく解釈し、聴き手に対して、情緒的な意味作用を及ぼすことだった。少々難解な話を私なりに噛み砕いて説明すると、その情緒的な意味をもたらす素となるのが、カダンス(アンセルメの造語)である。カダンスとは、楽曲を解釈することによって把握される根源的な感情・情緒の流れであり、人間の自然な認識作用と調和するものである。これがフレーズ、リズムを形成する土台となる。解釈以前の音楽テキストは、「音構造の抽象的な図式」にすぎない。演奏家は楽譜を研究をすることで、抽象的図式の奥にある感情・情緒(作曲家が音楽を書いた時の感情、作曲家に音楽を書かせたもの)を見出し、それと同化しなければならないのだ。
しかしながら、情緒的な意味作用が明らかに生じるのは、その作品が調性の法則によって支配されている(もしくは調性から完全には離れていない)場合のみである。調性から離れたセリー音楽は、「音楽の道からそれて思弁的体験に入り込み、音楽を難解な、あるいは理解不能な言語」にしたにすぎない。それはいちおう情緒に訴えかけはするものの、曖昧で、混乱していて、不確かで、「情緒的な意味作用」はない。そんな風に考えるアンセルメにとって、バッハやベートーヴェンの音楽は「人間の基本的な情緒的・倫理的諸様相を直接表現する」ものであり、情熱と信頼の対象だった。
不滅の名演奏
録音量は多いが、特に名盤とされているのは、チャイコフスキーの『くるみ割り人形』(1959年録音)、リムスキー=コルサコフの『シェヘラザード』(1960年録音)、ドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』(1957年録音)、『夜想曲』(1957年録音)、ラヴェルの『道化師の朝の歌』(1960年録音)、『スペイン狂詩曲』(1957年録音)、ファリャの『三角帽子』(1961年録音)、交響的印象『スペインの夜の庭』(1960年ライヴ録音)、ストラヴィンスキーの『ペトルーシュカ』(1946年録音、1957年録音)、『プルチネルラ』(1955年録音)である。これらは永遠に聴き継がれるであろう不滅の名演奏だ。
アンセルメは神秘的な表現に秀でていた。『牧神の午後への前奏曲』ではテンポを細かく揺らし、楽器の音を(緻密に計算しながら)大胆に重ねることで、水彩的な色合いと匂やかな官能性を醸している。『三角帽子』、『ペトルーシュカ』、『シェヘラザード』などに顕著なのは、目立たせたい音をとにかく目立たせる傾向だ。木管が寂寥の極みのような音を出したかと思えば、金管が鋭く耳をつんざくような強音を炸裂させ、打楽器が大変な勢いで躍動する。楽器の音量の加減、緩急強弱の付け方が独特なのである。それは強靭な生命力がうねっている『三角帽子』を少し聴くだけでも体感できるだろう。
アンセルメと古典派
アンセルメの録音を聴いていて、時折気になるのは、歯切れの良いテンポと推進力が求められている時に楽器の動きがもたつき、タテの線が微妙に揃わないことである。そういう状態で古典派音楽を演奏すれば、普通は悲惨なことになる。しかし、ハイドンの交響曲第22番「哲学者」(1965年録音)や交響曲第90番(1965年録音)を聴くと、その問題が解消されている。アンサンブルは機械的でない程度に揃っており、上品で、格調高く、諧謔味もあり、極上の演奏としか言いようがない。
この事実を踏まえて考えると、タテの線が揃わない録音があるのは意図的なことなのかもしれない。先述したように、アンセルメが重んじたのは情緒的な意味作用であり、譜面通りの正確さを常に優先していたわけではなかった。作品によっては、無理にタテの線を揃える必要はないと判断していたのだろう。
ベートーヴェンの「英雄」(1960年録音)や「田園」(1959年録音)も名演だ。「田園」の第1楽章の150小節からのクレッシェンドの高揚感は、エフゲニー・ムラヴィンスキー盤に匹敵する。第2楽章でしなやかな弦の動きから影のように浮かび上がるファゴットの音色も、どこか素朴で鄙びていて、耳の奥にしみる。こういった演奏を聴くと、「アンセルメはロシアもの、フランスものだけではない」と言いたくなる。とはいえ、ベートーヴェンに対する思いが強すぎるのか、例えば「運命」(1958年録音)などの演奏は、緩急強弱の変化が多すぎ、まとまりが感じられない。もっとも、そこが面白いと言う人もいるだろうが。
その他の録音
第二次世界大戦後の作品では、ブリテンの『戦争レクイエム』(1967年ライヴ録音)が怒りと悲しみを生々しく伝えるような演奏で、心打たれる。ひたむきで衒いのない合唱が「リベラ・メ」で不気味な迫力を帯びるところは特に忘れがたい。ディティユーの交響曲第1番(1956年ライヴ録音)も名演で、弦楽器の深みのある音が神秘的な印象を残す。マルタンの「7つの管楽器、ティンパニ、打楽器と弦楽のための協奏曲」(1961年録音)は各楽器の音色が醸す明るい色彩感が魅力。金管とティンパニがアンセルメらしく強調されている。
戦後の作品ではないが、フォーレのレクイエム(1955年録音)はアマチュア合唱団を起用した録音で、その拙さがしばしば批判されている。たしかに地声が聞こえるぶっきらぼうな合唱で、良く言えば「素朴」、率直に言えば下手である(ジェラール・スゼーのソロは美しい)。アンセルメの立場なら一流の合唱団も使えたはずだが、プロの洗練された技術ではなく、アマチュアにしか出せない率直さのようなものを求めたのだろう。それは映画の世界でロベール・ブレッソンが素人俳優を好んだ心境と似ているのかもしれない。粗野で生々しい合唱と、神聖なソロが混在する不思議な魅力に満ちたレクイエムである。
(阿部十三)
【関連サイト】
クロード・ピゲ 『アンセルメとの対話』
月別インデックス
- June 2024 [1]
- February 2024 [1]
- April 2023 [2]
- February 2023 [1]
- November 2022 [1]
- June 2022 [1]
- April 2022 [1]
- January 2022 [1]
- August 2021 [1]
- April 2021 [1]
- January 2021 [1]
- September 2020 [1]
- August 2020 [1]
- March 2020 [1]
- November 2019 [1]
- July 2019 [1]
- May 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [1]
- August 2018 [1]
- May 2018 [1]
- January 2018 [1]
- July 2017 [1]
- March 2017 [2]
- December 2016 [1]
- October 2016 [1]
- May 2016 [1]
- March 2016 [2]
- October 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- March 2015 [2]
- December 2014 [1]
- October 2014 [2]
- July 2014 [1]
- April 2014 [2]
- March 2014 [1]
- January 2014 [1]
- December 2013 [1]
- October 2013 [1]
- July 2013 [2]
- May 2013 [1]
- April 2013 [1]
- February 2013 [2]
- January 2013 [1]
- November 2012 [1]
- October 2012 [1]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- May 2012 [1]
- April 2012 [1]
- March 2012 [1]
- January 2012 [1]
- December 2011 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [2]
- June 2011 [3]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]