
古井由吉 おびただしい足音 その2
2024.03.03
空襲
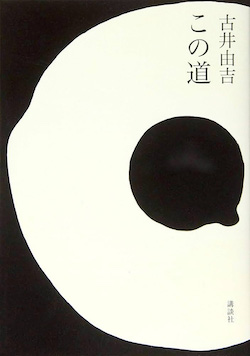
聴覚ばかりになっている状態での無音も、空襲の記憶と結びついている。防空壕でうずくまり、「頭上にたいして、耳ばかりになっていた」(「子供の行方」)状態がフラッシュバックするのだ。『聖耳』以前の『仮往生伝試文』にも、その当時のことが書かれている。爆音が遠ざかり、「頭上にぽっかりと、月ののぞく雲間のような静かさがひらいて、恐怖があらたまり、つぎの編隊が近づいてくる」という状況が繰り返されるうち、「静まって、何事も起らない」ことに、凄惨な予感を抱くようになる。
「......静まって、何事も起らない。何事も起らないことに、よけいにまた静まりかえる。その沈黙のはてしもなげに深まるその底から、赤熱した鉄の吐く炎のような、ゆらめきがほの見えるが、無事は刻々と続く......」
(『仮往生伝試文』)
後期作品では、現在の話をしている隙間から、過去の空襲の話が突然始まることが少なくない。そうすると梅崎春生の小説のように、現実と過去の境が曖昧になり、平穏な日常が当たり前のものでなく、ひどく危ういものに思えてくる。『この道』の「花の咲く頃には」に、「人の日常の平然さこそ驚嘆すべきもの、そしてあやういものだ」という言葉があるが、まさにそんな気分になる。
雨
空襲の話と並び、天気の話も多い。登山を好んでいたことも影響しているのだろう。とくに震災以後は、天気についての記述が目に見えて増えた。外が雨なのか、晴れなのか、低気圧がどうなっているのか、重要事であるかのように書かれている。古井は晩年のインタビュー(『群像』2019年4月号)で、聞き手に天気の描写が多いことを指摘され、「それこそ事件なんですよ」と答えている。人間は自分の意志や社会的影響から行動しているだけではなく、天気、自然現象からの影響も受けている、という考えが根底にあるようだ。
雨の描写も非常に多い。雨から連想されるのは必ずしも悪いことばかりではないが、古井作品ではどちらかというと生の儚さ、不穏さのメタファーとして扱われている。「道に鳴きつと」(『ゆらぐ玉の緒』収録)から引用する。
「強い低気圧の通る時には、人のからだは得体の知れぬ怯えに、あるいはその影に、心境によっては忍びこまれるものか。大雨の音に耳から心まで聾されて、気の振れかかる男もいるのかもしれない。雨の重さに支配されるもとで、至るところ、誰とは言わず女の恐怖と男の狂気とが互いに誘発して共振れを起こしかける。(中略)この年に続いた凶行がことごとく雨の中で起こったことのように思われる」
(「道に鳴きつと」)
雨音に耳から心まで聾される状態は、古井の中で死のイメージ、そして空襲体験につながる。『仮往生伝試文』の「四方に雨を見るやうに」では、「私」が雨の日に空襲があったことを語った後、話が現在に戻り、肉親の死病のことを語る。そして、高層ビルの最上階近くの窓から、「耳を聾する雨の中」を走る人を見て、「あの雨の下で今、自分の寿命を感じ取った人間は、何人ぐらいいるのだろうか」と想像する。上から降り注ぐ雨が、空襲の記憶を喚び覚ますのだろう。
日常
日常の危うさを示すメタファーとして古井作品によくみられるのは、獣、無音、歩行である。古井の言葉を借りると、獣は「滑らかに流れる大都会の群衆」や「滑らかな秩序」といったものに「つかのまでも狂いを来たさせることのできる」(「先導獣の話」)存在であり、初期作品に多用されたが、徐々に姿を消した。一方で、無音と歩行は残り続けた。
無音のときは、何が起こるかわからない。「明日の空」(『鐘の渡り』収録)に、「この日常こそ、無音そのものなのかもしれない」とあるが、これも日常は平和だという意味で使われているのではない。日常は何が起こるかわからず、いつ壊れてもおかしくない状態にあると言っているのだ。日常には確かに安息はある。しかし、「春の坂道」(『雨の裾』収録)に書かれているように、「安息と恐怖とは境を接している」。
歩行に関する記述は、初期の作品から多くみられる。代表的なのは「杳子」だろう。この作品では、心を病む杳子が一人でしっかりと歩けるかどうかが一つの大きなテーマとなっている。歩くという行為が頻出し、足音もおびただしい。足音は単なる音ではない。相手の存在を確認し、相手の心理状態を確認する拠り所である。まっすぐ歩けなかったり、足音を立てないで歩いたりするとき、杳子は失調に陥っている。
歩くという行為は当たり前のことではない。歩けなくなるという可能性を内在させている。「歩行が自然なとき、歩行を歩行とも感じない達者なときは、時間の流れが滑らかなんです」とは、前掲のインタビューでの言葉である。「ところが、だんだん歩行が不如意になってくると、過去が現在に淀んできて、現在が未来を先取りしてしまったりすることがある」ーー歩けなくなったとき、足音が絶えたとき、日常は綻び出し、時に崩れ去る。歩くという行為は、常にそういう危うさをはらんでいる。
古井作品は、年を経るほどに拵えたようなドラマ性が薄れ、形式が似てくる。晩年は同じようなことばかり書いていたのではないかと首を傾げる人がいるかもしれない。たしかに味わいは同じである。しかし、心に残るものはそれぞれ違うし、設定や描写の好みも分かれるだろう。理解できるかどうかは関係ない。関係なしに読むのがいい。ただ読むこと、ただ味わうことが感性の滋養となる文学もある。
(阿部十三)
【関連サイト】
古井由吉 自撰作品
古井由吉ロングインタビュー(TREE)
月別インデックス
- April 2025 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- March 2024 [1]
- February 2024 [1]
- November 2023 [1]
- August 2023 [7]
- March 2023 [1]
- February 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- August 2022 [1]
- May 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- September 2021 [2]
- August 2021 [1]
- July 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- January 2021 [1]
- December 2020 [1]
- October 2020 [1]
- August 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [2]
- March 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- November 2019 [2]
- October 2019 [1]
- September 2019 [1]
- August 2019 [1]
- July 2019 [1]
- June 2019 [1]
- May 2019 [1]
- March 2019 [1]
- January 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [2]
- May 2018 [1]
- February 2018 [1]
- December 2017 [2]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- July 2017 [3]
- June 2017 [1]
- May 2017 [1]
- April 2017 [1]
- February 2017 [1]
- January 2017 [1]
- December 2016 [2]
- October 2016 [1]
- September 2016 [1]
- August 2016 [1]
- July 2016 [1]
- June 2016 [2]
- April 2016 [2]
- March 2016 [1]
- January 2016 [1]
- December 2015 [2]
- November 2015 [1]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [2]
- April 2015 [1]
- March 2015 [1]
- February 2015 [1]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [2]
- August 2014 [1]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [1]
- February 2014 [1]
- January 2014 [3]
- December 2013 [3]
- November 2013 [2]
- October 2013 [1]
- September 2013 [2]
- August 2013 [1]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- April 2013 [3]
- March 2013 [2]
- February 2013 [2]
- January 2013 [1]
- December 2012 [3]
- November 2012 [2]
- October 2012 [3]
- September 2012 [3]
- August 2012 [3]
- July 2012 [3]
- June 2012 [3]
- May 2012 [2]
- April 2012 [3]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [4]
- December 2011 [5]
- November 2011 [4]
- October 2011 [5]
- September 2011 [4]
- August 2011 [4]
- July 2011 [5]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [4]
- February 2011 [5]