
ルイス・ブニュエル 〜不条理を生きる受難者たち〜
2016.02.17
序
ルイス・ブニュエルは、破壊者ないし挑発者というイメージの枠内で論じられることが多い映像作家である。その映画はしばしば常識を吹き飛ばす危険物とみなされ、反権威主義的な立場から賞賛される。しかし、そうやって形成されるブニュエル像に、私は物足りなさを覚える。シュルレアリスムの方法を応用して論理的整合性を破壊したとか、インモラルな描写をちりばめてキリスト教的権威を挑発したとか、そんなのは映画を半分まで観なくても言えることだ。私たちは、合理的な解釈を拒むように居並ぶ作品の内容に、もっと踏み込むべきである。
直進しない映画
 ブニュエルの映画は、目的に向かって直進しない。
ブニュエルの映画は、目的に向かって直進しない。
『昇天峠』(1952年)では、遺言状を作るために公証人を連れてきてほしいと病床の母親に頼まれた主人公が、バスに乗って目的地へと向かう。しかし、途中でパンクしたり、川にはまったり、運転手の母親の誕生会に参加させられたり、女に誘惑されたり、とさまざまな出来事に遭遇し、本来の目的から離れたところでエピソードが積み重なっていく。
なかなか目的地に辿り着けないという現象は、『幻影は市電に乗って旅をする』(1953年)でも起こる。会社に足蹴にされている運転手と車掌は、解体される寸前の市電133号に自己投影し、酔った勢いに任せて、真夜中に無断で133号を走らせる。朝になり、これはまずいと思った2人は、会社にバレる前に車庫に戻ろうとするが、途中で子供、検査官、資本家、厄介な老人などが乗ってきて、すんなり戻ることができない。
『皆殺しの天使』(1962年)はもっと極端である。この映画では、晩餐会にやって来たブルジョワたちがなぜか家に帰れなくなる。別に監禁されているわけではない。ただ客間から出ればいいだけなのに、誰も出ようとしないのだ。「どうして客間から出て帰ることができないのか」は分からない。理由が分からぬまま時間が過ぎる。そして何の説明もなく終わる。
後期の作品では、三大欲が目的として扱われる。『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』(1972年)では、ブルジョワたちが食事にありつけない状況が展開される。『自由の幻想』(1974年)では、永遠の眠りに就いたドンナ・エルヴィラの棺をこじあける冒頭のエピソードが示すように、眠りの妨げがモチーフのひとつになる。遺作『欲望のあいまいな対象』(1977年)では、初老の男やもめが「私は処女よ」と言う美女に夢中になるが、セックスすることができない。
これらの作品では「どんな目的が達せられるべきなのか」という方向性を示しておきながら、あらぬ角度へ脱線する有様が描かれている。平たく言えば、思い通りにならない夢の中の出来事のように、話が進むのだ。しかし、その直線的でない展開の仕方は、老練な手際で操られる不条理なイメージによってデフォルメされてはいるものの、現実とかけ離れているわけではない。私たちもまた映画の登場人物たちのように、ままならぬ世界にいて、常に欲求不満である。
さまざまな受難
ブニュエルは、登場人物たちを「受難者」に仕立てる傾向がある。これまでに挙げた作品は言うに及ばず、悪魔のようにみなされる『スサーナ』(1951年)の主人公ですら例外ではない。とある農場に身を寄せた脱獄者スサーナ(ロシーナ・キンタナ)は、自分の素性が使用人にバレた後も、そのことをネタに使用人から肉体関係を強要された後も、なお農場にとどまり農場主を誘惑しようとする。スサーナがどんなに恐るべき悪の権化であろうと、彼女に勝ち目はない。そして結果的に、嫉妬した農場主の妻に鞭で滅茶苦茶にぶたれた挙げ句、警察に連行される。その姿は憎むべき悪というよりも、ほとんど受難者のイメージを私に抱かせる。
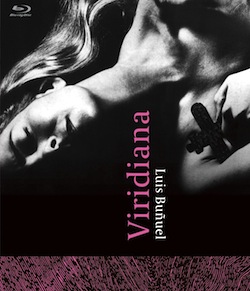 カトリック教会から非難された問題作『ビリディアナ』(1961年)の主人公は修道女ビリディアナ(シルビア・ピナル)。ひとことで言えば、信心深い女性が敗北する一見単純な話である。この映画は反宗教的な描写で物議を醸した。とくに注目を集めたのは、乞食たちが屋敷で好き勝手に飲み食いをしているとき、写真を撮ろうという話になってテーブルに並ぶカットだ。これがダ・ヴィンチの「最後の晩餐」そのままの構図になった。ただ、こういう箇所を取り上げて、ブニュエルを反キリスト的と評するのは安直である。
カトリック教会から非難された問題作『ビリディアナ』(1961年)の主人公は修道女ビリディアナ(シルビア・ピナル)。ひとことで言えば、信心深い女性が敗北する一見単純な話である。この映画は反宗教的な描写で物議を醸した。とくに注目を集めたのは、乞食たちが屋敷で好き勝手に飲み食いをしているとき、写真を撮ろうという話になってテーブルに並ぶカットだ。これがダ・ヴィンチの「最後の晩餐」そのままの構図になった。ただ、こういう箇所を取り上げて、ブニュエルを反キリスト的と評するのは安直である。
むしろブニュエルはキリスト教にとらわれていた。ただの無神論者なら、ここまで執拗に宗教的要素を自分の映画に持ち込んだりしない。後年のインタビューで、「キリストに関する強迫観念」が散見されることについて彼はこう語っている。
「もうそれは認めるよ。教養という点では、私はキリスト教徒だ。二千回はロサリオの祈りを捧げたと思う。何回、聖体拝領を受けたかわからない。それは私の人生に刻印されている。宗教的感情を理解できるし、もう一度、手にしたい幼年時代のある種の感動がある。五月の礼拝式、満開のアカシアの花々、光に囲まれた聖母像だ。これらは、心の奥深くにある、忘れがたい経験なのだ」
目につく場所に仕掛けられたインモラルな爆弾に惑わされるだけでは、作品解釈は成り立たない。『ビリディアナ』の設定で本来注目すべきところは、これが仕組まれた舞台の上で繰り広げられる受難者の物語だという点にある。誰がビリディアナの敗北を仕組んだのか。無論、彼女に拒絶されて自殺する叔父ドン・ハイメ(フェルナンド・レイ)である。その遺言により、息子ホルヘ(フランシスコ・ラバル)がやってきて家を継ぎ、ビリディアナを手に入れることで、父親は執念の賭けに勝ち、息子を通じて間接的に己の願望を成就させるのだ。最後にレコードをかけるところは象徴的である。父子の間に愛情はなくても、流れている音楽は異なっても、父が愛用したプレーヤーは息子に引き継がれている。私はこのエンディングを観ると、遺言を書く前にドン・ハイメが浮かべる笑みを思い出さずにいられない。
『ナサリン』(1959年)では青年神父が数々の試練に遭い、『砂漠のシモン』(1965年)では修行者が悪魔に幾度も誘惑される。ブニュエルが示す「受難」は、このように分かりやすい形をとるだけでなく、実に多様である。それらの受難の果てに「どういう奇跡が起こるのか」はほとんど問題とされない。受難の過程や性質といったものにブニュエルの関心は向けられている。直線的なストーリーを持つ『河と死』(1954年)は異色作だが、やはりこれも復讐に次ぐ復讐という因習的連鎖の中に身を置く登場人物の受難を描く点では変わらない。強い意志で復讐の連鎖を断ち切る爽やかなエンディングは、監督自身も認めているように無理がある。『昇天峠』『幻影は〜』の結末も然り。「私は欲求不満が好きなのだ」と語るブニュエルにとって、満たされたハッピーエンドという奇跡は重要ではないのである。
幼き日にキリスト教から得た感動を、ブニュエルが再び手にすることはなかった。彼は現実に広まっているキリスト教に権威性や合理性と結びつくものを認め、それらを拒否し、攻撃する立場をとった。このことは背信性よりも、彼のねじれた厳格さを示しているように思われる。その厳格さは、「受難」と「奇跡」の間に安易な合理的関連性を認めない態度にあらわれている。ブニュエルが無神論者だと標榜するのを額面通りに受けとるべきではない。心の奥深くにある「光に囲まれた聖母像」は捨てられていないのである。
犯罪的人間、そして音楽のこと
 私が好んでいるのはメキシコ時代の作品だが、この時期のブニュエルの魅力的なミューズといえば、前半はリリア・プラド、後半はシルビア・ピナルである。そこにもう一人、重要な作品に出演した女優の名前を加えたい。『アルチバルド・デラクルスの犯罪的人生』(1955年)の美女ミロスラヴァだ。
私が好んでいるのはメキシコ時代の作品だが、この時期のブニュエルの魅力的なミューズといえば、前半はリリア・プラド、後半はシルビア・ピナルである。そこにもう一人、重要な作品に出演した女優の名前を加えたい。『アルチバルド・デラクルスの犯罪的人生』(1955年)の美女ミロスラヴァだ。
これは殺人願望を持つアルチバルド(エルネスト・アロンソ)の半生を描いた作品。自分が殺そうと思った女性たちが、自ら手を下す(目的を達する)前に、次々と死を迎えてしまう話である。この作品を通じて、ブニュエルは「殺人のイメージを抱くことは犯罪なのか」と問う。「情欲を抱いて女を見る者は、心の中ですでに姦淫をしたのである」(マタイによる福音書)の殺人バージョンだ。殺人願望で頭がパンク寸前のアルチバルドは、「自分が女たちを殺したのだ」と言うが、警察からは相手にされない。これに沿って審判を下すなら、『ビリディアナ』も含めてブニュエルが抱くイメージも無罪である。
『アルチバルド〜』には愛の地獄で苦しむ2人の女が登場し、死を迎えるが、ミロスラヴァが演じたラビニアだけは死を免れる。しかし、その後ミロスラヴァが自殺し、映画外で皮肉な結末を付けてしまった。そんなこともあって呪われた作品のように言う人もいるが、映画自体は面白く、「欲求不満」や「イメージの有罪性」など複数のモチーフを渋滞感なく、分かりやすく編み込んでいる。女性の脚に対するブニュエルおなじみのフェティシズムも露骨に出ているし、もうひとつ、強迫観念の問題も扱われている。
アルチバルドはオルゴールの旋律にとらわれている。子供の頃、オルゴールを鳴らした途端、口うるさい女家庭教師が流れ弾に当たって(美脚を見せた状態で)死んだことが忘れられないのだ。このときから彼は音楽の魔力を信じるようになった。それが大人になると、自分の頭の中にオルゴールの旋律が流れる=殺人を犯したくなるという心理にまで発展する。これをブニュエルは「聴覚による強迫観念」と呼んだ。
音楽が人間に及ぼす影響は、ブニュエルが大きな関心を寄せたテーマだったのではないかと思われる。このテーマは、意味不明とされる『皆殺しの天使』からも抽出できる。身も心も衰弱したブルジョワたちは、いかにして状況を打開するのか。それは部屋から出られなくなった問題の日の行動を、皆でなぞることである。では、その「再生」はどこから行われるのか。パラディージのソナタである。ピアノが奏でられるところから彼らは行動を「再生」し、美しい音楽を二度聴くことで、呪縛を解くのだ。あえてパラディージの曲を使ったのは、その名前が「天国」に似たスペルだからだろう。それは偽りの天国といった意味を持ち、映画のタイトルの中に天使がいたことを私たちに思い出させる。
ブニュエルの映画は、想像力や理解力を刺激するイメージにあふれている。彼は「精神分析医によると、私は精神分析不可能なんだそうだ」と言って解釈の不可能性を示唆したが、その映画がもたらす刺激は、作家論や作品論を語る欲求を否応なしに起こさせる。ブニュエルはそこまで見越した上で、私たちにゴールのない解釈という受難を仕掛けたのだろう。しかし、それはまたなんと愉悦に満ちた受難であることか。
[引用文献]
トマス・ペレス・トレント、ホセ・デ・ラ・コリーナ『INTERVIEW ルイス・ブニュエル 公開禁止令』(フィルムアート社 1990年4月)
【関連サイト】
Luis Buñuel
ルイス・ブニュエルは、破壊者ないし挑発者というイメージの枠内で論じられることが多い映像作家である。その映画はしばしば常識を吹き飛ばす危険物とみなされ、反権威主義的な立場から賞賛される。しかし、そうやって形成されるブニュエル像に、私は物足りなさを覚える。シュルレアリスムの方法を応用して論理的整合性を破壊したとか、インモラルな描写をちりばめてキリスト教的権威を挑発したとか、そんなのは映画を半分まで観なくても言えることだ。私たちは、合理的な解釈を拒むように居並ぶ作品の内容に、もっと踏み込むべきである。
直進しない映画

『昇天峠』(1952年)では、遺言状を作るために公証人を連れてきてほしいと病床の母親に頼まれた主人公が、バスに乗って目的地へと向かう。しかし、途中でパンクしたり、川にはまったり、運転手の母親の誕生会に参加させられたり、女に誘惑されたり、とさまざまな出来事に遭遇し、本来の目的から離れたところでエピソードが積み重なっていく。
なかなか目的地に辿り着けないという現象は、『幻影は市電に乗って旅をする』(1953年)でも起こる。会社に足蹴にされている運転手と車掌は、解体される寸前の市電133号に自己投影し、酔った勢いに任せて、真夜中に無断で133号を走らせる。朝になり、これはまずいと思った2人は、会社にバレる前に車庫に戻ろうとするが、途中で子供、検査官、資本家、厄介な老人などが乗ってきて、すんなり戻ることができない。
『皆殺しの天使』(1962年)はもっと極端である。この映画では、晩餐会にやって来たブルジョワたちがなぜか家に帰れなくなる。別に監禁されているわけではない。ただ客間から出ればいいだけなのに、誰も出ようとしないのだ。「どうして客間から出て帰ることができないのか」は分からない。理由が分からぬまま時間が過ぎる。そして何の説明もなく終わる。
後期の作品では、三大欲が目的として扱われる。『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』(1972年)では、ブルジョワたちが食事にありつけない状況が展開される。『自由の幻想』(1974年)では、永遠の眠りに就いたドンナ・エルヴィラの棺をこじあける冒頭のエピソードが示すように、眠りの妨げがモチーフのひとつになる。遺作『欲望のあいまいな対象』(1977年)では、初老の男やもめが「私は処女よ」と言う美女に夢中になるが、セックスすることができない。
これらの作品では「どんな目的が達せられるべきなのか」という方向性を示しておきながら、あらぬ角度へ脱線する有様が描かれている。平たく言えば、思い通りにならない夢の中の出来事のように、話が進むのだ。しかし、その直線的でない展開の仕方は、老練な手際で操られる不条理なイメージによってデフォルメされてはいるものの、現実とかけ離れているわけではない。私たちもまた映画の登場人物たちのように、ままならぬ世界にいて、常に欲求不満である。
さまざまな受難
ブニュエルは、登場人物たちを「受難者」に仕立てる傾向がある。これまでに挙げた作品は言うに及ばず、悪魔のようにみなされる『スサーナ』(1951年)の主人公ですら例外ではない。とある農場に身を寄せた脱獄者スサーナ(ロシーナ・キンタナ)は、自分の素性が使用人にバレた後も、そのことをネタに使用人から肉体関係を強要された後も、なお農場にとどまり農場主を誘惑しようとする。スサーナがどんなに恐るべき悪の権化であろうと、彼女に勝ち目はない。そして結果的に、嫉妬した農場主の妻に鞭で滅茶苦茶にぶたれた挙げ句、警察に連行される。その姿は憎むべき悪というよりも、ほとんど受難者のイメージを私に抱かせる。
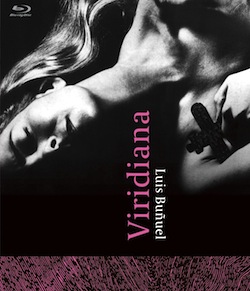
むしろブニュエルはキリスト教にとらわれていた。ただの無神論者なら、ここまで執拗に宗教的要素を自分の映画に持ち込んだりしない。後年のインタビューで、「キリストに関する強迫観念」が散見されることについて彼はこう語っている。
「もうそれは認めるよ。教養という点では、私はキリスト教徒だ。二千回はロサリオの祈りを捧げたと思う。何回、聖体拝領を受けたかわからない。それは私の人生に刻印されている。宗教的感情を理解できるし、もう一度、手にしたい幼年時代のある種の感動がある。五月の礼拝式、満開のアカシアの花々、光に囲まれた聖母像だ。これらは、心の奥深くにある、忘れがたい経験なのだ」
(『INTERVIEW ルイス・ブニュエル 公開禁止令』 岩崎清訳)
目につく場所に仕掛けられたインモラルな爆弾に惑わされるだけでは、作品解釈は成り立たない。『ビリディアナ』の設定で本来注目すべきところは、これが仕組まれた舞台の上で繰り広げられる受難者の物語だという点にある。誰がビリディアナの敗北を仕組んだのか。無論、彼女に拒絶されて自殺する叔父ドン・ハイメ(フェルナンド・レイ)である。その遺言により、息子ホルヘ(フランシスコ・ラバル)がやってきて家を継ぎ、ビリディアナを手に入れることで、父親は執念の賭けに勝ち、息子を通じて間接的に己の願望を成就させるのだ。最後にレコードをかけるところは象徴的である。父子の間に愛情はなくても、流れている音楽は異なっても、父が愛用したプレーヤーは息子に引き継がれている。私はこのエンディングを観ると、遺言を書く前にドン・ハイメが浮かべる笑みを思い出さずにいられない。
『ナサリン』(1959年)では青年神父が数々の試練に遭い、『砂漠のシモン』(1965年)では修行者が悪魔に幾度も誘惑される。ブニュエルが示す「受難」は、このように分かりやすい形をとるだけでなく、実に多様である。それらの受難の果てに「どういう奇跡が起こるのか」はほとんど問題とされない。受難の過程や性質といったものにブニュエルの関心は向けられている。直線的なストーリーを持つ『河と死』(1954年)は異色作だが、やはりこれも復讐に次ぐ復讐という因習的連鎖の中に身を置く登場人物の受難を描く点では変わらない。強い意志で復讐の連鎖を断ち切る爽やかなエンディングは、監督自身も認めているように無理がある。『昇天峠』『幻影は〜』の結末も然り。「私は欲求不満が好きなのだ」と語るブニュエルにとって、満たされたハッピーエンドという奇跡は重要ではないのである。
幼き日にキリスト教から得た感動を、ブニュエルが再び手にすることはなかった。彼は現実に広まっているキリスト教に権威性や合理性と結びつくものを認め、それらを拒否し、攻撃する立場をとった。このことは背信性よりも、彼のねじれた厳格さを示しているように思われる。その厳格さは、「受難」と「奇跡」の間に安易な合理的関連性を認めない態度にあらわれている。ブニュエルが無神論者だと標榜するのを額面通りに受けとるべきではない。心の奥深くにある「光に囲まれた聖母像」は捨てられていないのである。
犯罪的人間、そして音楽のこと

これは殺人願望を持つアルチバルド(エルネスト・アロンソ)の半生を描いた作品。自分が殺そうと思った女性たちが、自ら手を下す(目的を達する)前に、次々と死を迎えてしまう話である。この作品を通じて、ブニュエルは「殺人のイメージを抱くことは犯罪なのか」と問う。「情欲を抱いて女を見る者は、心の中ですでに姦淫をしたのである」(マタイによる福音書)の殺人バージョンだ。殺人願望で頭がパンク寸前のアルチバルドは、「自分が女たちを殺したのだ」と言うが、警察からは相手にされない。これに沿って審判を下すなら、『ビリディアナ』も含めてブニュエルが抱くイメージも無罪である。
『アルチバルド〜』には愛の地獄で苦しむ2人の女が登場し、死を迎えるが、ミロスラヴァが演じたラビニアだけは死を免れる。しかし、その後ミロスラヴァが自殺し、映画外で皮肉な結末を付けてしまった。そんなこともあって呪われた作品のように言う人もいるが、映画自体は面白く、「欲求不満」や「イメージの有罪性」など複数のモチーフを渋滞感なく、分かりやすく編み込んでいる。女性の脚に対するブニュエルおなじみのフェティシズムも露骨に出ているし、もうひとつ、強迫観念の問題も扱われている。
アルチバルドはオルゴールの旋律にとらわれている。子供の頃、オルゴールを鳴らした途端、口うるさい女家庭教師が流れ弾に当たって(美脚を見せた状態で)死んだことが忘れられないのだ。このときから彼は音楽の魔力を信じるようになった。それが大人になると、自分の頭の中にオルゴールの旋律が流れる=殺人を犯したくなるという心理にまで発展する。これをブニュエルは「聴覚による強迫観念」と呼んだ。
音楽が人間に及ぼす影響は、ブニュエルが大きな関心を寄せたテーマだったのではないかと思われる。このテーマは、意味不明とされる『皆殺しの天使』からも抽出できる。身も心も衰弱したブルジョワたちは、いかにして状況を打開するのか。それは部屋から出られなくなった問題の日の行動を、皆でなぞることである。では、その「再生」はどこから行われるのか。パラディージのソナタである。ピアノが奏でられるところから彼らは行動を「再生」し、美しい音楽を二度聴くことで、呪縛を解くのだ。あえてパラディージの曲を使ったのは、その名前が「天国」に似たスペルだからだろう。それは偽りの天国といった意味を持ち、映画のタイトルの中に天使がいたことを私たちに思い出させる。
ブニュエルの映画は、想像力や理解力を刺激するイメージにあふれている。彼は「精神分析医によると、私は精神分析不可能なんだそうだ」と言って解釈の不可能性を示唆したが、その映画がもたらす刺激は、作家論や作品論を語る欲求を否応なしに起こさせる。ブニュエルはそこまで見越した上で、私たちにゴールのない解釈という受難を仕掛けたのだろう。しかし、それはまたなんと愉悦に満ちた受難であることか。
(阿部十三)
[引用文献]
トマス・ペレス・トレント、ホセ・デ・ラ・コリーナ『INTERVIEW ルイス・ブニュエル 公開禁止令』(フィルムアート社 1990年4月)
【関連サイト】
Luis Buñuel
[ルイス・ブニュエル略歴]
1900年2月22日、スペインのアラゴン州生まれ。マドリード大に進学した後、フリッツ・ラング監督の『死滅の谷』を観て映画監督を志す。1929年、パリでサルバドール・ダリと共同で脚本を執筆し、短編映画『アンダルシアの犬』でデビュー。翌年、冒涜的な『黄金時代』を撮ったことで猛烈な批判を浴びる。渡米して職を得るが生活は安定せず、1946年にメキシコへ。同国で『忘れられた人々』(1950年)を撮り、カンヌ映画祭監督賞を受賞。次々と傑作を発表した後、祖国スペインで撮った『ビリディアナ』(1961年)によりカンヌ映画祭パルム・ドールを受賞。大スキャンダルを巻き起こす。活動拠点をフランスに移してからも、カトリーヌ・ドヌーヴを起用した『昼顔』(1967年)と『哀しみのトリスターナ』(1970年)で成功し、『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』(1972年)でアカデミー外国語映画賞を受賞。老いを感じさせない作風で問題作を撮り続けた。1983年7月29日、メキシコ市で死去。
1900年2月22日、スペインのアラゴン州生まれ。マドリード大に進学した後、フリッツ・ラング監督の『死滅の谷』を観て映画監督を志す。1929年、パリでサルバドール・ダリと共同で脚本を執筆し、短編映画『アンダルシアの犬』でデビュー。翌年、冒涜的な『黄金時代』を撮ったことで猛烈な批判を浴びる。渡米して職を得るが生活は安定せず、1946年にメキシコへ。同国で『忘れられた人々』(1950年)を撮り、カンヌ映画祭監督賞を受賞。次々と傑作を発表した後、祖国スペインで撮った『ビリディアナ』(1961年)によりカンヌ映画祭パルム・ドールを受賞。大スキャンダルを巻き起こす。活動拠点をフランスに移してからも、カトリーヌ・ドヌーヴを起用した『昼顔』(1967年)と『哀しみのトリスターナ』(1970年)で成功し、『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』(1972年)でアカデミー外国語映画賞を受賞。老いを感じさせない作風で問題作を撮り続けた。1983年7月29日、メキシコ市で死去。
[主な監督作品]
1929年『アンダルシアの犬』/1930年『黄金時代』/1947年『グラン・カジノ』/1949年『のんき大将』/1950年『忘れられた人々』/1951年『スサーナ』『賭博師の娘』/1952年『昇天峠』『愛なき女』/1953年『乱暴者』『エル』『幻影は市電に乗って旅をする』/1954年『嵐が丘』『ロビンソン漂流記』/1955年『河と死』『アルチバルド・デラクルスの犯罪的人生』/1956年『それを暁と呼ぶ』/1959年『ナサリン』/1961年『ビリディアナ』/1962年『皆殺しの天使』/1964年『小間使の日記』/1965年『砂漠のシモン』/1967年『昼顔』/1969年『銀河』/1970年『哀しみのトリスターナ』/1972年『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』/1974年『自由の幻想』/1977年『欲望のあいまいな対象』
1929年『アンダルシアの犬』/1930年『黄金時代』/1947年『グラン・カジノ』/1949年『のんき大将』/1950年『忘れられた人々』/1951年『スサーナ』『賭博師の娘』/1952年『昇天峠』『愛なき女』/1953年『乱暴者』『エル』『幻影は市電に乗って旅をする』/1954年『嵐が丘』『ロビンソン漂流記』/1955年『河と死』『アルチバルド・デラクルスの犯罪的人生』/1956年『それを暁と呼ぶ』/1959年『ナサリン』/1961年『ビリディアナ』/1962年『皆殺しの天使』/1964年『小間使の日記』/1965年『砂漠のシモン』/1967年『昼顔』/1969年『銀河』/1970年『哀しみのトリスターナ』/1972年『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』/1974年『自由の幻想』/1977年『欲望のあいまいな対象』
月別インデックス
- May 2024 [1]
- January 2023 [1]
- November 2021 [1]
- April 2021 [1]
- September 2020 [2]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- January 2020 [1]
- July 2019 [1]
- March 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [3]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- October 2017 [2]
- September 2017 [1]
- June 2017 [2]
- March 2017 [2]
- November 2016 [1]
- August 2016 [1]
- July 2016 [2]
- February 2016 [1]
- October 2015 [1]
- August 2015 [1]
- June 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [1]
- January 2015 [2]
- September 2014 [1]
- July 2014 [2]
- May 2014 [1]
- March 2014 [1]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- September 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [1]
- May 2013 [1]
- February 2013 [1]
- December 2012 [2]
- October 2012 [2]
- August 2012 [2]
- June 2012 [1]
- April 2012 [2]
- March 2012 [1]
- February 2012 [1]
- January 2012 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]