
マルセル・カルネ 〜ドラマを省略しない監督〜
2016.07.28
フランス精神よりも男女の愛
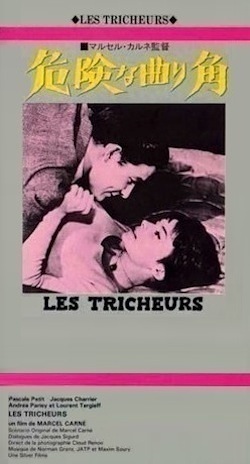 『危険な曲り角』(1958年)の中に、若者たちがシネマテークでルドルフ・ヴァレンティノの『血と砂』(1922年)を観に行くシーンがある。彼らはポスターを観て、「なぜこんな男がモテたのか」「まるでタンゴダンサーだ」「でもジェームズ・ディーンだって古くなるだろ」「そんなことはない」といった会話を交わし、ヴァレンティノのドラマティックなキスシーンを観て笑う。マルセル・カルネは当時の若者の生態を描く上で、このシーンを挿入せずにいられなかった。自分のことを否定する若い世代も、次の世代も、いずれは古くなる。そして大時代的と言われていたものが、かえって新鮮に見えたりする。カルネがそこまで見越していたかどうかは分からないが、本格的にヌーヴェルヴァーグの時代に入って活躍の場が減る前に、古い映画を観て笑う若者たちを身の程知らずの存在として映したのは、彼なりの皮肉であり抵抗であったに違いない。
『危険な曲り角』(1958年)の中に、若者たちがシネマテークでルドルフ・ヴァレンティノの『血と砂』(1922年)を観に行くシーンがある。彼らはポスターを観て、「なぜこんな男がモテたのか」「まるでタンゴダンサーだ」「でもジェームズ・ディーンだって古くなるだろ」「そんなことはない」といった会話を交わし、ヴァレンティノのドラマティックなキスシーンを観て笑う。マルセル・カルネは当時の若者の生態を描く上で、このシーンを挿入せずにいられなかった。自分のことを否定する若い世代も、次の世代も、いずれは古くなる。そして大時代的と言われていたものが、かえって新鮮に見えたりする。カルネがそこまで見越していたかどうかは分からないが、本格的にヌーヴェルヴァーグの時代に入って活躍の場が減る前に、古い映画を観て笑う若者たちを身の程知らずの存在として映したのは、彼なりの皮肉であり抵抗であったに違いない。
カルネといえば戦中に撮った『天井桟敷の人々』(1945年)が最も有名だ。詩的リアリズムの傑作と称されるこの作品は、同時代人に称賛され、不屈のフランス精神のアイコンとして扱われた。しかしながら、カルネの作家性はフランス精神といった大仰なものを表現するよりも、むしろ男女の愛を描くことに向いている。さらに言えば、彼らの愛はロマンティックである代わりにどこか閉鎖的かつ厭世的な雰囲気を帯びている。『天井桟敷の人々』も決して例外ではない。この映画には多くの登場人物が出てくるし、皆自分たちのドラマを生きながらその生命を輝かせているが、物語の中心にあるのは、ガランス(アルレッティ)とバティスト(ジャン=ルイ・バロー)の愛である。それは、肉体的に他者を受け入れることはあっても、精神的に他者を介入させることのない閉鎖的な愛なのだ。
込み入ったドラマ
夢の世界と惨めな現実を対比させた厭世観の濃い『愛人ジュリエット』(1951年)も、重い不倫劇でサスペンスとしても秀逸な『嘆きのテレーズ』(1953年)もそうだが、込み入った恋愛ドラマ、暗い人間ドラマを丁寧なタッチで撮るところにカルネの本領がある。彼は人物同士のややこしい心理の交錯を凝視し、細かい機微までスクリーンにきちんと描き込みたがる人なのだ。
きちんと描き込むとは、つまり省略法を濫用しないという意味である。その分、テンポの良さは犠牲になるが、観る者の想像力に委ねるつなぎ合わせがなくなることで、登場人物の性格や心理や生活感がリアルなものとして重みを持つ。『マンハッタンの哀愁』(1965年)のホテルのシーンはその好例だろう。若い男に妻を取られたフランス人俳優フランソワ(モーリス・ロネ)は、母国を捨ててニューヨークに移住し、そこで倦怠感漂う外交官夫人ケイ(アニー・ジラルド)と出会う。孤独な2人はなんとなく身を寄せ合い、夜のニューヨークをさまよい歩き、ホテルへ行こうという流れになる。ここで、普通ならば込み入った場面を割愛し、事が済んだ後のベッドの2人が映されるところだが、カルネの場合は異なり、安宿のフロントとのやりとりから、部屋に入った2人の気怠そうな動きまで、セックスシーン以外の何から何まで撮ってみせる。同じようにニューヨークを舞台にした(かつジャズを多用した)映画でも、ジャン=ピエール・メルヴィルの『マンハッタンの二人の男』(1959年)とは対照的な作風だ。
『危険な曲り角』は先にもふれたように若者の生態を描いた作品で、エリートコースを進む学生ボブ(ジャック・シャリエ)と奔放な生活を送る不良ミック(パスカル・プティ)の素直になれない恋愛模様が展開される。ここにも省略してよいはずなのに省略されない場面がたくさん出てくる。中でも大きな意味を持つのは、終盤、車を暴走させたミックが事故に遭った後、10分ほど続く病院のシーンだ。そこでカルネは、互いを深く傷つけ合ったことを後悔するボブ、そのボブを慰めるミックの兄(ローラン・ルサッフル/カルネ作品の常連)の心理に吸着する。ミックの怪我が治ったら一緒に海へ行き、愛を確かめ合いたいと言うボブ。その夢はかなわず、ミックは死ぬ。ボブはミックのことを一目見たいと病室へ。しかし足が前に進まない。ミックの兄は複雑な表情でボブに近付き、「君だけのせいじゃない」と言う。映画全体を必要以上に重くするシーンである。だが、カルネは凝視することを止めない。彼の姿勢は、むしろこういう込み入ったところを省くのは作家として無責任だと主張しているかのようでもある。
若者たちを描くからといって特別洒落た演出をせず(強いて言えば、主人公の名前がアメリカ風という程度)、どっしりとした土台の上でリアルな人間ドラマをみせているところもカルネらしい。そこから浮かび上がってくるのは、古い価値観(愛)を否定し反抗しながらも、結局それを求めずにいられない若者の姿である。そしていざ愛を失った後に、激しく後悔するのだ。公開当時は、テーマが説教臭いと批判されたが、「今時の若者は駄目だ」の一点張りではないし、秩序を押しつける大人に対するささやかな批判精神もないわけではない。何より、若者たちにとって古い権威の象徴のようなカルネ世代の旧式の演出により、20歳のパスカル・プティの魅力がたっぷり引き出されているところは注目に値する。「人を愛するなんて堕落よ、個の否定だもの」とうそぶき、多くの男たちと関係を結びながら、ボブとの間に真実の愛を見出して悩むミックが、悪い仲間にそそのかされて浮気することで同情の余地をなくしているにもかかわらず、観る者に憐れみを催させるほど美しく描かれているのだ。
【関連サイト】
マルセル・カルネ 〜ドラマを省略しない監督〜 [続き]
今も生きている『天井桟敷の人々』
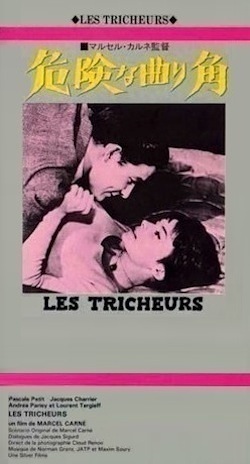
カルネといえば戦中に撮った『天井桟敷の人々』(1945年)が最も有名だ。詩的リアリズムの傑作と称されるこの作品は、同時代人に称賛され、不屈のフランス精神のアイコンとして扱われた。しかしながら、カルネの作家性はフランス精神といった大仰なものを表現するよりも、むしろ男女の愛を描くことに向いている。さらに言えば、彼らの愛はロマンティックである代わりにどこか閉鎖的かつ厭世的な雰囲気を帯びている。『天井桟敷の人々』も決して例外ではない。この映画には多くの登場人物が出てくるし、皆自分たちのドラマを生きながらその生命を輝かせているが、物語の中心にあるのは、ガランス(アルレッティ)とバティスト(ジャン=ルイ・バロー)の愛である。それは、肉体的に他者を受け入れることはあっても、精神的に他者を介入させることのない閉鎖的な愛なのだ。
込み入ったドラマ
夢の世界と惨めな現実を対比させた厭世観の濃い『愛人ジュリエット』(1951年)も、重い不倫劇でサスペンスとしても秀逸な『嘆きのテレーズ』(1953年)もそうだが、込み入った恋愛ドラマ、暗い人間ドラマを丁寧なタッチで撮るところにカルネの本領がある。彼は人物同士のややこしい心理の交錯を凝視し、細かい機微までスクリーンにきちんと描き込みたがる人なのだ。
きちんと描き込むとは、つまり省略法を濫用しないという意味である。その分、テンポの良さは犠牲になるが、観る者の想像力に委ねるつなぎ合わせがなくなることで、登場人物の性格や心理や生活感がリアルなものとして重みを持つ。『マンハッタンの哀愁』(1965年)のホテルのシーンはその好例だろう。若い男に妻を取られたフランス人俳優フランソワ(モーリス・ロネ)は、母国を捨ててニューヨークに移住し、そこで倦怠感漂う外交官夫人ケイ(アニー・ジラルド)と出会う。孤独な2人はなんとなく身を寄せ合い、夜のニューヨークをさまよい歩き、ホテルへ行こうという流れになる。ここで、普通ならば込み入った場面を割愛し、事が済んだ後のベッドの2人が映されるところだが、カルネの場合は異なり、安宿のフロントとのやりとりから、部屋に入った2人の気怠そうな動きまで、セックスシーン以外の何から何まで撮ってみせる。同じようにニューヨークを舞台にした(かつジャズを多用した)映画でも、ジャン=ピエール・メルヴィルの『マンハッタンの二人の男』(1959年)とは対照的な作風だ。
『危険な曲り角』は先にもふれたように若者の生態を描いた作品で、エリートコースを進む学生ボブ(ジャック・シャリエ)と奔放な生活を送る不良ミック(パスカル・プティ)の素直になれない恋愛模様が展開される。ここにも省略してよいはずなのに省略されない場面がたくさん出てくる。中でも大きな意味を持つのは、終盤、車を暴走させたミックが事故に遭った後、10分ほど続く病院のシーンだ。そこでカルネは、互いを深く傷つけ合ったことを後悔するボブ、そのボブを慰めるミックの兄(ローラン・ルサッフル/カルネ作品の常連)の心理に吸着する。ミックの怪我が治ったら一緒に海へ行き、愛を確かめ合いたいと言うボブ。その夢はかなわず、ミックは死ぬ。ボブはミックのことを一目見たいと病室へ。しかし足が前に進まない。ミックの兄は複雑な表情でボブに近付き、「君だけのせいじゃない」と言う。映画全体を必要以上に重くするシーンである。だが、カルネは凝視することを止めない。彼の姿勢は、むしろこういう込み入ったところを省くのは作家として無責任だと主張しているかのようでもある。
若者たちを描くからといって特別洒落た演出をせず(強いて言えば、主人公の名前がアメリカ風という程度)、どっしりとした土台の上でリアルな人間ドラマをみせているところもカルネらしい。そこから浮かび上がってくるのは、古い価値観(愛)を否定し反抗しながらも、結局それを求めずにいられない若者の姿である。そしていざ愛を失った後に、激しく後悔するのだ。公開当時は、テーマが説教臭いと批判されたが、「今時の若者は駄目だ」の一点張りではないし、秩序を押しつける大人に対するささやかな批判精神もないわけではない。何より、若者たちにとって古い権威の象徴のようなカルネ世代の旧式の演出により、20歳のパスカル・プティの魅力がたっぷり引き出されているところは注目に値する。「人を愛するなんて堕落よ、個の否定だもの」とうそぶき、多くの男たちと関係を結びながら、ボブとの間に真実の愛を見出して悩むミックが、悪い仲間にそそのかされて浮気することで同情の余地をなくしているにもかかわらず、観る者に憐れみを催させるほど美しく描かれているのだ。
【関連サイト】
マルセル・カルネ 〜ドラマを省略しない監督〜 [続き]
今も生きている『天井桟敷の人々』
月別インデックス
- May 2024 [1]
- January 2023 [1]
- November 2021 [1]
- April 2021 [1]
- September 2020 [2]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- January 2020 [1]
- July 2019 [1]
- March 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [3]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- October 2017 [2]
- September 2017 [1]
- June 2017 [2]
- March 2017 [2]
- November 2016 [1]
- August 2016 [1]
- July 2016 [2]
- February 2016 [1]
- October 2015 [1]
- August 2015 [1]
- June 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [1]
- January 2015 [2]
- September 2014 [1]
- July 2014 [2]
- May 2014 [1]
- March 2014 [1]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- September 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [1]
- May 2013 [1]
- February 2013 [1]
- December 2012 [2]
- October 2012 [2]
- August 2012 [2]
- June 2012 [1]
- April 2012 [2]
- March 2012 [1]
- February 2012 [1]
- January 2012 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]