
アルフレッド・ヒッチコック 〜『サイコ』について〜
2018.04.02
新たな挑戦
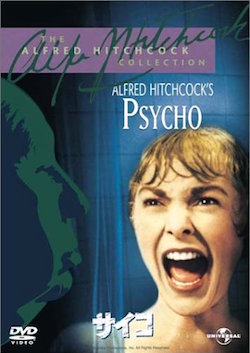 おそらく映画史において、アルフレッド・ヒッチコック監督の『サイコ』ほど多くの人々によって論じられた作品はほとんど存在しないだろう。この映画は、箝口令が敷かれる中で撮られ、試写会もなく公開された。そして批評家たちの不興を買いつつも、徹底した秘密主義が奏功して大ヒットし、大衆に支持された。その大衆によって、批評家以上の熱量で語られ、分析されたのである。
おそらく映画史において、アルフレッド・ヒッチコック監督の『サイコ』ほど多くの人々によって論じられた作品はほとんど存在しないだろう。この映画は、箝口令が敷かれる中で撮られ、試写会もなく公開された。そして批評家たちの不興を買いつつも、徹底した秘密主義が奏功して大ヒットし、大衆に支持された。その大衆によって、批評家以上の熱量で語られ、分析されたのである。
『サイコ』はヒッチコックにとって新しい挑戦だった。ハリウッドの慣例(スター・システムなど)に従って映画を作ってきた60歳の大監督は、当時、己の作家主義を存分に示すことができる題材、環境を求めていた。その際、目をつけたのがロバート・ブロックの原作である。パラマウント側が難色を示した原作の映画化権を自ら買い取ったヒッチコックは、撮影に際し、テレビ畑のスタッフを起用した。
映画は12月11日、午後2時43分、アリゾナ州フェニックスの安ホテルの一室から始まる。そこには情事に耽った後の男女がいる。不動産屋勤務で昼休み中のOL、マリオン(ジャネット・リー)と、カリフォルニア州から出張でやって来た恋人、サム(ジョン・ギャビン)である。マリオンはサムと結婚したがっているが、金銭問題を抱えるバツイチのサムは乗り気ではない。なんだか不毛の愛を描く映画のような雰囲気だ。
長い昼休みを終えて会社に戻ったマリオンは、取引相手が持ってきた4万ドルを銀行に預けに行くよう社長から言われる。金策に苦しむサムのために、そのお金を持ち逃げしよう。そう考えた彼女は会社を早退し、荷物をまとめてカリフォルニア州へ向かう。途中で警官に怪しまれたり、車を買い替えたりしながらも、彼女は何とか無事に運転を続ける。そこへ突然、大雨が降り、視界がきかなくなる。その時、「ベイツ・モーテル」の看板が目にとまる。
「ベイツ・モーテル」は時代に見放された旧道沿いにある。オフィスには誰もいない。マリオンはモーテルの隣に古めかしい邸宅があるのを認める。ベイツ邸は石段を上った高所に建っており、ゴシック風の大きな構えで、どこか不気味だ。明かりのついている窓のところに、老女らしき人影が見える。しかし、マリオンには気付いていないようだ。マリオンが車のクラクションを鳴らすと、邸宅から人が出てくる。甘いマスクの繊細そうな青年、鳥の剥製を趣味にしているノーマン・ベイツ(アンソニー・パーキンス)である。
動けない鳥
ここからは、映画を観ていない人は読まないことをお勧めする。
マリオンが「ベイツ・モーテル」に着くまでのくだりは印象的である。運転中、彼女は不動産屋の社長と取引相手が、月曜日にどんなやり取りをするのか想像してニヤリと笑う。そこへ雨が降る。執拗な豪雨のシャワーは、車中の彼女には直接当たっていないのに、冷たさと痛みを感じさせる。そんな中、目にするのが「ベイツ・モーテル」というわけだ。
そして二度目、バスルームでシャワーを浴びている時の彼女は、心を入れ替え、お金を会社に返すことを決意している。これは罪を洗いおとすシャワーである。すると、シャワー・カーテンの向こうに人影が現れる。「雨の中、モーテルが現れる」→「シャワーの中、殺人鬼が現れる」という風にイメージを反復させながら、死に向けて焦点を絞っているのである。
ノーマンが1号室の鍵を渡すのは、性的対象と認めた女性である。鳥の剥製(すでに指摘されているように、英語のstuffed birdの「stuff」には性交、「bird」には女の意味もある)があちこちに置かれたモーテルの応接室には、何枚かクラシカルな絵が飾られている。そのうちの一枚、「スザンナと長老たち」の絵を外すと、1号室を覗ける穴がある。1号室には鳥の絵が何枚も飾られている。この部屋はノーマンにとって、四六時中監視可能で、自分の意のままに出来る鳥かごなのだ。後の場面で、マリオンの行方を捜しに来た妹ライラ(ヴェラ・マイルズ)とサムが「ベイツ・モーテル」に来た時、彼らは10号室をあてがわれるが、そこに鳥の絵はない。
なぜこんな事件が起こったのか。ノーマン・ベイツが逮捕された後、分析医はその心理状態をやや気取った口調で長々と説明する。要約すると、ノーマンの中には、彼自身と亡き母親が半々の割合で棲んでいて、息子が女性を欲すると、母親が嫉妬して怒り出す。今はその争いも終わり、母親が勝利を収めたというのである。が、これで全ての説明がつくわけではない。マリオンが「殺されなければならなくなる」きっかけは何だったのか、映画から読み取る必要がある。
私が注視したいのは、モーテルの応接室でノーマンとマリオンが会話をするシーンである。その際、ノーマンの横には大きな鳥の剥製があり、マリオンの横にはインコらしき小鳥の剥製がある。これは一種のマウンティングである。過去にも何度か同じように女性をその位置に座らせ、会話し、威圧したことがあるのだろう。ノーマンはいわば「キャンディ・コーン」を餌にしている鳥であり、身動きできない鳥たちのボスなのである。
彼は初対面の女性に向かって、自分に自由がないこと、人生を諦めていること、母親に奉仕していることを話して聞かせる。しかし、小鳥と同列のかよわそうな鳥、すなわちマリオンは飛び立とうとする。ノーマンにとって、マリオンは先にも述べたように鳥かごの中の鳥である。その鳥が明朝フェニックスに帰る、と言うのだ。鳥に囲まれた中で口にされる「フェニックス」という言葉は、都市名よりも不死鳥を想起させる。これは生命力があり再生しようとする女のメタファーである。こうして飛べない鳥であるノーマンとの不協和音は決定的になる。
同化と再生
この時、立ち上がったマリオンの横に、カラスの剥製が映る。鳥を吉兆の徴とみなす人もいるが、少なくともヒッチコックは全くそう考えていなかった。このカットを観た誰もが、マリオンに良くないことが起こると予想するだろう。その後、彼女が1号室に戻ると、今度はノーマンが同じカラスの剥製の前に立ち、記帳を調べる。マリオンが偽名を使っていることがバレる場面だ。
そのわずかの間、カラスの影は大きくのびていて、あたかもノーマンのいびつな影のようになっている。撮影中、ヒッチコックはキャストの立ち位置を異常なほど細かく指示していたので、これは間違いなく意図的なカットである。こうしてノーマンは鳥の剥製と同化する。この映画では、鳥の剥製とミイラになった(剥製にされた)母親は同義である。すなわち、鳥の剥製と同化するということは、母親と同化するという意味を持つ。
そのおぞましい同化が、映像的にはっきり示されるのは、逮捕後、分析医による説明が終わったラスト間際である。薄気味悪い笑みを浮かべたノーマンの顔と、ミイラになった母親の顔がうっすらと重なるショットは、ヒッチコック自身、使うかどうか迷ったらしい。原作には、笑みを浮かべるという記述はない。しかし、これがあることにより、『サイコ』は救いのない映画となった。
その直後、沼から引き上げられるマリオンの車が映され、観客にまた彼女の死体を思い出させて、映画は終わる。「死」を墓地から掘り起こし、あるいは、沼地から引き上げる『サイコ』は、死者のイメージを再生させる映画なのだ。バックに流れている低弦の旋律が、「フランスのヒッチコック」と称されたアンリ=ジョルジュ・クルーゾー監督の『悪魔のような女』の音楽に似ているのも故無しとしない。このフランス映画でも、死んだはずの人間のイメージが何度も再生される。ヒッチコックはかつてボワロ&ナルスジャックの原作の映画化権を獲得しようとして、クルーゾーに先を越されたことがあった。このラストは、「本家」によるささやかな意趣返しだったのかもしれない。
全てが揃っている映画
『サイコ』には、ホラー映画に必要なテーマ、アイテム、シチュエーションがきれいに揃っている。ゴシック風の邸宅、モーテル、シャワー、シャワー・カーテン、剥製、ミイラ、鳥、沼、異常心理、母子の関係性、一人で危険な場所に向かう女性、女性の見開いた目、鏡、覗き穴、ストリングスを用いた鮮烈な音楽、童話的な設定(フランソワ・トリュフォーは「赤ずきんちゃん」と評した)などなど、挙げ出すとキリがない。これらの中には、1950年代までのホラーないしサスペンス映画で使われているものもあるが、すべてが集約されているのが『サイコ』である。その影響力は映画業界のみならず映画ファンにも及ぶ。映画の中でシャワー・シーンが映れば、殺人を連想してしまうレベルの凄まじい影響である。
ヒッチコックのフィルモグラフィの中でも、『サイコ』の位置は特殊である。それまでのサスペンス映画では、ヒッチコックはロマンティックな要素を重んじ、恋愛の成り行きにも注意を払っていた。『サイコ』も最初のシーンを男女の逢瀬で始めて、そのヒロインであるマリオンの行く末がどうなるのか気になるように仕向けている。が、その要素は映画の半分にも満たないうちに切り捨てられる。ヒロインであるべき存在が殺され、主人公が突然ノーマン・ベイツになり、観客の感情移入の対象が変わってしまい、恐怖映画のトーンに覆われる。
このようにロマンティックな要素が消え去り恐怖一色に覆われるパターン、誰もが(観客も含めて)犠牲者になり得るという不条理性、そして鳥のイメージの氾濫は、そのまま次作『鳥』に引き継がれることになる。
【関連サイト】
Alfred Hitchcock
PSYCHO(Blu-ray)
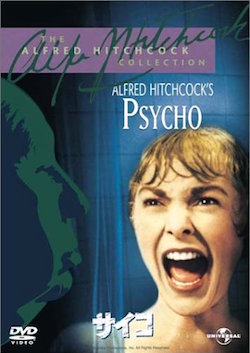
『サイコ』はヒッチコックにとって新しい挑戦だった。ハリウッドの慣例(スター・システムなど)に従って映画を作ってきた60歳の大監督は、当時、己の作家主義を存分に示すことができる題材、環境を求めていた。その際、目をつけたのがロバート・ブロックの原作である。パラマウント側が難色を示した原作の映画化権を自ら買い取ったヒッチコックは、撮影に際し、テレビ畑のスタッフを起用した。
映画は12月11日、午後2時43分、アリゾナ州フェニックスの安ホテルの一室から始まる。そこには情事に耽った後の男女がいる。不動産屋勤務で昼休み中のOL、マリオン(ジャネット・リー)と、カリフォルニア州から出張でやって来た恋人、サム(ジョン・ギャビン)である。マリオンはサムと結婚したがっているが、金銭問題を抱えるバツイチのサムは乗り気ではない。なんだか不毛の愛を描く映画のような雰囲気だ。
長い昼休みを終えて会社に戻ったマリオンは、取引相手が持ってきた4万ドルを銀行に預けに行くよう社長から言われる。金策に苦しむサムのために、そのお金を持ち逃げしよう。そう考えた彼女は会社を早退し、荷物をまとめてカリフォルニア州へ向かう。途中で警官に怪しまれたり、車を買い替えたりしながらも、彼女は何とか無事に運転を続ける。そこへ突然、大雨が降り、視界がきかなくなる。その時、「ベイツ・モーテル」の看板が目にとまる。
「ベイツ・モーテル」は時代に見放された旧道沿いにある。オフィスには誰もいない。マリオンはモーテルの隣に古めかしい邸宅があるのを認める。ベイツ邸は石段を上った高所に建っており、ゴシック風の大きな構えで、どこか不気味だ。明かりのついている窓のところに、老女らしき人影が見える。しかし、マリオンには気付いていないようだ。マリオンが車のクラクションを鳴らすと、邸宅から人が出てくる。甘いマスクの繊細そうな青年、鳥の剥製を趣味にしているノーマン・ベイツ(アンソニー・パーキンス)である。
動けない鳥
ここからは、映画を観ていない人は読まないことをお勧めする。
マリオンが「ベイツ・モーテル」に着くまでのくだりは印象的である。運転中、彼女は不動産屋の社長と取引相手が、月曜日にどんなやり取りをするのか想像してニヤリと笑う。そこへ雨が降る。執拗な豪雨のシャワーは、車中の彼女には直接当たっていないのに、冷たさと痛みを感じさせる。そんな中、目にするのが「ベイツ・モーテル」というわけだ。
そして二度目、バスルームでシャワーを浴びている時の彼女は、心を入れ替え、お金を会社に返すことを決意している。これは罪を洗いおとすシャワーである。すると、シャワー・カーテンの向こうに人影が現れる。「雨の中、モーテルが現れる」→「シャワーの中、殺人鬼が現れる」という風にイメージを反復させながら、死に向けて焦点を絞っているのである。
ノーマンが1号室の鍵を渡すのは、性的対象と認めた女性である。鳥の剥製(すでに指摘されているように、英語のstuffed birdの「stuff」には性交、「bird」には女の意味もある)があちこちに置かれたモーテルの応接室には、何枚かクラシカルな絵が飾られている。そのうちの一枚、「スザンナと長老たち」の絵を外すと、1号室を覗ける穴がある。1号室には鳥の絵が何枚も飾られている。この部屋はノーマンにとって、四六時中監視可能で、自分の意のままに出来る鳥かごなのだ。後の場面で、マリオンの行方を捜しに来た妹ライラ(ヴェラ・マイルズ)とサムが「ベイツ・モーテル」に来た時、彼らは10号室をあてがわれるが、そこに鳥の絵はない。
なぜこんな事件が起こったのか。ノーマン・ベイツが逮捕された後、分析医はその心理状態をやや気取った口調で長々と説明する。要約すると、ノーマンの中には、彼自身と亡き母親が半々の割合で棲んでいて、息子が女性を欲すると、母親が嫉妬して怒り出す。今はその争いも終わり、母親が勝利を収めたというのである。が、これで全ての説明がつくわけではない。マリオンが「殺されなければならなくなる」きっかけは何だったのか、映画から読み取る必要がある。
私が注視したいのは、モーテルの応接室でノーマンとマリオンが会話をするシーンである。その際、ノーマンの横には大きな鳥の剥製があり、マリオンの横にはインコらしき小鳥の剥製がある。これは一種のマウンティングである。過去にも何度か同じように女性をその位置に座らせ、会話し、威圧したことがあるのだろう。ノーマンはいわば「キャンディ・コーン」を餌にしている鳥であり、身動きできない鳥たちのボスなのである。
彼は初対面の女性に向かって、自分に自由がないこと、人生を諦めていること、母親に奉仕していることを話して聞かせる。しかし、小鳥と同列のかよわそうな鳥、すなわちマリオンは飛び立とうとする。ノーマンにとって、マリオンは先にも述べたように鳥かごの中の鳥である。その鳥が明朝フェニックスに帰る、と言うのだ。鳥に囲まれた中で口にされる「フェニックス」という言葉は、都市名よりも不死鳥を想起させる。これは生命力があり再生しようとする女のメタファーである。こうして飛べない鳥であるノーマンとの不協和音は決定的になる。
同化と再生
この時、立ち上がったマリオンの横に、カラスの剥製が映る。鳥を吉兆の徴とみなす人もいるが、少なくともヒッチコックは全くそう考えていなかった。このカットを観た誰もが、マリオンに良くないことが起こると予想するだろう。その後、彼女が1号室に戻ると、今度はノーマンが同じカラスの剥製の前に立ち、記帳を調べる。マリオンが偽名を使っていることがバレる場面だ。
そのわずかの間、カラスの影は大きくのびていて、あたかもノーマンのいびつな影のようになっている。撮影中、ヒッチコックはキャストの立ち位置を異常なほど細かく指示していたので、これは間違いなく意図的なカットである。こうしてノーマンは鳥の剥製と同化する。この映画では、鳥の剥製とミイラになった(剥製にされた)母親は同義である。すなわち、鳥の剥製と同化するということは、母親と同化するという意味を持つ。
そのおぞましい同化が、映像的にはっきり示されるのは、逮捕後、分析医による説明が終わったラスト間際である。薄気味悪い笑みを浮かべたノーマンの顔と、ミイラになった母親の顔がうっすらと重なるショットは、ヒッチコック自身、使うかどうか迷ったらしい。原作には、笑みを浮かべるという記述はない。しかし、これがあることにより、『サイコ』は救いのない映画となった。
その直後、沼から引き上げられるマリオンの車が映され、観客にまた彼女の死体を思い出させて、映画は終わる。「死」を墓地から掘り起こし、あるいは、沼地から引き上げる『サイコ』は、死者のイメージを再生させる映画なのだ。バックに流れている低弦の旋律が、「フランスのヒッチコック」と称されたアンリ=ジョルジュ・クルーゾー監督の『悪魔のような女』の音楽に似ているのも故無しとしない。このフランス映画でも、死んだはずの人間のイメージが何度も再生される。ヒッチコックはかつてボワロ&ナルスジャックの原作の映画化権を獲得しようとして、クルーゾーに先を越されたことがあった。このラストは、「本家」によるささやかな意趣返しだったのかもしれない。
全てが揃っている映画
『サイコ』には、ホラー映画に必要なテーマ、アイテム、シチュエーションがきれいに揃っている。ゴシック風の邸宅、モーテル、シャワー、シャワー・カーテン、剥製、ミイラ、鳥、沼、異常心理、母子の関係性、一人で危険な場所に向かう女性、女性の見開いた目、鏡、覗き穴、ストリングスを用いた鮮烈な音楽、童話的な設定(フランソワ・トリュフォーは「赤ずきんちゃん」と評した)などなど、挙げ出すとキリがない。これらの中には、1950年代までのホラーないしサスペンス映画で使われているものもあるが、すべてが集約されているのが『サイコ』である。その影響力は映画業界のみならず映画ファンにも及ぶ。映画の中でシャワー・シーンが映れば、殺人を連想してしまうレベルの凄まじい影響である。
ヒッチコックのフィルモグラフィの中でも、『サイコ』の位置は特殊である。それまでのサスペンス映画では、ヒッチコックはロマンティックな要素を重んじ、恋愛の成り行きにも注意を払っていた。『サイコ』も最初のシーンを男女の逢瀬で始めて、そのヒロインであるマリオンの行く末がどうなるのか気になるように仕向けている。が、その要素は映画の半分にも満たないうちに切り捨てられる。ヒロインであるべき存在が殺され、主人公が突然ノーマン・ベイツになり、観客の感情移入の対象が変わってしまい、恐怖映画のトーンに覆われる。
このようにロマンティックな要素が消え去り恐怖一色に覆われるパターン、誰もが(観客も含めて)犠牲者になり得るという不条理性、そして鳥のイメージの氾濫は、そのまま次作『鳥』に引き継がれることになる。
(阿部十三)
【関連サイト】
Alfred Hitchcock
PSYCHO(Blu-ray)
[アルフレッド・ヒッチコック略歴]
1899年8月13日、ロンドン郊外レインストーン生まれ。電信会社で働きながら絵画を学び、イズリントン撮影所で字幕書きを担当。助監督を経て、1925年に『快楽の園』でデビューを飾る。トーキー映画の到来と共に監督業も軌道に乗り、『暗殺者の家』『三十九夜』『サボタージュ』『バルカン超特急』を発表。渡米後、『レベッカ』でアカデミー作品賞を受賞。1960年代初頭まで精力的に傑作を撮り続け、『めまい』『北北西に進路をとれ』『サイコ』『鳥』でピークを迎える(これらの作品と同時期、テレビ番組『ヒッチコック劇場』の監修も務めていた)。その後、一時精彩を欠くものの1970年代に『フレンジー』で復活。1980年4月29日ベル・エアの自宅で死去。「サスペンスの神様」の異名を持つ。1926年に結婚した妻アルマは、『殺人!』『断崖』『疑惑の影』などの脚本家でもある。
1899年8月13日、ロンドン郊外レインストーン生まれ。電信会社で働きながら絵画を学び、イズリントン撮影所で字幕書きを担当。助監督を経て、1925年に『快楽の園』でデビューを飾る。トーキー映画の到来と共に監督業も軌道に乗り、『暗殺者の家』『三十九夜』『サボタージュ』『バルカン超特急』を発表。渡米後、『レベッカ』でアカデミー作品賞を受賞。1960年代初頭まで精力的に傑作を撮り続け、『めまい』『北北西に進路をとれ』『サイコ』『鳥』でピークを迎える(これらの作品と同時期、テレビ番組『ヒッチコック劇場』の監修も務めていた)。その後、一時精彩を欠くものの1970年代に『フレンジー』で復活。1980年4月29日ベル・エアの自宅で死去。「サスペンスの神様」の異名を持つ。1926年に結婚した妻アルマは、『殺人!』『断崖』『疑惑の影』などの脚本家でもある。
[主な監督作品]
1925年『快楽の園』/1927年『下宿人』/1929年『ゆすり』/1930年『殺人!』/1932年『第十七番』/1934年『暗殺者の家』/1935年『三十九夜』/1936年『間諜最後の日』『サボタージュ』/1937年『第3逃亡者』/1938年『バルカン超特急』/1940年『レベッカ』『海外特派員』/1941年『断崖』/1942年『逃走迷路』/1943年『疑惑の影』/1944年『救命艇』/1945年『白い恐怖』/1946年『汚名』/1947年『パラダイン夫人の恋』/1948年『ロープ』/1949年『山羊座のもとに』/1950年『舞台恐怖症』/1951年『見知らぬ乗客』/1953年『私は告白する』/1954年『ダイヤルMを廻せ!』『裏窓』/1955年『ハリーの災難』/1956年『知りすぎていた男』/1956年『間違えられた男』/1958年『めまい』/1959年『北北西に進路をとれ』/1960年『サイコ』/1963年『鳥』/1964年『マーニー』/1966年『引き裂かれたカーテン』/1969年『トパーズ』/1972年『フレンジー』/1976年『ファミリー・プロット』
1925年『快楽の園』/1927年『下宿人』/1929年『ゆすり』/1930年『殺人!』/1932年『第十七番』/1934年『暗殺者の家』/1935年『三十九夜』/1936年『間諜最後の日』『サボタージュ』/1937年『第3逃亡者』/1938年『バルカン超特急』/1940年『レベッカ』『海外特派員』/1941年『断崖』/1942年『逃走迷路』/1943年『疑惑の影』/1944年『救命艇』/1945年『白い恐怖』/1946年『汚名』/1947年『パラダイン夫人の恋』/1948年『ロープ』/1949年『山羊座のもとに』/1950年『舞台恐怖症』/1951年『見知らぬ乗客』/1953年『私は告白する』/1954年『ダイヤルMを廻せ!』『裏窓』/1955年『ハリーの災難』/1956年『知りすぎていた男』/1956年『間違えられた男』/1958年『めまい』/1959年『北北西に進路をとれ』/1960年『サイコ』/1963年『鳥』/1964年『マーニー』/1966年『引き裂かれたカーテン』/1969年『トパーズ』/1972年『フレンジー』/1976年『ファミリー・プロット』
月別インデックス
- May 2024 [1]
- January 2023 [1]
- November 2021 [1]
- April 2021 [1]
- September 2020 [2]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- January 2020 [1]
- July 2019 [1]
- March 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [3]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- October 2017 [2]
- September 2017 [1]
- June 2017 [2]
- March 2017 [2]
- November 2016 [1]
- August 2016 [1]
- July 2016 [2]
- February 2016 [1]
- October 2015 [1]
- August 2015 [1]
- June 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [1]
- January 2015 [2]
- September 2014 [1]
- July 2014 [2]
- May 2014 [1]
- March 2014 [1]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- September 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [1]
- May 2013 [1]
- February 2013 [1]
- December 2012 [2]
- October 2012 [2]
- August 2012 [2]
- June 2012 [1]
- April 2012 [2]
- March 2012 [1]
- February 2012 [1]
- January 2012 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]