
川島雄三 〜日本軽佻派であり、天才であり〜
2011.06.26
映画界の戯作者として
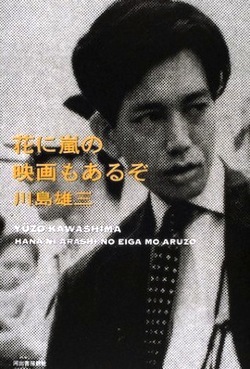 川島雄三は45年の短い人生で51本の作品を撮ったが、そのうち傑作と呼べるものは僅かしかない。しかし、その数少ない傑作には、誇張を抜きにして、観た人の価値観や人生観までも変えてしまうくらいの磁場が広がっている。残りの困った作品群も、見方によっては斬新で、捨てがたい味わいがあり、一部のカルト映画ファンから支持されている。
川島雄三は45年の短い人生で51本の作品を撮ったが、そのうち傑作と呼べるものは僅かしかない。しかし、その数少ない傑作には、誇張を抜きにして、観た人の価値観や人生観までも変えてしまうくらいの磁場が広がっている。残りの困った作品群も、見方によっては斬新で、捨てがたい味わいがあり、一部のカルト映画ファンから支持されている。
具体的に書くと、一方では『洲崎パラダイス 赤信号』『幕末太陽傳』『女は二度生まれる』というタイプの異なる3種類の傑作を撮った天才監督として崇拝され、他方では『とんかつ大将』『グラマ島の誘惑』などのカルト映画の監督として偏愛されているのだ。凡作、駄作はかなりの数にのぼる。こんな奇妙な振り幅を持った人は、世界映画史を見渡してもそうそういないだろう。
川島監督は進行性筋萎縮症のため右手右足が不自由で、病気がちで、つねに死への不安を抱いていた。それを振りきらんとして映画界の戯作者になりきり、都会的で軽佻浮薄な作品をむやみやたらに乱発した。......というのが定説になっているが、それはキャリアの前半に低予算コメディがひしめいていること、自ら〈日本軽佻派〉を標榜していたこと、そして川島の代表作『幕末太陽傳』のイメージが強いことから、そう言われているのだろう。実際は深みのある文芸作品も撮っている。
病気についても、体が不自由だったのは確かだが、進行性筋萎縮症だったかどうかは判然としない。この病名はあくまでも川島の助監督を務めていた今村昌平が唱えた説である。
実生活での川島は、おセンチを毛嫌いしていた。田舎を嫌い、生まれ故郷の青森を嫌い、過去を振り返ることを拒んでいた。病気のことも人に言わなかった。そんな彼が愛した言葉は、「花ニ嵐ノタトエモアルゾ、「サヨナラ」ダケガ人生ダ」(井伏鱒二訳の漢詩『勧酒』)だった。
積極的逃避
川島監督の神髄を味わえる傑作は『洲崎パラダイス 赤信号』『幕末太陽傳』『女は二度生まれる』。この中で最も語られる機会が多いのは『幕末太陽傳』だろう。
時は幕末、文久2年(1862年)。舞台は品川宿の遊郭。労咳を病みながらも己の才覚を武器に要領よく生きる男、佐平次を軸に、騒乱の時代を生きる人々の姿を軽妙なタッチで描いた群像劇の傑作である。元ネタは古典落語「居残り佐平次」「三枚起請」「品川心中」など。冒頭から快速テンポで、全くだれることなく、巧みなギアチェンジを駆使しながら終盤まで突っ切る。
ただ、佐平次の病気が暗い影を落としている点がミソ。このハンデがあることによって、我々は飄々とした佐平次の心中に死への恐怖が潜んでいることをいやでも感じてしまう。
川島によると、この映画のテーマは「積極的逃避」だという。何からの逃避なのか。人間関係、面倒事、嫉妬、束縛、支配、恋愛、義理人情、病気、そして死からの逃避であろう。それらは生きている以上、必ずついて回るもの。とくに死から逃げようなんて無駄な抵抗である。だけど、せいぜい逃げることができる所まで逃げてやれというわけだ(最も象徴的なのがラストシーン)。
 『幕末太陽傳』の「太陽」の由来は太陽族。簡単に言ってしまえば、幕末の太陽族の映画である。『幕末太陽傳』が公開されたのは1957年7月14日。いわゆる「太陽族映画」が映画館から締め出された1956年8月から約1年後のこと。そこへあえて「太陽」の文字を持ち込むのが川島らしい。
『幕末太陽傳』の「太陽」の由来は太陽族。簡単に言ってしまえば、幕末の太陽族の映画である。『幕末太陽傳』が公開されたのは1957年7月14日。いわゆる「太陽族映画」が映画館から締め出された1956年8月から約1年後のこと。そこへあえて「太陽」の文字を持ち込むのが川島らしい。
太陽族のシンボル、石原裕次郎も出演している。彼の役は高杉晋作。アイドル的な存在感を放ち、高杉というよりは裕次郎そのものにしか見えない。イナセで、ひたすらカッコよく、爽やかな笑い方も裕次郎独特のものだ。ただ、キレイにカッコよくおさまりすぎたところが川島自身は不服だったようで、「高杉の扱いが類型的になりすぎて、やり直したい気がします」と述べている。
主役の佐平次はフランキー堺。生涯のハマり役である。ほとんど地でやっているようにしか見えないが、さにあらず、浴衣の着方ひとつとっても吉原の幇間に教えてもらうなど、ちょっとした所作にもこだわっていたようだ。労咳病みという設定についても、脚本が上がった当初は「病気か、仮病か」という点が曖昧だったが、フランキー堺が明確に病気持ちにした方がいいと提案し、それが通った。
織田作之助の影響
佐平次は宿痾に悩みながらも〈軽佻派〉であろうとした川島自身の分身ではないか、と言われているが、その辺はどうなのだろう。川島映画に欠かせないカメラマン高村倉太郎は、「あれはちょっと関西っぽいんじゃないかと。佐平次の動き回る姿がね、あれだけ抜け目なく動くのは関西風じゃないかと」と指摘している。そう言われるとそんな気もする。
「関西」と聞いて思い浮かぶのは大阪の織田作之助。通称「オダサク」。生き方の上でも川島が多大な影響を受けた無頼派作家である。
オダサクは1913年10月大阪生まれ。若い頃から結核を患い、ひどい咳をし、喀血を繰り返していた。戦時中にはヒロポンを覚え、中毒になった(最初にヒロポンをすすめたのは刑事だという)。作家としては『俗臭』が芥川賞候補になって注目され、『夫婦善哉』で評価を高め、戦後、『六白金星』『アド・バルーン』『世相』などで流行作家になった。そして1947年1月、33歳で閃光のように逝った。その人生の全容は、大谷晃一が書いた伝記『生き愛し書いた 織田作之助伝』に詳しく書いてある(この伝記のタイトルは、オダサクが夢中になったフランスの作家、スタンダールの墓碑銘「生きた、書いた、愛した」からとられたものである)。
川島はオダサクの脚本による『還って来た男』で監督デビューし、プライヴェートでも親交を結んでいた。戦争末期、共に〈日本軽佻派〉を作った仲でもある。無頼派オダサクのイメージが佐平次の人物造型に影響を与えたかどうか、はっきりしたことは言えないが、多少投影されている部分はあるだろうと私は思っている。
【関連サイト】
川島雄三 〜日本軽佻派であり、天才であり〜 [続き]
監督・川島雄三
川島雄三(DVD)
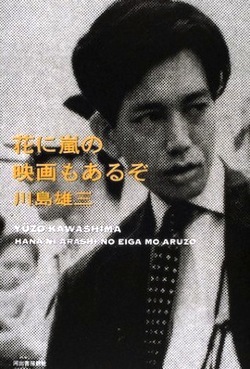
具体的に書くと、一方では『洲崎パラダイス 赤信号』『幕末太陽傳』『女は二度生まれる』というタイプの異なる3種類の傑作を撮った天才監督として崇拝され、他方では『とんかつ大将』『グラマ島の誘惑』などのカルト映画の監督として偏愛されているのだ。凡作、駄作はかなりの数にのぼる。こんな奇妙な振り幅を持った人は、世界映画史を見渡してもそうそういないだろう。
川島監督は進行性筋萎縮症のため右手右足が不自由で、病気がちで、つねに死への不安を抱いていた。それを振りきらんとして映画界の戯作者になりきり、都会的で軽佻浮薄な作品をむやみやたらに乱発した。......というのが定説になっているが、それはキャリアの前半に低予算コメディがひしめいていること、自ら〈日本軽佻派〉を標榜していたこと、そして川島の代表作『幕末太陽傳』のイメージが強いことから、そう言われているのだろう。実際は深みのある文芸作品も撮っている。
病気についても、体が不自由だったのは確かだが、進行性筋萎縮症だったかどうかは判然としない。この病名はあくまでも川島の助監督を務めていた今村昌平が唱えた説である。
実生活での川島は、おセンチを毛嫌いしていた。田舎を嫌い、生まれ故郷の青森を嫌い、過去を振り返ることを拒んでいた。病気のことも人に言わなかった。そんな彼が愛した言葉は、「花ニ嵐ノタトエモアルゾ、「サヨナラ」ダケガ人生ダ」(井伏鱒二訳の漢詩『勧酒』)だった。
積極的逃避
川島監督の神髄を味わえる傑作は『洲崎パラダイス 赤信号』『幕末太陽傳』『女は二度生まれる』。この中で最も語られる機会が多いのは『幕末太陽傳』だろう。
時は幕末、文久2年(1862年)。舞台は品川宿の遊郭。労咳を病みながらも己の才覚を武器に要領よく生きる男、佐平次を軸に、騒乱の時代を生きる人々の姿を軽妙なタッチで描いた群像劇の傑作である。元ネタは古典落語「居残り佐平次」「三枚起請」「品川心中」など。冒頭から快速テンポで、全くだれることなく、巧みなギアチェンジを駆使しながら終盤まで突っ切る。
ただ、佐平次の病気が暗い影を落としている点がミソ。このハンデがあることによって、我々は飄々とした佐平次の心中に死への恐怖が潜んでいることをいやでも感じてしまう。
川島によると、この映画のテーマは「積極的逃避」だという。何からの逃避なのか。人間関係、面倒事、嫉妬、束縛、支配、恋愛、義理人情、病気、そして死からの逃避であろう。それらは生きている以上、必ずついて回るもの。とくに死から逃げようなんて無駄な抵抗である。だけど、せいぜい逃げることができる所まで逃げてやれというわけだ(最も象徴的なのがラストシーン)。

太陽族のシンボル、石原裕次郎も出演している。彼の役は高杉晋作。アイドル的な存在感を放ち、高杉というよりは裕次郎そのものにしか見えない。イナセで、ひたすらカッコよく、爽やかな笑い方も裕次郎独特のものだ。ただ、キレイにカッコよくおさまりすぎたところが川島自身は不服だったようで、「高杉の扱いが類型的になりすぎて、やり直したい気がします」と述べている。
主役の佐平次はフランキー堺。生涯のハマり役である。ほとんど地でやっているようにしか見えないが、さにあらず、浴衣の着方ひとつとっても吉原の幇間に教えてもらうなど、ちょっとした所作にもこだわっていたようだ。労咳病みという設定についても、脚本が上がった当初は「病気か、仮病か」という点が曖昧だったが、フランキー堺が明確に病気持ちにした方がいいと提案し、それが通った。
織田作之助の影響
佐平次は宿痾に悩みながらも〈軽佻派〉であろうとした川島自身の分身ではないか、と言われているが、その辺はどうなのだろう。川島映画に欠かせないカメラマン高村倉太郎は、「あれはちょっと関西っぽいんじゃないかと。佐平次の動き回る姿がね、あれだけ抜け目なく動くのは関西風じゃないかと」と指摘している。そう言われるとそんな気もする。
「関西」と聞いて思い浮かぶのは大阪の織田作之助。通称「オダサク」。生き方の上でも川島が多大な影響を受けた無頼派作家である。
オダサクは1913年10月大阪生まれ。若い頃から結核を患い、ひどい咳をし、喀血を繰り返していた。戦時中にはヒロポンを覚え、中毒になった(最初にヒロポンをすすめたのは刑事だという)。作家としては『俗臭』が芥川賞候補になって注目され、『夫婦善哉』で評価を高め、戦後、『六白金星』『アド・バルーン』『世相』などで流行作家になった。そして1947年1月、33歳で閃光のように逝った。その人生の全容は、大谷晃一が書いた伝記『生き愛し書いた 織田作之助伝』に詳しく書いてある(この伝記のタイトルは、オダサクが夢中になったフランスの作家、スタンダールの墓碑銘「生きた、書いた、愛した」からとられたものである)。
川島はオダサクの脚本による『還って来た男』で監督デビューし、プライヴェートでも親交を結んでいた。戦争末期、共に〈日本軽佻派〉を作った仲でもある。無頼派オダサクのイメージが佐平次の人物造型に影響を与えたかどうか、はっきりしたことは言えないが、多少投影されている部分はあるだろうと私は思っている。
【関連サイト】
川島雄三 〜日本軽佻派であり、天才であり〜 [続き]
監督・川島雄三
川島雄三(DVD)
月別インデックス
- May 2024 [1]
- January 2023 [1]
- November 2021 [1]
- April 2021 [1]
- September 2020 [2]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- January 2020 [1]
- July 2019 [1]
- March 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [3]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- October 2017 [2]
- September 2017 [1]
- June 2017 [2]
- March 2017 [2]
- November 2016 [1]
- August 2016 [1]
- July 2016 [2]
- February 2016 [1]
- October 2015 [1]
- August 2015 [1]
- June 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [1]
- January 2015 [2]
- September 2014 [1]
- July 2014 [2]
- May 2014 [1]
- March 2014 [1]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- September 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [1]
- May 2013 [1]
- February 2013 [1]
- December 2012 [2]
- October 2012 [2]
- August 2012 [2]
- June 2012 [1]
- April 2012 [2]
- March 2012 [1]
- February 2012 [1]
- January 2012 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]