
ロベール・ブレッソン 〜孤独な「シネマトグラフ」〜
2012.01.12
同情と共感をあてにしない映像作家
2003年製作のドキュメンタリー「『スリ』のモデルたち」で、マリカ・グリーンが興味深い発言をしている。ブレッソン映画に出た女優たちはお互いに攻撃的で、協調性がない、というのだ。
「何かあるんだろうと思うわ。嫉妬というと語弊があるけど、おそらくそれぞれの親密な関係を守りたいんでしょうね。〈私とブレッソン〉という秘密の小さな花園を。それぞれの〈ブレッソン〉が存在するのよ」
同じことはファンの態度にも当てはまる。自分にとっての至高のブレッソン作品を崇拝するあまり、彼が撮ったほかの作品に冷淡な態度をとっている人がいかに多いことか。かつてイングマール・ベルイマンはインタビュアーに『少女ムシェット』を否定されると、ムキになってこの作品の魅力を説き、『バルタザールどこへ行く』を一蹴した。ある者は『田舎司祭の日記』を絶賛し、『スリ』を否定する。ある者は『抵抗ー死刑囚の手記より』に驚嘆し、『ラルジャン』から目を背ける。同じ監督の手から生まれた作品なのに、互いに相容れない、といわんばかりである。
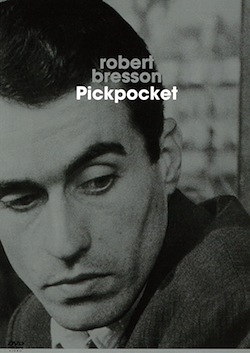 ロベール・ブレッソンは、極限まで切り詰められた素材で完全にオリジナルな映像世界を創造した寡作の天才である。彼以上に「映像作家」という呼称がしっくりくる監督もいない。「シネマトグラフ」と呼ばれるその数少ない作品で、彼は素人の「モデル」を起用し(俳優ではなくモデルと呼ばれた)、音楽の使用を最小限に抑え、演出上の仰々しさ、派手さ、センチメンタリズムを排除し、登場人物の孤独を淡々と、冷たく、容赦なく映し出す。観客の同情や共感などあてにしていない。特定のキャラクターに温情をかけたり、ストーリーにメッセージ性を持たせたりもしない。彼が注力したのは、人物の目線や動作のフォルムの様式化である。それを、技術を匂わせないようにしながら行っている。その簡略化された様式が、想像力の起爆装置となり、観る者の心に忘れがたい印象を刻み残す。
ロベール・ブレッソンは、極限まで切り詰められた素材で完全にオリジナルな映像世界を創造した寡作の天才である。彼以上に「映像作家」という呼称がしっくりくる監督もいない。「シネマトグラフ」と呼ばれるその数少ない作品で、彼は素人の「モデル」を起用し(俳優ではなくモデルと呼ばれた)、音楽の使用を最小限に抑え、演出上の仰々しさ、派手さ、センチメンタリズムを排除し、登場人物の孤独を淡々と、冷たく、容赦なく映し出す。観客の同情や共感などあてにしていない。特定のキャラクターに温情をかけたり、ストーリーにメッセージ性を持たせたりもしない。彼が注力したのは、人物の目線や動作のフォルムの様式化である。それを、技術を匂わせないようにしながら行っている。その簡略化された様式が、想像力の起爆装置となり、観る者の心に忘れがたい印象を刻み残す。
1956年の『抵抗』以降は音楽の使用が減り、その代わり、カツカツという靴音、ドアの閉まる音、車のエンジンの音、紙幣がカサカサいう音、日常の様々な音が意図的に強調されるようになった。そういうありふれた音を効果的に用いることで、観る者の集中力を引き出す手法も、ブレッソンならではのものだ。ルイ・マルやジャン=リュック・ゴダールをはじめとするヌーヴェル・ヴァーグの監督たちはブレッソンを崇拝していたが、結局この先人よりも斬新なスタイルを確立できた者はいない。
「全く演技をしないことが重要だ」
具体的に、その演出法はどんなものだったのか。『バルタザールどこへ行く』の撮影時を回想したアンヌ・ヴィアゼムスキーの著作『若い娘』には、ブレッソンがジャック役のヴァルテル・グリーン(マリカ・グリーンの弟)を指導するシーンが出てくる。そこでブレッソンはこういっている。
「君にはあらゆる意図を取り除いてほしい。ジャックであろうとして演技してはならない。内面を演じてはいけない。全く演技をしないことが重要だ」
『若い娘』は小説なので、全てが事実というわけでもないのだろうが、ほかの「モデル」たちの証言を読んでも、ブレッソンのディレクションは大体こんな感じだったらしい。歩くシーンを撮る時も、何度も何度も歩かせて、演者の感覚が麻痺してなぜ自分が歩いているのか分からなくなった時にようやくオーケーが出る。このやり方では時間もかかるわけである。ブレッソンは職業俳優を全否定したが、それも彼の理念からすれば当然の成り行きだったのだろう。演技欲に満ち、ほかの作品と掛け持ちするようなスターはお呼びではなかったのだ。
このように、ブレッソン・スタイルともいうべき美学が共通してありながらも、完成した作品それぞれが異なる性格とニュアンスを持ち、観る者の好みを完全に隔てているのは、注目すべきことである。かくいう私も昔、『スリ』をきっかけにこの監督にのめり込んだものの、『ラルジャン』をどうしても受け入れることができず、映画サークルにいた同級生と議論したことがある。『バルタザールどこへ行く』を褒めちぎっている人の神経を疑ったこともある。なぜそんな風に感じてしまうのか、当時は自己分析すらできないほど生理的なレベルで拒否していた。今思うと、『バルタザールどこへ行く』や『ラルジャン』を受け入れられなかったのは、この2作のどこにも善意を見出せなかったからだろう。悪意によって生まれた邪悪な映画としか思えなかったのだ。そのため、凄い作品だということは分かっても、好きにはなれなかった。善意の押し売りは勘弁願いたいが、善意のかけらもないのも苦痛である。
慣れさせない映画
ブレッソンの映画がもたらす印象は恒久的に変わらない。ホラーでさえ、同じものを何度も観れば受容の感覚が安定し、恐怖が薄れてくるものなのに、「シネマトグラフ」ではそういうことが起こらない。感覚が慣れる、ということがないのだ。
私はこれまでに『田舎司祭の日記』を少なくとも10回は観ているが、この作品がもたらす畏怖にも近い感銘は一向に弱まらない。映画のトーンは「常に」冷たく、悲しく、苦しく、容赦がない。『スリ』も20回は観ているが、「常に」簡素で、ブレッソンらしくない粗さはあるけれど、そこも含めて美しい。とくに新たな発見があるわけでもないのに、その都度、新たな気持ちで接することができる。懐かしい、という感覚とはほど遠いところにある映画だ。『バルタザールどこへ行く』も、「相変わらず」胸底から湧く怒りと生木を裂くような痛みでこちらをヘトヘトにさせるし、『ラルジャン』でやがて残虐な加害者になる男がスープを飲む忌まわしいシーンも、「相変わらず」生理的嫌悪感を催させる。繰り返すが、何度も観ても、慣れることはない。
多くの人が映画を選ぶ時に重要視するのはキャストだろう。ブレッソンはそんな中で「映画は監督が作るものだ」というスタンスを明確に打ち出し、実践した。いわゆる作家主義である。スターは使わない。「モデル」には一切権限を与えない。過剰なドラマも排除する。そのスタイルを徹底して貫く。ーーただ、それだけでは傑作は生まれない。印象そのものは変わらないのに、奇跡のように常に新しい映画。多くの人に幾度となく分析されながら、未だ神秘に包まれている映画術。金言を集めた『シネマトグラフ覚書』を読んでも、ブレッソンの魔術の秘密は解き明かせない。私たちは、分析を撥ねつけるシンプルな映像の圧倒的強度に対し、ほとんど無抵抗のまま、感嘆するよりほかないのだ。
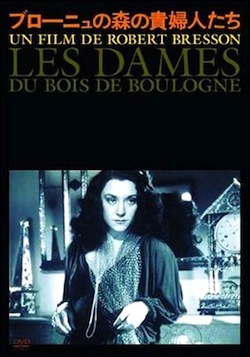 個人的に大事にしている作品は、『ブローニュの森の貴婦人たち』と『スリ』である。『スリ』は最初に夢中になった「シネマトグラフ」だが、ここ10年くらいは『ブローニュの森の貴婦人たち』の方をよく観ている。原作は、ディドロの『運命論者ジャックとその主人』。この中のエピソードをもとにして、「危険な関係」的な物語を紡いでいる。台詞監修にジャン・コクトーの名があるが、ブレッソンにいわせると「コクトーはほとんど何もしていない」らしい。
個人的に大事にしている作品は、『ブローニュの森の貴婦人たち』と『スリ』である。『スリ』は最初に夢中になった「シネマトグラフ」だが、ここ10年くらいは『ブローニュの森の貴婦人たち』の方をよく観ている。原作は、ディドロの『運命論者ジャックとその主人』。この中のエピソードをもとにして、「危険な関係」的な物語を紡いでいる。台詞監修にジャン・コクトーの名があるが、ブレッソンにいわせると「コクトーはほとんど何もしていない」らしい。
主人公は、男の愛を失ったのではないかと感じているエレーヌ。彼女はまだ男のことを愛しているが、もう愛していないと嘘をつく。すると男は目を輝かせ、実は僕も同じ気持ちだったといい、すがすがしい表情で女のもとを去る。復讐を決意したエレーヌは、過去を持つ踊り子アニエスを清純な乙女に仕立てて男に紹介し、結婚させようと企む。
この作品はジャック・ドゥミを感激させ、映画監督を志すきっかけを与えた。フランソワ・トリュフォーも『暗くなるまでこの恋を』で台詞を引用している。長編としては2作目で、まだブレッソン・スタイルは確立されておらず、台詞にも気取りが感じられるが、洗練された様式の中に格調高い古典劇の雰囲気が漂っていて、崇高ともいえる余韻を残す。
【関連サイト】
Robert Bresson
ロベール・ブレッソン(DVD)
2003年製作のドキュメンタリー「『スリ』のモデルたち」で、マリカ・グリーンが興味深い発言をしている。ブレッソン映画に出た女優たちはお互いに攻撃的で、協調性がない、というのだ。
「何かあるんだろうと思うわ。嫉妬というと語弊があるけど、おそらくそれぞれの親密な関係を守りたいんでしょうね。〈私とブレッソン〉という秘密の小さな花園を。それぞれの〈ブレッソン〉が存在するのよ」
同じことはファンの態度にも当てはまる。自分にとっての至高のブレッソン作品を崇拝するあまり、彼が撮ったほかの作品に冷淡な態度をとっている人がいかに多いことか。かつてイングマール・ベルイマンはインタビュアーに『少女ムシェット』を否定されると、ムキになってこの作品の魅力を説き、『バルタザールどこへ行く』を一蹴した。ある者は『田舎司祭の日記』を絶賛し、『スリ』を否定する。ある者は『抵抗ー死刑囚の手記より』に驚嘆し、『ラルジャン』から目を背ける。同じ監督の手から生まれた作品なのに、互いに相容れない、といわんばかりである。
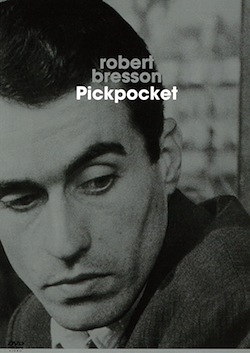
1956年の『抵抗』以降は音楽の使用が減り、その代わり、カツカツという靴音、ドアの閉まる音、車のエンジンの音、紙幣がカサカサいう音、日常の様々な音が意図的に強調されるようになった。そういうありふれた音を効果的に用いることで、観る者の集中力を引き出す手法も、ブレッソンならではのものだ。ルイ・マルやジャン=リュック・ゴダールをはじめとするヌーヴェル・ヴァーグの監督たちはブレッソンを崇拝していたが、結局この先人よりも斬新なスタイルを確立できた者はいない。
「全く演技をしないことが重要だ」
具体的に、その演出法はどんなものだったのか。『バルタザールどこへ行く』の撮影時を回想したアンヌ・ヴィアゼムスキーの著作『若い娘』には、ブレッソンがジャック役のヴァルテル・グリーン(マリカ・グリーンの弟)を指導するシーンが出てくる。そこでブレッソンはこういっている。
「君にはあらゆる意図を取り除いてほしい。ジャックであろうとして演技してはならない。内面を演じてはいけない。全く演技をしないことが重要だ」
『若い娘』は小説なので、全てが事実というわけでもないのだろうが、ほかの「モデル」たちの証言を読んでも、ブレッソンのディレクションは大体こんな感じだったらしい。歩くシーンを撮る時も、何度も何度も歩かせて、演者の感覚が麻痺してなぜ自分が歩いているのか分からなくなった時にようやくオーケーが出る。このやり方では時間もかかるわけである。ブレッソンは職業俳優を全否定したが、それも彼の理念からすれば当然の成り行きだったのだろう。演技欲に満ち、ほかの作品と掛け持ちするようなスターはお呼びではなかったのだ。
このように、ブレッソン・スタイルともいうべき美学が共通してありながらも、完成した作品それぞれが異なる性格とニュアンスを持ち、観る者の好みを完全に隔てているのは、注目すべきことである。かくいう私も昔、『スリ』をきっかけにこの監督にのめり込んだものの、『ラルジャン』をどうしても受け入れることができず、映画サークルにいた同級生と議論したことがある。『バルタザールどこへ行く』を褒めちぎっている人の神経を疑ったこともある。なぜそんな風に感じてしまうのか、当時は自己分析すらできないほど生理的なレベルで拒否していた。今思うと、『バルタザールどこへ行く』や『ラルジャン』を受け入れられなかったのは、この2作のどこにも善意を見出せなかったからだろう。悪意によって生まれた邪悪な映画としか思えなかったのだ。そのため、凄い作品だということは分かっても、好きにはなれなかった。善意の押し売りは勘弁願いたいが、善意のかけらもないのも苦痛である。
慣れさせない映画
ブレッソンの映画がもたらす印象は恒久的に変わらない。ホラーでさえ、同じものを何度も観れば受容の感覚が安定し、恐怖が薄れてくるものなのに、「シネマトグラフ」ではそういうことが起こらない。感覚が慣れる、ということがないのだ。
私はこれまでに『田舎司祭の日記』を少なくとも10回は観ているが、この作品がもたらす畏怖にも近い感銘は一向に弱まらない。映画のトーンは「常に」冷たく、悲しく、苦しく、容赦がない。『スリ』も20回は観ているが、「常に」簡素で、ブレッソンらしくない粗さはあるけれど、そこも含めて美しい。とくに新たな発見があるわけでもないのに、その都度、新たな気持ちで接することができる。懐かしい、という感覚とはほど遠いところにある映画だ。『バルタザールどこへ行く』も、「相変わらず」胸底から湧く怒りと生木を裂くような痛みでこちらをヘトヘトにさせるし、『ラルジャン』でやがて残虐な加害者になる男がスープを飲む忌まわしいシーンも、「相変わらず」生理的嫌悪感を催させる。繰り返すが、何度も観ても、慣れることはない。
多くの人が映画を選ぶ時に重要視するのはキャストだろう。ブレッソンはそんな中で「映画は監督が作るものだ」というスタンスを明確に打ち出し、実践した。いわゆる作家主義である。スターは使わない。「モデル」には一切権限を与えない。過剰なドラマも排除する。そのスタイルを徹底して貫く。ーーただ、それだけでは傑作は生まれない。印象そのものは変わらないのに、奇跡のように常に新しい映画。多くの人に幾度となく分析されながら、未だ神秘に包まれている映画術。金言を集めた『シネマトグラフ覚書』を読んでも、ブレッソンの魔術の秘密は解き明かせない。私たちは、分析を撥ねつけるシンプルな映像の圧倒的強度に対し、ほとんど無抵抗のまま、感嘆するよりほかないのだ。
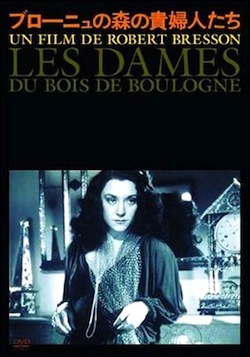
主人公は、男の愛を失ったのではないかと感じているエレーヌ。彼女はまだ男のことを愛しているが、もう愛していないと嘘をつく。すると男は目を輝かせ、実は僕も同じ気持ちだったといい、すがすがしい表情で女のもとを去る。復讐を決意したエレーヌは、過去を持つ踊り子アニエスを清純な乙女に仕立てて男に紹介し、結婚させようと企む。
この作品はジャック・ドゥミを感激させ、映画監督を志すきっかけを与えた。フランソワ・トリュフォーも『暗くなるまでこの恋を』で台詞を引用している。長編としては2作目で、まだブレッソン・スタイルは確立されておらず、台詞にも気取りが感じられるが、洗練された様式の中に格調高い古典劇の雰囲気が漂っていて、崇高ともいえる余韻を残す。
(阿部十三)
【関連サイト】
Robert Bresson
ロベール・ブレッソン(DVD)
[ロベール・ブレッソン プロフィール]
1901年9月25日、フランスのブロモン=ラモット生まれ。画家を志すが、映画界に進み、1934年に喜劇『公務』で短編デビュー。1943年ジャン・ジロドゥ台本による『罪の天使たち』で長編デビュー。1951年『田舎司祭の日記』がヴェネチア映画祭で3部門受賞。1956年の『抵抗ー死刑囚の手記より』から独自の演出スタイルの徹底化を図り、職業俳優を使わなくなる。同作品でカンヌ映画祭監督賞受賞。1983年『ラルジャン』でカンヌ映画祭創造大賞受賞。1999年12月18日、パリで死去。私生活はヴェールに包まれているが、レイディア・ファン・デル・ゼー、ミレーヌ・ファン・デル・メルシュとの結婚歴あり。アンヌ・ヴィアゼムスキーの『若い娘』によると、ヴィアゼムスキーにも求愛していたらしい。
1901年9月25日、フランスのブロモン=ラモット生まれ。画家を志すが、映画界に進み、1934年に喜劇『公務』で短編デビュー。1943年ジャン・ジロドゥ台本による『罪の天使たち』で長編デビュー。1951年『田舎司祭の日記』がヴェネチア映画祭で3部門受賞。1956年の『抵抗ー死刑囚の手記より』から独自の演出スタイルの徹底化を図り、職業俳優を使わなくなる。同作品でカンヌ映画祭監督賞受賞。1983年『ラルジャン』でカンヌ映画祭創造大賞受賞。1999年12月18日、パリで死去。私生活はヴェールに包まれているが、レイディア・ファン・デル・ゼー、ミレーヌ・ファン・デル・メルシュとの結婚歴あり。アンヌ・ヴィアゼムスキーの『若い娘』によると、ヴィアゼムスキーにも求愛していたらしい。
[監督作品]
1934年『公務』/1943年『罪の天使たち』/1945年『ブローニュの森の貴婦人たち』/1951年『田舎司祭の日記』/1956年『抵抗ー死刑囚の手記より』/1959年『スリ』/1962年『ジャンヌ・ダルク裁判』/1966年『バルタザールどこへ行く』/1967年『少女ムシェット』/1969年『やさしい女』/1972年『白夜』/1974年『湖のランスロ』/1977年『たぶん悪魔が』/1983年『ラルジャン』
1934年『公務』/1943年『罪の天使たち』/1945年『ブローニュの森の貴婦人たち』/1951年『田舎司祭の日記』/1956年『抵抗ー死刑囚の手記より』/1959年『スリ』/1962年『ジャンヌ・ダルク裁判』/1966年『バルタザールどこへ行く』/1967年『少女ムシェット』/1969年『やさしい女』/1972年『白夜』/1974年『湖のランスロ』/1977年『たぶん悪魔が』/1983年『ラルジャン』
月別インデックス
- May 2024 [1]
- January 2023 [1]
- November 2021 [1]
- April 2021 [1]
- September 2020 [2]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- January 2020 [1]
- July 2019 [1]
- March 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [3]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- October 2017 [2]
- September 2017 [1]
- June 2017 [2]
- March 2017 [2]
- November 2016 [1]
- August 2016 [1]
- July 2016 [2]
- February 2016 [1]
- October 2015 [1]
- August 2015 [1]
- June 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [1]
- January 2015 [2]
- September 2014 [1]
- July 2014 [2]
- May 2014 [1]
- March 2014 [1]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- September 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [1]
- May 2013 [1]
- February 2013 [1]
- December 2012 [2]
- October 2012 [2]
- August 2012 [2]
- June 2012 [1]
- April 2012 [2]
- March 2012 [1]
- February 2012 [1]
- January 2012 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]