
ルー・リード 『トランスフォーマー』
2013.08.04
ルー・リード
『トランスフォーマー』
1972年作品
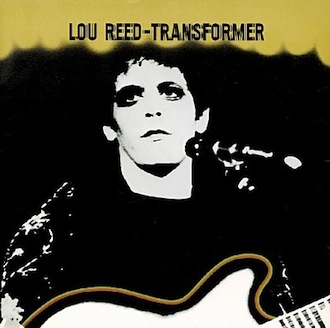 パンク以降の〈ギター・ロック〉に影響力絶大なバンドのヴェルヴェット・アンダーグラウンドのリーダーだったにもかかわらず1970年に脱退したルー・リード(vo、g)が、その2年後にリリースしたセカンド・ソロ・アルバムである。クールに見えてやんちゃで挑戦的だからムラ(≠ブレ)が多く、地雷盤も作ってきたルーのソロ活動の中で、崇高なロック・オペラの次作『ベルリン』と並び称される70年代の代表作だ。
パンク以降の〈ギター・ロック〉に影響力絶大なバンドのヴェルヴェット・アンダーグラウンドのリーダーだったにもかかわらず1970年に脱退したルー・リード(vo、g)が、その2年後にリリースしたセカンド・ソロ・アルバムである。クールに見えてやんちゃで挑戦的だからムラ(≠ブレ)が多く、地雷盤も作ってきたルーのソロ活動の中で、崇高なロック・オペラの次作『ベルリン』と並び称される70年代の代表作だ。
ソロ・デビュー時にルーは自分が知るものすべてと関係を切ろうとしていたが、1972年に出したファースト・ソロ・アルバムの『ルー・リード』は、レコード化してなかったヴェルヴェット・アンダーグラウンド時代の曲で占められている。だからゼロからのスタートという当時のルーの意識がリアルに表れているという点で、『トランスフォーマー』こそが真のソロ・デビュー作だ。米国ビルボードのチャートの29位まで上昇し、60年代半ばからのルーの音楽キャリアの中で初めて商業的にも成功した作品である。
プロデュースは、本作録音の2ヶ月前に出した『ジギー・スターダスト』で〈グラム・ロック・スター〉として脚光を浴び始めていたデヴィッド・ボウイと、当時の彼のバンドの核だったミック・ロンソン。レコード会社の人間の推薦だったが、もともとボウイはヴェルヴェット・アンダーグラウンドのファンであり、音楽制作の実務的なパートナーを引き連れてレコーディングに臨んだ形である。
いつの時代も〈一見さん〉のことは気にせずファンにも媚びず我が道を行くルーだが、アーティスティックなところとキャッチーなところが程よくブレンドされた作りは、芸術家肌に見えて現実的なバランス感覚に長けたボウイのプロデュース力が大きい。特にルーのお気に入りの部分がボウイのポップなコーラスで、本人が大好きな音楽であるにもかかわらずルーのアルバムではあまり聴けないドゥーワップの味わいも楽しめる。
数多いルーのレパートリーの中でライヴのセットリストに入り続けている曲が多いことも本作の親しみやすさを象徴する事実で、オープニング・ナンバーの「ヴィシャス」もその一つ。例によって寝起きみたいな声で歌われるが、金属質の響きのギターとタイトルどおりの背徳イメージの歌詞で初期ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの流れを汲み、80年代初頭の英国のハード・パンク・バンドのブリッツがカヴァーしたのもうなずける。
さらにステージで披露される機会が頻繁なライヴの定番ナンバーが3曲収められている。その内の2曲の「パーフェクト・デイ」と「サテライト・オブ・ラヴ」は、ギタリストのイメージが強いプロデューサーのロンソンがピアノで活躍し、ギター主導のロックンロールとは一味違って切々と歌い綴るルーのソロ・ナンバーの一つの方向性を示した曲群である。
そしてもちろん飄々とした佇まいながらも必殺なのが、ルーのキャリアの中で唯一のトップ20シングル・ヒット曲の「ウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイド」。曲名を直訳すれば「ワイルド・サイドを歩け」でロックそのものだが、まったりしたジャジーな曲調と実際の歌詞は〈ワイルド横丁を散歩しなよ〉みたいなトーンでもある。といっても、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのデビュー作をプロデュースした、アンディ・ウォーホルのスタジオのファクトリーに出入りしていたアウトサイダーたちを紹介する歌で、〈Take a walk on the wild side〉というフレーズがニューヨーク・シティの売春婦が客に声を掛ける時のフレーズというのも、当時のルーらしいセンスだ。
取り立てて親しいミュージャンが当時いなかったルーだけにボウイの顔の広さで本作の音楽もふくらんだ。たとえば「ウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイド」で言えば、終盤でサックスを吹いたロニー・ロスはボウイのサックスの家庭教師であり、エレクトリック・ベースとストリングス・ベースを操ったハービー・フラワーズはボウイのアルバムでも演奏していた人。もう一人の参加ベーシストのクラウス・フォアマンも、ジョン・レノン/ヨーコ・オノ関連のアルバムでお馴染みの演奏家ながらやはりボウイ人脈である。
大半のギター・パートがイケイケでギラギラしたミック・ロンソンの音というのもポイントだ。何しろこのアルバムではルーがほとんどギターを弾いてないらしく、以降しばらく続くギタリストとしてのルーの存在感が希薄な最初の作品という点も特筆したい。落ち着いた趣の曲が半数近くを占めるが、ボウイとロンソンがアレンジも大々的に手掛けているだけに、やはり全体的にはグラム・ロックの薄化粧に覆われている。ノー・メイクのハードボイルドな音のアルバムが多い中で、艶めかしくどこか淫靡なルーの歌声をはじめとして妖しい。『トランスフォーマー』というタイトルの意味を「性転換者」と深読みしたくなるほどだ。
アートワークも象徴的である。表ジャケットは中性的なアンドロイドのようなルーだし、裏ジャケットには巨根が勃起してジーンズが破けそうなゲイ風の男と、彼に襲われまいと股間を手で防御する女装した男との〈二重奏〉で、ジェンダーに挑戦したかのようにも見える。ルーはそういう意味合いに関しては無意識だったらしいが、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド時代から性差の概念を掻きまわしていただけに、ルーがグラム・ロックとニアミスしたのは必然だったとも言える。
『トランスフォーマー』以降、ルーとボウイの間でポジティヴな絡みはほとんどない。もともとルーにとってボウイは好きなアーティストの一人で後々も一定のリスペクトはしているが、『トランスフォーマー』のレコーディングの最中はたびたび軋轢も生じていたようである。そもそも〈同類〉に見えて、勝手気ままなストロング・スタイルのルーと戦略家でカメレオンのボウイとでは根っこが違う。だが水と油ほど異なる資質のボウイが手を差し伸べたからこそのケミストリーでこの快作が生まれ、暗中模索状態だったルーがソロ・アーティストとして自立するきっかけになったことは間違いない。
【関連サイト】
Lou Reed 『Transformer』
『トランスフォーマー』
1972年作品
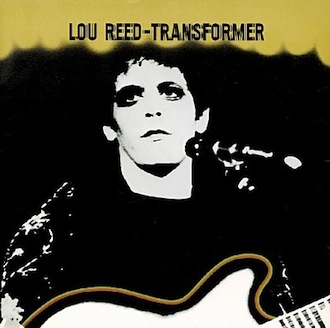
ソロ・デビュー時にルーは自分が知るものすべてと関係を切ろうとしていたが、1972年に出したファースト・ソロ・アルバムの『ルー・リード』は、レコード化してなかったヴェルヴェット・アンダーグラウンド時代の曲で占められている。だからゼロからのスタートという当時のルーの意識がリアルに表れているという点で、『トランスフォーマー』こそが真のソロ・デビュー作だ。米国ビルボードのチャートの29位まで上昇し、60年代半ばからのルーの音楽キャリアの中で初めて商業的にも成功した作品である。
プロデュースは、本作録音の2ヶ月前に出した『ジギー・スターダスト』で〈グラム・ロック・スター〉として脚光を浴び始めていたデヴィッド・ボウイと、当時の彼のバンドの核だったミック・ロンソン。レコード会社の人間の推薦だったが、もともとボウイはヴェルヴェット・アンダーグラウンドのファンであり、音楽制作の実務的なパートナーを引き連れてレコーディングに臨んだ形である。
いつの時代も〈一見さん〉のことは気にせずファンにも媚びず我が道を行くルーだが、アーティスティックなところとキャッチーなところが程よくブレンドされた作りは、芸術家肌に見えて現実的なバランス感覚に長けたボウイのプロデュース力が大きい。特にルーのお気に入りの部分がボウイのポップなコーラスで、本人が大好きな音楽であるにもかかわらずルーのアルバムではあまり聴けないドゥーワップの味わいも楽しめる。
数多いルーのレパートリーの中でライヴのセットリストに入り続けている曲が多いことも本作の親しみやすさを象徴する事実で、オープニング・ナンバーの「ヴィシャス」もその一つ。例によって寝起きみたいな声で歌われるが、金属質の響きのギターとタイトルどおりの背徳イメージの歌詞で初期ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの流れを汲み、80年代初頭の英国のハード・パンク・バンドのブリッツがカヴァーしたのもうなずける。
さらにステージで披露される機会が頻繁なライヴの定番ナンバーが3曲収められている。その内の2曲の「パーフェクト・デイ」と「サテライト・オブ・ラヴ」は、ギタリストのイメージが強いプロデューサーのロンソンがピアノで活躍し、ギター主導のロックンロールとは一味違って切々と歌い綴るルーのソロ・ナンバーの一つの方向性を示した曲群である。
そしてもちろん飄々とした佇まいながらも必殺なのが、ルーのキャリアの中で唯一のトップ20シングル・ヒット曲の「ウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイド」。曲名を直訳すれば「ワイルド・サイドを歩け」でロックそのものだが、まったりしたジャジーな曲調と実際の歌詞は〈ワイルド横丁を散歩しなよ〉みたいなトーンでもある。といっても、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのデビュー作をプロデュースした、アンディ・ウォーホルのスタジオのファクトリーに出入りしていたアウトサイダーたちを紹介する歌で、〈Take a walk on the wild side〉というフレーズがニューヨーク・シティの売春婦が客に声を掛ける時のフレーズというのも、当時のルーらしいセンスだ。
取り立てて親しいミュージャンが当時いなかったルーだけにボウイの顔の広さで本作の音楽もふくらんだ。たとえば「ウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイド」で言えば、終盤でサックスを吹いたロニー・ロスはボウイのサックスの家庭教師であり、エレクトリック・ベースとストリングス・ベースを操ったハービー・フラワーズはボウイのアルバムでも演奏していた人。もう一人の参加ベーシストのクラウス・フォアマンも、ジョン・レノン/ヨーコ・オノ関連のアルバムでお馴染みの演奏家ながらやはりボウイ人脈である。
大半のギター・パートがイケイケでギラギラしたミック・ロンソンの音というのもポイントだ。何しろこのアルバムではルーがほとんどギターを弾いてないらしく、以降しばらく続くギタリストとしてのルーの存在感が希薄な最初の作品という点も特筆したい。落ち着いた趣の曲が半数近くを占めるが、ボウイとロンソンがアレンジも大々的に手掛けているだけに、やはり全体的にはグラム・ロックの薄化粧に覆われている。ノー・メイクのハードボイルドな音のアルバムが多い中で、艶めかしくどこか淫靡なルーの歌声をはじめとして妖しい。『トランスフォーマー』というタイトルの意味を「性転換者」と深読みしたくなるほどだ。
アートワークも象徴的である。表ジャケットは中性的なアンドロイドのようなルーだし、裏ジャケットには巨根が勃起してジーンズが破けそうなゲイ風の男と、彼に襲われまいと股間を手で防御する女装した男との〈二重奏〉で、ジェンダーに挑戦したかのようにも見える。ルーはそういう意味合いに関しては無意識だったらしいが、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド時代から性差の概念を掻きまわしていただけに、ルーがグラム・ロックとニアミスしたのは必然だったとも言える。
『トランスフォーマー』以降、ルーとボウイの間でポジティヴな絡みはほとんどない。もともとルーにとってボウイは好きなアーティストの一人で後々も一定のリスペクトはしているが、『トランスフォーマー』のレコーディングの最中はたびたび軋轢も生じていたようである。そもそも〈同類〉に見えて、勝手気ままなストロング・スタイルのルーと戦略家でカメレオンのボウイとでは根っこが違う。だが水と油ほど異なる資質のボウイが手を差し伸べたからこそのケミストリーでこの快作が生まれ、暗中模索状態だったルーがソロ・アーティストとして自立するきっかけになったことは間違いない。
(行川和彦)
【関連サイト】
Lou Reed 『Transformer』
『トランスフォーマー』収録曲
01. ヴィシャス/02. アンディの胸/03. パーフェクト・デイ/04. ハンギン・ラウンド/05. ワイルド・サイドを歩け/06. メイキャップ/07. サテライト・オブ・ラヴ/08. ワゴンの車輪/09. ニューヨーク・テレフォン・カンヴァセイション/10. アイム・ソー・フリー/11. グッドナイト・レイディズ
01. ヴィシャス/02. アンディの胸/03. パーフェクト・デイ/04. ハンギン・ラウンド/05. ワイルド・サイドを歩け/06. メイキャップ/07. サテライト・オブ・ラヴ/08. ワゴンの車輪/09. ニューヨーク・テレフォン・カンヴァセイション/10. アイム・ソー・フリー/11. グッドナイト・レイディズ
月別インデックス
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- June 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- February 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- August 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- April 2023 [1]
- March 2023 [1]
- February 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- November 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- June 2022 [1]
- May 2022 [1]
- April 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- January 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- August 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- April 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- January 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- September 2020 [1]
- August 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- March 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- November 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [1]
- August 2019 [1]
- July 2019 [1]
- June 2019 [1]
- May 2019 [1]
- April 2019 [2]
- February 2019 [1]
- January 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- August 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- May 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [1]
- February 2018 [1]
- January 2018 [2]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- July 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [1]
- April 2017 [1]
- March 2017 [1]
- February 2017 [1]
- January 2017 [1]
- December 2016 [1]
- November 2016 [1]
- October 2016 [1]
- September 2016 [1]
- August 2016 [1]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- March 2016 [1]
- February 2016 [1]
- January 2016 [1]
- December 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [1]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- March 2015 [1]
- February 2015 [1]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [1]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [1]
- July 2014 [2]
- June 2014 [1]
- May 2014 [1]
- April 2014 [1]
- March 2014 [1]
- February 2014 [1]
- January 2014 [1]
- December 2013 [2]
- November 2013 [1]
- October 2013 [1]
- September 2013 [2]
- August 2013 [2]
- July 2013 [1]
- June 2013 [1]
- May 2013 [2]
- April 2013 [1]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [1]
- December 2012 [1]
- November 2012 [2]
- October 2012 [1]
- September 2012 [1]
- August 2012 [2]
- July 2012 [1]
- June 2012 [2]
- May 2012 [1]
- April 2012 [2]
- March 2012 [1]
- February 2012 [2]
- January 2012 [2]
- December 2011 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [1]
- August 2011 [1]
- July 2011 [2]
- June 2011 [2]
- May 2011 [2]
- April 2011 [2]
- March 2011 [2]
- February 2011 [3]