
ザ・ウォーターボーイズ 『ディス・イズ・ザ・シー』
2014.08.21
ザ・ウォーターボーイズ
『ディス・イズ・ザ・シー』
1985年作品
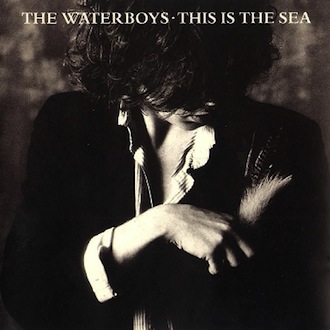 さる2014年7月末のフジ・ロック・フェスティバル2日目の昼下がり、デビューから31年を経て初めて、ザ・ウォーターボーイズが日本でライヴを敢行した。厳密にはフロントマンのマイク・スコットが1995年にソロで来日済みで、まあザ・ウォーターボーイズ=マイクみたいなものなのだが、一大事であることに変わりなし! 途方もない暑さの中、人数は限られていたものの、年季の入った熱いファンがステージ前に集まった。そこに現れたマイクがオープニング曲に選んだのは、なんといきなり「The Whole of the Moon」。そう、サード・アルバム『This Is the Sea』(1985年発表/邦題は『自由への航海』と『ディス・イズ・ザ・シー』の2種ある)からのシングル曲で、彼らにとって初のUKトップ30ヒットとなった(1991年、ベスト盤発表を機に再発された際には最高3位に)問答無用の名曲かつ代表曲である。
さる2014年7月末のフジ・ロック・フェスティバル2日目の昼下がり、デビューから31年を経て初めて、ザ・ウォーターボーイズが日本でライヴを敢行した。厳密にはフロントマンのマイク・スコットが1995年にソロで来日済みで、まあザ・ウォーターボーイズ=マイクみたいなものなのだが、一大事であることに変わりなし! 途方もない暑さの中、人数は限られていたものの、年季の入った熱いファンがステージ前に集まった。そこに現れたマイクがオープニング曲に選んだのは、なんといきなり「The Whole of the Moon」。そう、サード・アルバム『This Is the Sea』(1985年発表/邦題は『自由への航海』と『ディス・イズ・ザ・シー』の2種ある)からのシングル曲で、彼らにとって初のUKトップ30ヒットとなった(1991年、ベスト盤発表を機に再発された際には最高3位に)問答無用の名曲かつ代表曲である。
スコットランドのエディンバラ生まれ、1970年代後半から様々な形態で活動したのちにザ・ウォーターボーイズ名義で作品をリリースし始めたマイク。最初の2枚(1983年の『The Waterboys』と1984年の『A Pagan Place』)はソロで制作し、初めてバンド形態でレコーディングしたのが『This Is the Sea』だった。もっともラインナップは頻繁に替わっており、当時のコア・メンバーーーカール・ウォリンガー(キーボード/のちにワールド・パーティーを結成)、アンソニー・シッスルスウェウト(サックス、ベース)、ロディ・ロリマー(トランペット)、ケヴィン・ウィルキンソン(ドラムスなど)ーーは今や誰も残っていない。変わったのはメンバーだけでなく、次の『Fisherman's Blues』(1988年)以降はスコットランドとアイルランドのトラッド・フォークに傾倒して自身のケルティック・ルーツを掘り下げ、90年代に入るとより直球のロックを志向するなど、音楽性も幾度も変わっている。そしてどの時代にもいいアルバムがあるのだが、初期の名盤が『This Is the Sea』であることは間違いなく、計8曲のフジ・ロックのセットには本作からもう1曲、「The Pan Within」も含まれていたものだ。
その1980年代前半の彼らの作風は、『A Pagan Place』の収録曲に因んで〈Big Music〉と総称されていた。つまり、とにかくビッグでシネマティック。中でも本作は、マイクが若い頃に聴いたあらゆる音楽(ディランやボウイからヴァン・モリソン、ザ・クラッシュに至るまで)を反映させ、独学で身に付けたレコーディング技術を駆使して完成させたもので、荘厳なスケール感は圧巻だった。ポストパンク的な鋭角なギター、メロディックなサックス、リズミカルなピアノ、そして流麗なフィドル......。マルチ・トラッキングの限りを尽くして構築した、自己流のウォール・オブ・サウンドが聴き手に与えるクラクラするような感覚は、例えば、満天の星空を眺めた時、或いは、高い山の頂きを麓から眺めた時のそれに近い。
そんなスケール感に寄与する要素として、自然界の事象をメタファーに用いたスピリチャルな歌詞も挙げておくべきだろう。ここでいう「スピリチャル」はクリスチャンという意味合いではなく、ごく普遍的なもので、ギリシャ神話からネイティヴ・アメリカンに至るまで様々なカルチャーからモチーフを引用。偉大なことを成し遂げた先人たちに敬意を捧げる「The Whole of the Moon」然り、魂の不変性を歌う「Spirit」然り、自分の内に潜む牧神パーンを呼び覚まそうと訴える「The Pan Within」然り、人生の意義を探究し、知識と叡智を求めて彷徨う若者の旅日記のような趣が、本作にはある。また、エディンバラ大学で英文学を学び、ロバート・バーンズやウィリアム・ブレイク、W・B・イェイツ(2011年の最新作『An Appointment with Mr.Yeats』ではイェイツの詩を歌詞に使用した)といった詩人からも多大な影響を受けたマイクが好む、古風な表現や詠唱に似たヴォーカル・スタイルにも、サウンドを背負えるだけの重みがあった。
だから彼は、恋愛も社会問題もやはりポエティックに描く。前者にあたる「Trumpet」は愛をめぐる雄弁なメタファーで埋め尽くし、後者にあたる「Old England」では、心はすさみ過去の栄光にすがる老人に英国を譬えて、サッチャー政権下で荒廃する社会を嘆くーーといった具合に。そしてグランド・フィナーレと呼ぶに相応しいラストの表題曲で、我々はマイクと一緒に人生の川を下り、徐々にクレッシェンドする12弦ギターの幽玄な響きに乗って河口に辿り着き、海に流れ込む。果たしてこの「海」は自由を意味するのか、一種の真実なのか? いかようにも解釈は可能だが、〈Behold the sea(海を見よ)〉とこれまた古風な言い回しでアルバムを括る彼は、自分より遥かに大きな存在に圧倒されて静かな高揚感に浸っている。
そんな『This Is the Sea』は好セールスを記録し、一気に知名度を上げたザ・ウォーターボーイズはU2に続くバンドとも評され、このあとも〈Big Music〉路線を踏襲していたら大きな成功を収めただろうと言われたものだ。それだけのスター性とカリスマ性を、マイクも備えていた。でも彼はテレビ番組でパフォーマンスをすることすら拒み、ロックスターダムに背を向けて、間もなくアイルランドのダブリンに移住。トラッドの世界に飛び込んだ。2000年に筆者がインタヴューした時には、「『This Is the Sea』で俺は若かりし自分の〈ロック・ドリーム〉を完遂し、もうやるべきことは残っていなくて、次の章を開くしかなかった」とも話していたけど、以来ずっと音楽の神が導くままに活動を続けてきたマイクは、55歳になった今も相変わらずカッコ良くて、どこから見ても紛れもないロックスターだった......。
【関連サイト】
The Waterboys
『ディス・イズ・ザ・シー』
1985年作品
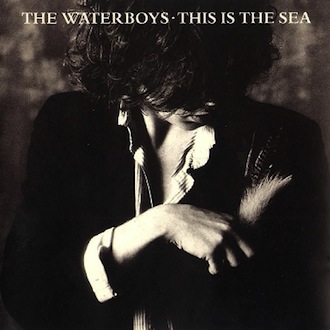
スコットランドのエディンバラ生まれ、1970年代後半から様々な形態で活動したのちにザ・ウォーターボーイズ名義で作品をリリースし始めたマイク。最初の2枚(1983年の『The Waterboys』と1984年の『A Pagan Place』)はソロで制作し、初めてバンド形態でレコーディングしたのが『This Is the Sea』だった。もっともラインナップは頻繁に替わっており、当時のコア・メンバーーーカール・ウォリンガー(キーボード/のちにワールド・パーティーを結成)、アンソニー・シッスルスウェウト(サックス、ベース)、ロディ・ロリマー(トランペット)、ケヴィン・ウィルキンソン(ドラムスなど)ーーは今や誰も残っていない。変わったのはメンバーだけでなく、次の『Fisherman's Blues』(1988年)以降はスコットランドとアイルランドのトラッド・フォークに傾倒して自身のケルティック・ルーツを掘り下げ、90年代に入るとより直球のロックを志向するなど、音楽性も幾度も変わっている。そしてどの時代にもいいアルバムがあるのだが、初期の名盤が『This Is the Sea』であることは間違いなく、計8曲のフジ・ロックのセットには本作からもう1曲、「The Pan Within」も含まれていたものだ。
その1980年代前半の彼らの作風は、『A Pagan Place』の収録曲に因んで〈Big Music〉と総称されていた。つまり、とにかくビッグでシネマティック。中でも本作は、マイクが若い頃に聴いたあらゆる音楽(ディランやボウイからヴァン・モリソン、ザ・クラッシュに至るまで)を反映させ、独学で身に付けたレコーディング技術を駆使して完成させたもので、荘厳なスケール感は圧巻だった。ポストパンク的な鋭角なギター、メロディックなサックス、リズミカルなピアノ、そして流麗なフィドル......。マルチ・トラッキングの限りを尽くして構築した、自己流のウォール・オブ・サウンドが聴き手に与えるクラクラするような感覚は、例えば、満天の星空を眺めた時、或いは、高い山の頂きを麓から眺めた時のそれに近い。
そんなスケール感に寄与する要素として、自然界の事象をメタファーに用いたスピリチャルな歌詞も挙げておくべきだろう。ここでいう「スピリチャル」はクリスチャンという意味合いではなく、ごく普遍的なもので、ギリシャ神話からネイティヴ・アメリカンに至るまで様々なカルチャーからモチーフを引用。偉大なことを成し遂げた先人たちに敬意を捧げる「The Whole of the Moon」然り、魂の不変性を歌う「Spirit」然り、自分の内に潜む牧神パーンを呼び覚まそうと訴える「The Pan Within」然り、人生の意義を探究し、知識と叡智を求めて彷徨う若者の旅日記のような趣が、本作にはある。また、エディンバラ大学で英文学を学び、ロバート・バーンズやウィリアム・ブレイク、W・B・イェイツ(2011年の最新作『An Appointment with Mr.Yeats』ではイェイツの詩を歌詞に使用した)といった詩人からも多大な影響を受けたマイクが好む、古風な表現や詠唱に似たヴォーカル・スタイルにも、サウンドを背負えるだけの重みがあった。
だから彼は、恋愛も社会問題もやはりポエティックに描く。前者にあたる「Trumpet」は愛をめぐる雄弁なメタファーで埋め尽くし、後者にあたる「Old England」では、心はすさみ過去の栄光にすがる老人に英国を譬えて、サッチャー政権下で荒廃する社会を嘆くーーといった具合に。そしてグランド・フィナーレと呼ぶに相応しいラストの表題曲で、我々はマイクと一緒に人生の川を下り、徐々にクレッシェンドする12弦ギターの幽玄な響きに乗って河口に辿り着き、海に流れ込む。果たしてこの「海」は自由を意味するのか、一種の真実なのか? いかようにも解釈は可能だが、〈Behold the sea(海を見よ)〉とこれまた古風な言い回しでアルバムを括る彼は、自分より遥かに大きな存在に圧倒されて静かな高揚感に浸っている。
そんな『This Is the Sea』は好セールスを記録し、一気に知名度を上げたザ・ウォーターボーイズはU2に続くバンドとも評され、このあとも〈Big Music〉路線を踏襲していたら大きな成功を収めただろうと言われたものだ。それだけのスター性とカリスマ性を、マイクも備えていた。でも彼はテレビ番組でパフォーマンスをすることすら拒み、ロックスターダムに背を向けて、間もなくアイルランドのダブリンに移住。トラッドの世界に飛び込んだ。2000年に筆者がインタヴューした時には、「『This Is the Sea』で俺は若かりし自分の〈ロック・ドリーム〉を完遂し、もうやるべきことは残っていなくて、次の章を開くしかなかった」とも話していたけど、以来ずっと音楽の神が導くままに活動を続けてきたマイクは、55歳になった今も相変わらずカッコ良くて、どこから見ても紛れもないロックスターだった......。
(新谷洋子)
【関連サイト】
The Waterboys
『ディス・イズ・ザ・シー』収録曲
01. Don't Bang The Drum/02. The Whole of the Moon/03. Spirit/04. The Pan Within/05. Medicine Bow/06. Old England/07. Be My Enemy/08. Trumpets/09. This Is the Sea
01. Don't Bang The Drum/02. The Whole of the Moon/03. Spirit/04. The Pan Within/05. Medicine Bow/06. Old England/07. Be My Enemy/08. Trumpets/09. This Is the Sea
月別インデックス
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- June 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- February 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- August 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- April 2023 [1]
- March 2023 [1]
- February 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- November 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- June 2022 [1]
- May 2022 [1]
- April 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- January 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- August 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- April 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- January 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- September 2020 [1]
- August 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- March 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- November 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [1]
- August 2019 [1]
- July 2019 [1]
- June 2019 [1]
- May 2019 [1]
- April 2019 [2]
- February 2019 [1]
- January 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- August 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- May 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [1]
- February 2018 [1]
- January 2018 [2]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- July 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [1]
- April 2017 [1]
- March 2017 [1]
- February 2017 [1]
- January 2017 [1]
- December 2016 [1]
- November 2016 [1]
- October 2016 [1]
- September 2016 [1]
- August 2016 [1]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- March 2016 [1]
- February 2016 [1]
- January 2016 [1]
- December 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [1]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- March 2015 [1]
- February 2015 [1]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [1]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [1]
- July 2014 [2]
- June 2014 [1]
- May 2014 [1]
- April 2014 [1]
- March 2014 [1]
- February 2014 [1]
- January 2014 [1]
- December 2013 [2]
- November 2013 [1]
- October 2013 [1]
- September 2013 [2]
- August 2013 [2]
- July 2013 [1]
- June 2013 [1]
- May 2013 [2]
- April 2013 [1]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [1]
- December 2012 [1]
- November 2012 [2]
- October 2012 [1]
- September 2012 [1]
- August 2012 [2]
- July 2012 [1]
- June 2012 [2]
- May 2012 [1]
- April 2012 [2]
- March 2012 [1]
- February 2012 [2]
- January 2012 [2]
- December 2011 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [1]
- August 2011 [1]
- July 2011 [2]
- June 2011 [2]
- May 2011 [2]
- April 2011 [2]
- March 2011 [2]
- February 2011 [3]