
ピーター・ガブリエル 『So』
2018.08.23
ピーター・ガブリエル
『So』1986年作品
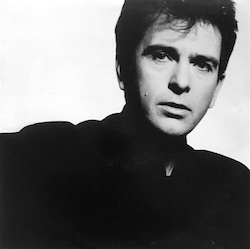
ちなみに、ジャケットのデザインもファクトリー・レーベルの作品でお馴染みのピーター・サヴィルに依頼して、従来のイメージを刷新した彼、より間口が広い作品に仕上げたのは偶然ではなかった。1980年代初めにピーターは、アラン・パーカー監督の映画『バーディ』のサントラを担当。映画・音楽共に非常に重い内容だったため、なにか解放感を得られる作品を作りたかったのだという。そしてまずはコラボレーターを選んだのだが、これがすごい。共同プロデューサーにはダニエル・ラノワを起用し(彼はギタリストとしても活躍)、ドラムスはコートジボワール系フランス人の奇才マヌ・カチェや、ザ・ポリスのスチュワート・コープランド、ベースは当時キング・クリムゾンにも在籍していたトニー・レヴィンやラリー・クライン、トランペットはスタックス・レコードの諸作品で活躍したウェイン・ジャクソン......といった具合に、世界中から才能を選りすぐった形だ。
さらにはサンプラーの前身であるフェアライトCMIやリン・ドラムを駆使して、1980年代半ばのレコーディング・テクノロジーの粋を尽くし、ピカピカに磨き上げられ、でも一定の温もりを維持するサウンドを構築したピーターとダニエル。数秒聴けば時代を特定できるそんな耳触わりの良さは、言わばトロイの木馬だ。そもそもポップと言っても3分台の曲は1曲だけで、大半は5〜6分台に及び(ジェネシス時代は20分を超える曲もあったものだが......)、この人の実験欲やエキセントリシティと、生々しいエモーションや力強い主張が、内側では波打っているのである。
何しろオープニング曲「レッド・レイン」が描き出すのは、タイトル通りの血の雨が、細やかなリズムパターンに置き換えられて降りしきる、世界の終わりの情景。核の恐怖に誰もが震えた時代の気分を捉えたかと思えば、次に待ち受けているのが、尺八の音で始まる説明無用の全米ナンバーワン・ヒット「スレッジハンマー」だ。子供時代に大好きだったというオーティス・レディングにインスパイアされ、ふんだんにホーンを盛ったこの曲は実はかなり露骨な求愛ソングで、ユーモラスではあるものの、その下世話な内容に今更ながら驚かされる。
こんな調子で本作は全編にわたって激しく揺れ動き、「スレッジハンマー」でマスキュリンなエネルギーを迸らせたかと思うと、続くゴスペル調の「ドント・ギヴ・アップ」は女性のパワーの見せどころ。舞台はサッチャー政権下の荒廃した英国社会、失業して家族の大黒柱という存在意義を失った男が主人公だ。〈勝つことが全て〉と教わって育った彼が敗北を喫して絶望しているところに、神なのか母なのか、ゲストのケイト・ブッシュが〈諦めないで〉と救いの手を差し伸べているのである。このジェンダー・バランス、かなり時代の先を行っているが、当時名盤『愛のかたち』を発表して間もなかったケイトとピーターは、ミュージシャンとしても互角の存在だったと言って差し支えないだろう。
そして後半でも彼は同様のコントラストを提示する。その片方の極に該当するのが、ファンキー極まりないヒット・シングル「ビッグ・タイム」。再びネガティヴなマスキュリン・エネルギーを放出し、欲だけに突き動かされた80年代の拝金志向を面白おかしく風刺する曲で(2018年に聴くと、トランプ米大統領を歌っているようでもある)、人権擁護活動にも熱心な社会派シンガーとしてのピーターは、多彩なアプローチで問題提起をしている。時にシリアスに、時にユーモアを交えて。
そんな「ビッグ・タイム」を両側から挿む「マーシー・ストリート」と「ウィ・ドゥ・ホワット・ウィアー・トールド」は、対照的にアンビエント志向。女流詩人アン・セクストンに捧げた、ブラジル録音の前者は、現地の名パーカッショニスト、ジェルマ・コレアの参加を得てブラジル音楽のフォホーの影響をさりげなくミックスしている。そう、ブラック・ミュージックと並んで本作で大きな役割を果たしているのは、ピーターがかねてから関心を寄せていた欧米圏外の音楽だ(彼は1982年からワールド・ミュージックの祭典WOMADフェスティバルを主催していた)。1986年と言えばポール・サイモンも『グレイスランド』を発表し、グラミーの最優秀アルバム賞を本作と競うのだが(軍配はポールに)、南アフリカの音楽に特化したポールと、ソウルやゴスペルもある種の〈ワールド・ミュージック〉と見做して、多様なサウンドを切れ目なく融合するピーターのスタイルの違いを比較するのも面白い。
ならば、デヴィッド・ボウイの『ロウ』の世界にも通ずる後者はどんな曲なのか? 原題に〈Milgram's 37〉とサブタイトルが添えられているように、権威に服従する人間の心理を探った通称ミルグラム実験を題材にしており、歌詞は〈我々は言われたままに行動する〉と繰り返すのみ。マインド・コントロールの怖さをじわじわと感じさせ、次の「ディス・イズ・ザ・ピクチャー」はまるでその続編みたいに聴こえなくものない。ローリー・アンダーソンと共作し、ナイル・ロジャースがギターを弾くこの曲は、元々現代アーティストのナム・ジュン・パイクの作品のために用意されたそうで、ジョージ・オーウェルの小説『1984年』のようなコンセプトを提示されたと聞けば、なるほど、納得がいく。
従って、大ヒット作にしてはあれこれ考えさせられるアルバムなのだが、ピーターは最後にラヴソング「イン・ユア・アイズ」で、自分にも聴き手にも希望を与えることを忘れない。当初のアナログ盤ではB面の1曲目に配置され、その後CD化された際に曲順が変わり、個人的にはラストにこそ相応しいと思う。歌詞は少々ベタだし、いかにも1980年代的な大仰なプロダクションのバラードではあるものの、だからこそ、ここに至るまでにどんどん深まった不穏な空気を、一気に洗い流すだけのインパクトがある。しかも彼はアウトロになって、強力な隠し玉を繰り出す。「流れる黄金」とその声を形容したこともある、セネガルが生んだレジェンド、ユッスー・ンドゥールという隠し玉だ。ウォロフ語のユッスーのヴォーカルは、ケイトのそれとはまた別の意味で神々しく、欧米の病の解毒剤として絶大な効力を発揮している。
(新谷洋子)
【関連サイト】
Peter Gabriel 『So』(CD)
『So』収録曲
01. レッド・レイン/02. スレッジハンマー/03. ドント・ギヴ・アップ/04. ザット・ヴォイス・アゲイン/05. マーシー・ストリート/06. ビッグ・タイム/07. ウィ・ドゥ・ホワット・ウィアー・トールド/08. ディス・イズ・ザ・ピクチャー/09. イン・ユア・アイズ
01. レッド・レイン/02. スレッジハンマー/03. ドント・ギヴ・アップ/04. ザット・ヴォイス・アゲイン/05. マーシー・ストリート/06. ビッグ・タイム/07. ウィ・ドゥ・ホワット・ウィアー・トールド/08. ディス・イズ・ザ・ピクチャー/09. イン・ユア・アイズ
月別インデックス
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- June 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- February 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- August 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- April 2023 [1]
- March 2023 [1]
- February 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- November 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- June 2022 [1]
- May 2022 [1]
- April 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- January 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- August 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- April 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- January 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- September 2020 [1]
- August 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- March 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- November 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [1]
- August 2019 [1]
- July 2019 [1]
- June 2019 [1]
- May 2019 [1]
- April 2019 [2]
- February 2019 [1]
- January 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- August 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- May 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [1]
- February 2018 [1]
- January 2018 [2]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- July 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [1]
- April 2017 [1]
- March 2017 [1]
- February 2017 [1]
- January 2017 [1]
- December 2016 [1]
- November 2016 [1]
- October 2016 [1]
- September 2016 [1]
- August 2016 [1]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- March 2016 [1]
- February 2016 [1]
- January 2016 [1]
- December 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [1]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- March 2015 [1]
- February 2015 [1]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [1]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [1]
- July 2014 [2]
- June 2014 [1]
- May 2014 [1]
- April 2014 [1]
- March 2014 [1]
- February 2014 [1]
- January 2014 [1]
- December 2013 [2]
- November 2013 [1]
- October 2013 [1]
- September 2013 [2]
- August 2013 [2]
- July 2013 [1]
- June 2013 [1]
- May 2013 [2]
- April 2013 [1]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [1]
- December 2012 [1]
- November 2012 [2]
- October 2012 [1]
- September 2012 [1]
- August 2012 [2]
- July 2012 [1]
- June 2012 [2]
- May 2012 [1]
- April 2012 [2]
- March 2012 [1]
- February 2012 [2]
- January 2012 [2]
- December 2011 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [1]
- August 2011 [1]
- July 2011 [2]
- June 2011 [2]
- May 2011 [2]
- April 2011 [2]
- March 2011 [2]
- February 2011 [3]